地質古玩を愛でる ― 2025年11月01日 08時32分00秒
パリの博物系古書店、アラン・ブリウ書店から、メールで新着カタログのお知らせをいただきました。カタログはオンラインで公開されているので、リンクを張っておきます。オールカラー113頁、PDFファイルで約29MBという堂々たるものです(ダウンロードにちょっと時間がかかります)。
今回は題して「Les Archives de la Terre(大地のアーカイブ)」、すなわち地質学特集です。
昔の鉱物趣味の徒必携の吹管分析セットに始まり、各種測量機器、色鮮やかな地質図、化石図譜、古生物学関連書…等々、主に18世紀から20世紀初頭に至る「地質古玩」の品々が紹介されています。もちろん商品カタログなので、すべて売り物です。
(上記カタログの一頁)
大地の歴史と真剣に向き合った古の学者たちの蘊奥(うんおう)と、地質学という学問が放つ香気に、わけもなく惹かれる自分がいます。「ああ、いいなあ…」と、眺めるだけでも大いなる眼福ですので、ここにそのお裾分けをさせていただきます。
★
カタログを見て「おや?」と思ったのは、地質学と不可分であるはずの鉱物学関係の書籍が、今号にはまったく載っていないことです。したがって、日本でも人気のアンティーク鉱物画を収めた書籍類は、ここには含まれません。たぶん、それはそれで別に一冊のカタログを編むだけのボリュームがあるので、割愛されたのでしょう。
あるいは geology と mineralogy は、フランスの博物趣味の徒にとっては、日本よりも「別物感」が相対的に濃いのか? でも、日本の鉱物好きの人も、その色形は大いに愛でるものの、地質学にはあまり関心がない…という人も一定数いるはずなので、それほど違いはないのかな?とも思うし、この辺の事情は、その道(どの道?)の人にお聞きしてみたいところです。
Katzen und der Mond ― 2025年10月31日 19時31分14秒
この「天文古玩」も、今やリアルな天文現象のごとく、条件によって見えたり見えなかったりで、「うーん“504 Gateway Time-out”か…今日は雲量が多いなあ」といった具合に、のんびり観望していただければありがたく思います(本当にすみません)。
サーバーの心配は尽きませんが、いざさらば雪見にころぶところまで、とりあえず行けるところまで行くことにします。
★
ときにこの10月はあっという間でした。
この分だと11月と12月もこんな調子で、すぐに新年のご挨拶をしないといけないことになりそうです。まあ、残りふた月ですから、それもむべなる哉。
そんなわけで、ハロウィンと年末を合せた雰囲気の一枚。
黒猫と三日月。
エンボス加工に金彩の美しい仕上がりです。
消印は1914年12月30日付で、アメリカ東部のメイン州で差し出されたもの。
欄外の表示によれば、印刷はドイツ、販売はイギリスの会社が行っていますが、この年の7月に第一次世界大戦が勃発して、独英間の交易は途絶したので、それ以前に輸入した在庫処分品というわけでしょう。印刷の質の高さで知られた、ドイツ製絵葉書の黄金時代がまさに終焉を迎える間際の作品です。
★
一枚の絵葉書にも時代は自ずと表れるものですが、何はともあれ
To Wish You all Good Luck !
デジタル・エフェメラ ― 2025年10月27日 05時54分40秒
つらつら思うに、昨日書いたこと(サーバーがとんで、ブログが全消滅するんじゃないか…という不安)は、先日の荒俣宏氏の蔵書問題とも深く関係します。
★
すなわち、デジタル・コンテンツの危うさと、紙の本の底力…みたいな論点です。
この件は、すでに多くの人が繰り返し論じているはずですが、やっぱり常に警鐘を鳴らし続ける必要があると思います。
もちろん技術は今後もどんどん進歩して、デジタル・データはより安全に、より永続的なものになっていくとは思います。しかし、それ以前にネットの海に放出されたデータは、すでに膨大な量になっているし、そのすべてがより堅固なストレージに移行できるかといえば、これは相当の難事でしょう。少なくとも今あるデジタル・コンテンツは、拙ブログも含めて、まさにうたかたの如きものであり、エフェメラルなものだと言わざるを得ません。
もし、これが紙の本だったら?…というところに思いは自ずと向かいます。
世界中の人が簡単に共有することはできないかわり、それが堅固なことは確かです(酸性紙の劣化問題はまた別に考えることにしましょう)。紙の本を大事にしようという主張には、紙の手触りやインクの匂いを愛でるといった情緒的な要素以外に、物理的堅牢性を貴ぶという趣意もこもっています。そこは正当に評価されてしかるべきでしょう。
★
花は散るから美しい。
人生は終わりがあるから尊い。
そこから敷衍すると、デジタル・コンテンツも消えるから愛しい…と思いたいところですが、なかなかそうは思えそうにありません。永く残ることを期待して記録したのに、あっさり消滅したら、信用して虎の子を預けた銀行が破綻したような気分というか、呆然として「裏切られた!」という気分になることでしょう。(「そんなもん自己責任で対策をしとかなきゃ…」という非難の声が飛ぶところまでがセットですかね。)
★
誰かが虎の子を失っても、世間は何の痛痒も感じませんが、本人にとっては大打撃です。同様に、「天文古玩」が消えても、世間は何も困りませんが、私にとってはかなり深刻な問題です。
気息奄々 ― 2025年10月26日 07時41分50秒
私が利用しているブログサービス、「アサブロ」。
プロバイダ会社のASAHIネットが、会員に提供しているサービスで、素朴な構成ながら、広告が一切表示されない点が気に入っています。でも、最近動作が異様に重い。これは私だけなのか、他の方にとってもそうなのか?
何となくサーバーのメンテナンスがうまくいってない気がしますが、だとすると、予算的な制約がいちばん大きな要因でしょう。そして、その先にはブログサービスの終了と、「天文古玩」のデータがすべて消滅…ということも現実的に視野に入ってきます。
さすがに閉鎖前に、データの一括ダウンロードサービスぐらいは提供してくれるだろうと思うのですが、実際どうなるかは分かりません。何だかひどく陰鬱な気分です。
(この件はASAHIネットに現在問い合わせ中です)
★
…と書いたそばから、回答がありました。
ご不便をおかけしてしまい、誠に申し訳ございません。
現在、アサブロのサーバーの負荷が高い状況が慢性的に続いておりブログが表示されにくい等といった状況が発生しております。
お客様がご申告の現象も、上記が要因と思われます。
弊社でも対策を検討しておりますが、誠に恐れながら、現時点では具体的な改善予定をご案内出来かねる状況です。
お客様には大変申し訳ございませんが、何卒ご容赦ください。
このようなご回答しか差し上げられないことを心よりお詫び申し上げます。
現在、アサブロのサーバーの負荷が高い状況が慢性的に続いておりブログが表示されにくい等といった状況が発生しております。
お客様がご申告の現象も、上記が要因と思われます。
弊社でも対策を検討しておりますが、誠に恐れながら、現時点では具体的な改善予定をご案内出来かねる状況です。
お客様には大変申し訳ございませんが、何卒ご容赦ください。
このようなご回答しか差し上げられないことを心よりお詫び申し上げます。
うーむ…
原因がアサブロ側にあるとはっきりしたのは一歩前進ですが、しかしこれは全く安閑としていられない状況です。具体的な改善予定がないということは、もうそこに予算はかけないぞという態度表明とも読めます。どうも杞憂は杞憂で終わらない感じです。
まあ、今さら嘆くにも及びませんが、「天文古玩」というブログも、書き手である私も、アサブロも、ASAHIネットも、そしてブログ文化そのものも、みんなみんな齢をとってしまったのです。
★
とりあえず現状の告知と、他のアサブロユーザーのご参考までに。
惑星の子どもたち ― 2025年10月25日 18時01分00秒
「芸術新潮」の占星術特集(昨日の記事参照)を読んで、個人的に有益と感じたのは、「惑星の子どもたち」という概念の例証として、イタリアのエステンセ図書館(モデナ)が所蔵する15世紀の写本、『天球について(De Sphaera)』のミニアチュール画について、かなり字数を費やして解説されていることでした。
「惑星の子どもたち」というのは、7つの惑星(※)ごとに、その影響下に生まれた人々は、それぞれ固有の性格なり職業なりに就く傾向を有するという概念で、それを絵解きしたのが、1470年頃にクリストフォロ・デ・プレディスが描いた、この一連の細密画です。
(※)水・金・火・木・土の5大惑星に太陽と月を加えたもの。黄道十二星座の間を縫うようにして、天球上での位置を変える太陽と月も昔は惑星扱いでした。
★
『天球について』は、以前買った複製本が手元にあります。
(円環中に描かれた擬人化された土星、土星が支配するとされる水瓶座と山羊座、そして土星の下に生まれついた地上の人々の姿)
本書は非常に有名な本なので、過去に何度か出版社を替えて複製が作られていますが、手元にあるのは、1969年にベルガモのボリス・ポリグラフィチェ社から出たものです。
(本を収めるための、革装本を模したクラムシェルボックス)
複製本には詳細な解説本が付属しますが、いかんせんイタリア語なので読むことがかなわず、積ん読状態になっていました。でも、この機会に改めて巻を開いて、しばしルネサンスのイタリア貴族の気分を味わうことができました。
(左が解説本、右が複製本)
(木星)
(太陽)
天文学と占星術が未分化な時代にあって、本書は星々を描いた最も美しい本と呼ばれることもあります。まあ、最美かどうかはともかくとして、ド派手なことは類を見ません。
(太陽/部分)
(金星/同)
男神も女神も素裸で局部だけ光らせているのは、いかにも奇異な感じを受けますが、こういう裸体画自体、中世にあっては稀でしたから、異教的神々を風俗画すれすれの姿で描く本書は、二重三重の意味でルネサンス的なのでしょう。
なお、極彩色のミニアチュールの前後には、こうした↑↓グラフィカルな図もあって、これがまぎれもなく天文学・占星術の本であることを物語っています。
ルネサンスと占星術とネオ・プラトニズム ― 2025年10月24日 18時18分45秒
今月は『週刊現代』のほかにもう一冊雑誌を買いました。
『芸術新潮』の10月号です。
10月号の特集は「鏡リュウジの占星術でめぐる西洋美術」。
こういうのは、たいてい何か大規模な展覧会に合わせて組まれることが多いと思いますが、今回は特にそういうのは無くて、純粋にルネサンス美術鑑賞の背景知識として、当時の占星術ブームや、古代の異教的伝統とキリスト教の関係について知っておこうという趣旨のようです。
記事の方は、占星術研究家の鏡リュウジ氏(1968~)が、ルネサンス思想史と芸術論が専門の伊藤博明氏(1955~)および西洋美術史家の池上英洋氏(1967~)と、それぞれ実作品を眺めながら対談する内容がメインになっています。
このテーマはいつも分かりにくく感じていたので、大いに蒙をひらかれました。中でも「なるほど」と思ったのは、伊藤氏のコラム記事「ルネサンス時代のさまざまな異教秘儀とそのルーツ」に出てくる以下の記述です(太字は引用者)。
「ルネサンスはフランス語の「再生」を意味する言葉であり、この時代に古代ギリシア・ローマの学芸と文化が復興したことを示しています。〔…〕ところが、彼らに帰されている著作〔=『ヘルメス文書』やゾロアスターの『カルデアの託宣』など〕はすべて、後1~3世紀に思想・文化のカオスと言うべき、アレクサンドリア周辺において成立しました。〔…〕ルネサンスの人々は壮大なアナクロニズム(時代錯誤)に陥っていたのです。彼らが再生させたのは、古代ギリシアではなく後期ヘレニズムの思想だったのです。」
★
コラム本文にも登場するワードですが、思想史の話題で、私がいつも躓くのは「ネオ・プラトニズム」というやつです。「新プラトン主義」と聞けば、自ずとあの哲人プラトンを思い浮かべますが、それと「万物の一者からの流出」を説く、すぐれて神秘主義的な思想とのつながりが今ひとつ分らず、これまで何となく敬遠していました。でも、言うなればこれは私自身のアナクロニズムに他ならず、ここは思い切って「プラトンの思想と新プラトン主義はまったく別物だ」と割り切るのが至当ではないでしょうか。
プラトンと新プラトン主義の関係は、おそらく老子と道教の関係に近いのでしょう。そこには確かに連続した要素があると思いますが、白と黒が連続しているからといって、白と黒が同じとは言えないように、やっぱり違いの方が目立ちます。同じことは孔子と朱子学の関係や、ゴータマ・ブッダと密教の関係についても言えそうです。
要するに、ネオ・プラトニズムは、決して「新しいプラトン主義」ではなく、「ネオ・プラトニズム」というひとつの固有の思想だ…と考えるわけです。まあ、素人のいうことですから、あまり真面目に受け止めてもいけませんが、そう考えることで、少なくとも私自身は非常にすっきりした気分です。
荒俣氏の蔵書に思ったこと ― 2025年10月18日 15時09分11秒
ボンヤリしている間に世の中にはいろいろなことが起こり、何だかますますボンヤリしてしまいます。国内も国外も多事多難。そんな中、いいささか小市民的な話題ですが、先日、荒俣宏氏の件でネットの一部がざわつき、私もいろいろ考えさせられました。
★
荒俣氏の件というのは、氏が最近蔵書2万冊を処分されたのですが、半分は引き取り手が見つかったものの、残りの半分は古本屋からも見放され、結局、産廃業者のトラックで運ばれていった…という話題です。
問題の記事は、現在ネットでも公開されていますが【LINK】、せっかくなので紙の雑誌を買ってきました(「週刊現代」を買ったのは、生まれて初めてだと思いますが、今は税込みで600円もするんですね。それと「週刊現代」は週刊ではなく、隔週刊だって知ってましたか?)
いかにも悄然とする話で、記事に接した人々の反応もさまざまでした。
あの荒俣氏でも老いは避けがたいという感慨。
もったいない、何か他に方法はなかったのか?という不審の念。
これは他人事ではないぞという焦慮。
もったいない、何か他に方法はなかったのか?という不審の念。
これは他人事ではないぞという焦慮。
そしてもう一つ、本というのはそんなに売れんものか、本邦の文化水準の凋落まことに恐るべし…という慨嘆を文字にされた方もいました。
いずれももっともな感想です。
最初の老いの問題はまたちょっと違うかもしれませんが、あとの3つは、結局「本は資産なのか?」という疑問に帰着するように思います。
不動産が「負動産」と呼ばれるようになり、都会地はともかく、地方の土地や建物は邪魔っけなもの、できれば相続したくないものになって久しいです。書物も今や「負の動産」の代表であり、かつては威信財でもあった大部で高価な書物も、遺族には迷惑千万なゴミの山と化している…というのが、時代の趨勢なのでしょう。
嘆けども、事実は事実として受け入れるほかありません。
★
ただ、ここで一つ注意を喚起したいことがあります。
少し考えればわかるように、ここで最大の障壁は、遺族にとってそれが迷惑千万な存在だという点で、仮に遺族がそれを喜んで受け継いでくれるならば、ゴミの山はとたんに宝の山と化し、何の問題も生じないことです。
コレクター気質の人は、得てして家族の犠牲の上にコレクションを築くので、遺族にとっては迷惑なばかりでなく、自分を虐げた「仇」のように感じるのではないでしょうか。こうなると憎悪の対象にすらなってしまうわけです。そして持ち主自身も、内心そういう負い目があるので、いきおい「何とか自分が元気なうちに片づけないと…」と思いつめるのでしょう。
我が家の場合も、たしかにその気配があります。でも家人と共通の趣味の本に関しては、そんなに邪魔っけにされません。したがって、一家和合こそが問題解決のカギであり、身近な人々を趣味を同じうする同志たらしめること、そのための努力と工夫と真心を欠いてはならない…と、改めて思った次第です。
(以上のことは、単身の方にはそのまま当てはまりませんが、でも同様の視点はあってもよいのではないでしょうか。すなわち、ぜひ身近な理解者を…ということです。)
季節のたより ― 2025年10月12日 19時28分11秒
一番風邪、二番風邪、三番風邪…と、毎年だいたい3回ぐらい風邪をひきますが、最近の寒暖差で、どうやら一番風邪をひいたようです。身近な人の葬儀が続いて、ちょっと気弱になったことも影響しているかもしれません。
そんなわけで、記事の方はしばらくお休みです。
皆さまもどうぞご自愛ください。
雑誌『シリウス』のこと(2) ― 2025年10月10日 14時31分44秒
ルドルフ・ファルプ(Rudolf falb、1838-1903)が1868年に創始した一般向け天文雑誌、『シリウス(Sirius. Zeitschrift für populäre Astronomie)』。同誌の書誌はWikimrdia Commonsの当該項【LINK】に載っており、それによれば終刊は1926年だそうです。時代の嗜好に合ったのか、とにもかくにも半世紀以上続いたのは立派です。
ただしファルプが編者だったのは 創刊から1878年までの10年間で、以後は、Hermann Joseph Klein(1879~1914)、Hans-Hermann Kritzinger (1915~1926)が、編集を引き継いだとあります。したがって、手元の4冊のうち1902年の号だけは、別人であるヘルマン・クラインの手になるものです。
1902年になると、図版も網点による写真版になったりして、科学雑誌としては進化かもしれませんが、味わいという点では石版刷りによる初期の号に軍配が上がります。(まあ、当時の人は別に「味」を求めて石版を採用していたわけではなく、それがいちばんマスプロダクトな手段だったからだと思いますが。)
(火星かな?と思いましたが、1863年6月1日の皆既月食の図でした)
この何ともいえない色合い。
地球の影に入った「赤い月」は、恰好の天体ショーであり、雑誌の見せ場でもありました、
(1877年2月27日の月食3態。月の動きに連れて刻々と変わるその表情)
★
1870年代は、イギリスの場合だと、トーマス・ウィリアム・ウェッブ(1807—1885)による天体観測ガイドの古典『普通の望遠鏡向けの天体』(1859)が出た後で、天文趣味が面的広がりを見せつつあった時期です。アマチュア向けの天体望遠鏡市場も徐々に形を整えつつありました。たぶんドイツでも事情は同じでしょう。
『シリウス』にも、いわゆる「趣味の天体観測」的な記事が登場します。
(さそり座の二重星たち)
(時代を隔てたほぼ同じ月齢の月。左:1865年、ラザフォードが撮影した月、右:1644年、ヘヴェリウスによるスケッチ)
(巨大クレーター「プラトン」を囲む環状山脈の偉観)
(1876年の木星表面の変化。モスクワ大学のブレディキンのスケッチに基づく図)
もちろん小口径望遠鏡では、月にしろ、木星にしろ、かほどにスペクタキュラーな光景が見られたわけではないでしょうが、それでもイマジネーション豊かなアマチュアたちの目には、それがありありと見えたはずです。
そして仮に望遠鏡を持たなくても、美しい星空は常に頭上にあり、星への憧れを誘っていたのです。
(北極星を中心とした北天星図)
(同上部分。よく見ると、星がところどころ金で刷られた美しい仕上がり)
★
「雑誌『シリウス』のこと」と銘打って、(1)(2)と書き継いできましたが、とりあえず19世紀の星ごころの断片は伝わったと思うので、ちょっと尻切れトンボですが、連載は(2)で終わりです。
(この項おわり)
雑誌『シリウス』のこと(1) ― 2025年10月07日 21時50分22秒
今回の調べごとの副産物として、実はファルプは知らぬ間に私の部屋にも入り込んでいたことを知りました。
★
前回参照したwikipediaの記述には、ファルプは1868年、大衆向け天文雑誌『シリウス』を創刊した人であることが書かれていて、「なるほど、そうだったのか」と膝を打ちました。『シリウス』は、その種の天文雑誌としては最初期のものですから、ファルプは天文趣味史においても、重要な位置を占めていることになります。
『シリウス』は、以前サンプルとして入手したものが、4冊だけ手元にあります。
同誌は年によって月刊だったり、月2回刊だったりしますが、それを1年分まとめて、ハードカバーで製本したものです。手元にあるのは1871、1877、1878、1902の各年分で、元の所蔵先がバラバラなので、装丁も不統一です。
(タイトルページに見えるファルプの名)
昔も今もビジュアルに訴えかけることが、大衆向け雑誌の肝でしょう。各巻はいずれも美しいカラー図版を含み、眺めるだけでも楽しいです(というか、ドイツ語なので眺めるしかできませんが)。
(1902年の巻には、雑誌の元表紙も綴じ込まれていました。雑誌の常として、表紙デザインは時代とともに変わったでしょうが、少なくとも1902年当時は、こういう衣装をまとって、読者の手元に届いたはずです)
前回はファルプを一代の奇人と呼んだので、あるいは『シリウス』も、奇説オンパレードの、“19世紀の『ムー』”みたいなものを想像されるかもしれませんが、決してそんなことはありません。これまた中身を読んでないので断言はできませんけれど、内容は至極まっとうなものと見受けられます。
その中身を少し覗いてみます。
(この項つづく)
















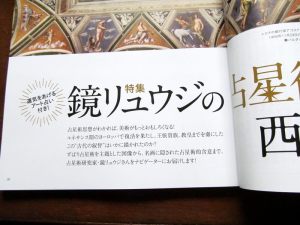













最近のコメント