雲をつかむような話(2) ― 2010年03月14日 16時24分29秒
冊子の冒頭、まず「雲級図の沿革」というのがあります。
時系列に沿って述べると、
1)雲の科学的分類というのは、1803年、英国のLuke Howard という学者が、巻雲、積雲、層雲の3区分を考案し、さらにそれらの中間形態である巻積雲、積層雲、乱雲を入れて、都合6種の雲級を定めたのが始まりだそうです。
2)その後、このハワードの区分を基本として、各国で独自の分類や名称を用いて観測を行っていた時代が長く続きます。
3)しかし、気象観測というのは国際協力がなければ成果が上がらないので、雲の分類を統一しなければ不便だということで、1891年にミュンヘンで行われた国際気象委員会で<国際雲級図>を制定しようという提案がなされました。そのための委員として、スウェーデンのヒルデブランドソン、フランスのティスラン・ド・ボール、スイスのリーゲンバッハといった人々が推挙され、協議を重ねた末に、1895年にチューリッヒで『国際雲級図』がめでたく刊行されました。
4)しかし、これは発行部数も少なく、すぐ絶版になってしまったので、1910年、こんどはパリで『国際雲級図第2版』が出版されることになりました。これは上記のヒルデブランドソン、ティスラン・ド・ボールの2氏共編という形をとっています。
5)しかし、これまたすぐに絶版となってしまい、入手困難となったため、1921年にロンドンで開かれた国際気象委員会において、再び専門の調査委員を設け、雲級を根本的に研究することが決まった…というのが、この『雲級図』が出た1922年(大正11年)までのあらましです。
なんだか雲級図というのは、雲散霧消しやすいようで、出ては消えということを繰り返しているのが興味深いです。
ところで、日本における雲級の取り扱いですが、日本では『国際雲級図』が出た後も、1890年にヒルデブランドソンが個人名で出した『菲氏雲級図』というのを使い続けて、『国際雲級図』の第2版が出た後で、ようやくこれを採用したようです。
しかし、1922年の段階でも、雲の名称にはちょっとした混乱がありました。
『雲級図』の解説には、
「本邦気象界に於て現に使用する雲級の名称は其拠るところ
明らかならず〔…〕而して国際気象委員会にて決議し、欧米
各国の気象界にて採用せるものとは異なるもの二、三あり、
又之を略記する記号の如きも大部分異なれり」
とあります。例えば、「層巻雲」は国際標準だと Alto-stratus と呼称し、略号 A-St を用いたのに、日本では Strato-Cirrus、略号 SC を用いたりしたのが、その例です。おそらく、近代気象学を導入する過程であれこれあって、それが歴史的残滓として用語にも影響したのでしょう。
さて、以下に海洋気象台スタッフの力作である雲の図を見ていきます。
彼らの<美>へのこだわりは、そこにも遺憾なく発揮されているのですが、それはまた次回。
(この項つづく)
【付記】
ルーク・ハワードはその筋では有名な人のようで、英語版Wikipediaでも扱いが大きいです(http://en.wikipedia.org/wiki/Luke_Howard)。なおこの記事によれば、ハワードよりも先に、進化論者のラマルクが雲の分類名を提唱したそうですが、ハワードのようなラテン名ではなく、フランス語名を用いたために、一般に普及しなかったとのこと。
(おまけ。裏表紙には海洋気象台のマークが拡大して載っていました。太陽だったんですね。しかもリアルな。単なる「お天気」のシンボルかもしれませんが、ひょっとしたら太陽観測へのこだわりの表れかも。このマークは、現在の神戸海洋気象台のHPには出てこないようです。)
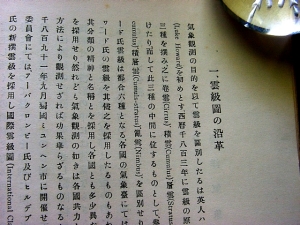

コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。