さわやかな星座早見盤 ― 2017年03月01日 06時21分30秒
駄菓子的な天文アイテムといえば、この星座早見盤は、さしずめ薄荷味のお菓子。
(右側は早見盤が入っていた外袋)
シュトゥットガルトの老舗教育出版社、フランク出版(Franckh’sche Verlagshandlung、現・フランク・コスモス出版)が売り出した星座早見盤。
時代はさして古いものではありません。付属の説明書によれば、初版は1965年、手元のものは1974年に出た第8版です。
地平線を示す楕円の周囲に、地上の景色を描きこむのは、他にも例がありますが、窓自体が凹凸の不整形になっているのは、ちょっと面白い工夫です。
それに何といっても、この色合い。上品なペールブルーと純白のコントラストが、とても爽やかな印象を生んでいます。
洒落たコートを羽織った男が、じっと見入るのもむべなるかな。
裏面はこんな様子。
星座早見というのは、星を描いた「星図盤」と、その時見える空の範囲を示す「地平盤」の組み合わせから出来ており、北極星を中心に盤をクルクル回すことで、星空をシミュレートするわけですが、この製品は、地平盤から南北に伸びた「突起」の隙間を星図盤が回るようになっており、星座早見としてはわりと珍しい構造です。
(ヘルムート・シュミットさんというのは、たぶん元の持ち主)
さらに、星図盤をよく見ると、通常の「日付目盛り」の外側に「赤経目盛り」があり、最外周に「黄道十二宮」が表示されているのも、細かい工夫です。
黄道十二宮については、占星術に関心のある人以外、あまり使いでがないかもしれませんが、現在の黄道十二星座とのずれ具合から、地球の歳差運動に関心を持ったり、天文学の長い歴史に思いをはせる役には立つでしょう。
洒落たデザインばかりでなく、教育的配慮も行き届いた、これはなかなかの佳品です。
★
…というようなことを書いて、事足れりとしてはいけないのでした。
実は、この爽やかな星座早見盤は、単に爽やかなだけの品ではありません。
先日、部屋の灯りを消して、ふと机の上を振り返ったら、この星座早見が微かにボーっと光っていて、一瞬ぎょっとしました。
(私のカメラは暗所では無力なので、画像をいじってコントラストをMAXにしました)
「え?!」と思って、読めないドイツ語を辞書で引いたら、この早見盤のタイトル、「Nachtleuchtende Sternkarte für Jedermann」というのは、「一般用夜光星図」の意味なのでした。
他にも夜光塗料を使った星座早見盤の例はあるでしょうが、それと意識せずに見せられると、やっぱりちょっとびっくりします。そして、「うむ、よくできている」と、ここで再び膝を打ったことは、言うまでもありません。確かにこれは佳品と呼ぶに足る品です。
(さらなる暗闇の中、鬼火のように燃える星たち)
神戸の夢 ― 2017年03月03日 18時35分05秒
ところで、先週と先々週の「ブラタモリ」は神戸でした(明日は奄美大島)。
時間の制約から、やや食い足りないところも見受けられましたが、それでも神戸の街のあれこれを思い浮かべて、しばし画面に見入りました。
★
このブログで神戸といえば、何と言っても稲垣足穂が過ごした町。
そして、長野まゆみさんの『天体議会』の舞台となったのも、きっと神戸だろう…ということを、以前長々と書きました。
神戸に関する本は、ずいぶんたくさん出ていることでしょう。
私はそれらを広く読んだわけではありませんが(というか殆ど読んでいませんが)、ただ、通り一遍の観光案内なんぞでなく、神戸の「深層」を語る本として、私が一読深い感銘を受けたのは、西秋生氏の『ハイカラ神戸幻視行』です。
西氏は生粋の神戸人であり、紙資料を博捜するばかりでなく、ご自分の足で神戸中を歩き回り、町の現況を確認し、多くのオリジナルな観察や発見をされています。
この本のことは、すでに4年前にも取り上げました。
■夢の神戸…カテゴリー縦覧:新本編
そのときは、初編にあたる『ハイカラ神戸幻視行―コスモポリタンと美少女の都へ』について言及したのですが、昨年、その続編である『ハイカラ神戸幻視行―紀行篇 夢の名残り』が刊行されました。
(左・初編(2009)、右・続編(2016)。いずれも神戸新聞総合出版センター)
この2冊は、ともに神戸を縦横に掘り下げた本ですが、その構成がいくぶん違います。
すなわち、初編は「人物」を軸としているのに対し、続編は「土地」を軸としています。この2冊を合わせて読めば、神戸の街に漂う「記憶」や「匂い」が、鮮やかに甦る仕掛けです。
試みに、それぞれの章題のみ、目次から抜粋してみます。
■『ハイカラ神戸幻視行―コスモポリタンと美少女の都へ』
序章 神戸、その都市魅力
第1章 宇宙論的挑発(イナガキ・タルホ)
第2章 美女と美食と藝術と(谷崎潤一郎)
第3章 詩人さん(竹中郁)
第4章 妖しい漆黒の光芒(探偵作家たち)
第5章 カンバスとレンズの向う(小松益喜と中山岩太)
第6章 港都の誘惑(やって来た人たち)
第7章 失楽の軌跡(去って行った人たち)
終章 <ハイカラ神戸>へのコンセプトワーク
序章 神戸、その都市魅力
第1章 宇宙論的挑発(イナガキ・タルホ)
第2章 美女と美食と藝術と(谷崎潤一郎)
第3章 詩人さん(竹中郁)
第4章 妖しい漆黒の光芒(探偵作家たち)
第5章 カンバスとレンズの向う(小松益喜と中山岩太)
第6章 港都の誘惑(やって来た人たち)
第7章 失楽の軌跡(去って行った人たち)
終章 <ハイカラ神戸>へのコンセプトワーク
■『ハイカラ神戸幻視行―紀行篇 夢の名残り』
序章 夢の街へ、街の夢を訪ねて
第1章 世界一美しい“異国” 元居留地
第2章 異人館の街 山手雑居地(北野町・山本通)
第3章 ボヘミアンの闊歩 トアロード
第4章 繁華街の古層 三宮界隈
第5章 鈴蘭燈の輝く下で 元町界隈
第6章 船長文化の開花 中山手界隈
第7章 夢のミクロコスモス 阪神間
第8章 山の麓 六甲・王子公園
第9章 静謐な歴史の街 兵庫
第10章 明るい海と山と石と 須磨・明石
終章 時の彼方から
この章題からも、神戸の魅力が尽くされていることが――西氏は「いや、決して尽くされていない」と仰るかもしれませんが――お分かりいただけるのではないでしょうか。
★
この美しい2冊の本の「衣装」を手がけたのが、画家の戸田勝久氏で、氏もまた生粋の神戸人と伺いました。その思いは、初編の北野町小路の夜景に、そして続編の昔日のトアロードの光景へと結実し、この2冊を並べることで、神戸の昼と夜が一望できる趣向となっています。
(カバー絵は表と裏で連続し、1枚の絵となっています。戸田勝久画 『神戸幻景 トアロード1928』)
そして見返しには、
彗星と並んで疾走するボギー車。
スパークする火花。
「地上とは思い出ならずや 稲垣足穂」の文字。
★
嗚呼、地上とは思い出ならずや…
著者の西氏は、2015年、本書が上梓されるのを見ずに病没されました。
この『ハイカラ神戸幻視行―紀行篇 夢の名残り』は、西氏の遺著であり、思い出であり、夢の名残りであるのです。そこに深い寂寥を感じつつ、本書の内容についても見てみます。
(この項つづく)
神戸の夢(2) ― 2017年03月04日 14時20分13秒
(昨日のつづき)
西 秋生(本名・妹尾俊之、1956-2015)著、『ハイカラ神戸幻視行―紀行篇 夢の名残』(2016)は、大正~昭和戦前に、まばゆい光を放った神戸ハイカラモダニズムを、現在の神戸に重ねて幻視する内容の本です。元となったのは、2009~10年に神戸新聞紙上に連載されたコラム、「ハイカラ神戸幻視行―紀行篇」。
当時の神戸は、他の時代や、他の土地では決して見られない、文字通りユニークな文化的オーラをまとった街だった…というのが、西氏の言わんとするところだと思います。そして、それは土地っ子の身びいきではなく――もちろん身びいきの要素もあるでしょうが、それを差し引いてもなお――真実その通りであると、この本を読むと頷かれます。
多くの異人さんが住み、舶来品が毎日荷揚げされた町は、旧来の日本人にとって、まさに異国の町。他方、船に乗ってやって来た当の異人さんにしても、神戸はもちろん異国の町です。神戸は誰にとっても異邦であり、誰もがエトランジェであり、だからこそ自由であり、夢があったのでしょう。そういう無国籍な街は、往々「魔都」になりがちですが、神戸の場合、その明るい風光のゆえか、始終伸びやかな空気が支配的だったのは、まことに幸いでした。
★
明治の香りが匂い立つ旧居留地、北野町の異人館、トアロードの賑わい、緑したたる六甲、阪神間のそこここに展開したお屋敷町、往来する市民を明るく照らした元町通りの鈴蘭灯…。
西氏の文章は、どちらかといえば抑制の利いた、客観描写を主とするものですが、その筆致は、かつてそこにあった建物、かつてそこを行き来した人々を活写して、読者を昔の神戸へと誘いこみます。そして西氏自身、ときに「向うの世界」へと迷い込みそうになる自分を抑えかねる風情が見られます。
たとえば、神戸の中でもとりわけ古い地区――かつて福原の都が置かれ、濃い緑の中に寺社が点在し、幕末に勝海舟が寓居した奥平野地区を歩きながら、氏はつぶやきます。
「私の幻視行は2010年の今日を出発点として、約八十年前、神戸に無類のハイカラ文化が開花した時代を訪ねるものであるが、奥平野を歩いていると、自分がまさに大正半ばから昭和初期のその頃にいて、そこから明治や幕末の昔を偲んでいる、そんな錯覚に見舞われることがある。
だから、あるいは深夜、漆黒の闇が街をすっかり塗り潰してしまうまで当地に留まっていて、それから暗闇伝いに山麓線をたどって行くと、赤いおとぎ話のような錐塔に彩られたトアホテルに行き着くことができるかも知れない。」 (上掲書 p.237)
〔※改行は引用者。引用に際し、年代の漢数字をアラビア数字に変換。以下同じ〕
こうした<跳躍の予感>こそ、西氏が持つ幻視者としての資質を示すものでしょう。
★
さらに、本書の中にちょっと妙な記述が出てきます。
それは、明治の末に、西本願寺門主の大谷光瑞が、西洋趣味とオリエント趣味を混ぜ込んで建てた、奇怪な建築「二楽荘」について触れた箇所です。
(二楽荘本館。ウィキペディアより)
「私は子どものころ、それと知らずに二楽荘を訪れたことがある。記憶にはこの異形の建造物に向き合った鮮烈な時間のみが刻み込まれていて、前後はまったく定かでない。
真夏であった。いまから振り返ると天王山の急勾配を登り詰めた果てのことだったのだろう、唐突に広がった視界の真ん中に、思いがけず二階建てのがっしりした洋館が聳え立っていて、私は息を飲んだ。異様な外観であった。濃くくすんだ灰色の壁には細長い窓があり、部屋や庇が複雑な形に張り出している。屋根は赤い。右端はドームになっており、尖塔は玉ねぎを半分に切った形に見える。その先には何もなく、ずっと遠くに見える市街と大阪湾のほうからしきりと風が吹き寄せてくる。それで初めて、全身汗みずくになっていたことに気づいた。昼下がり、蝉の声も途切れて、静寂の中に叢のざわめく音が僅かに漂ってくる。…
時に甦ってくるたび、何か不思議なおもいに包まれる記憶であった。小学校の低学年か、もっと前かも知れない。二楽荘は阪急岡本の北、山の中腹にあり、そこは幼時の私の生活圏のぎりぎり外縁に当たる。夏休みのささやかな冒険だったのだろう〔…〕」 (同 p.179-80)
真夏であった。いまから振り返ると天王山の急勾配を登り詰めた果てのことだったのだろう、唐突に広がった視界の真ん中に、思いがけず二階建てのがっしりした洋館が聳え立っていて、私は息を飲んだ。異様な外観であった。濃くくすんだ灰色の壁には細長い窓があり、部屋や庇が複雑な形に張り出している。屋根は赤い。右端はドームになっており、尖塔は玉ねぎを半分に切った形に見える。その先には何もなく、ずっと遠くに見える市街と大阪湾のほうからしきりと風が吹き寄せてくる。それで初めて、全身汗みずくになっていたことに気づいた。昼下がり、蝉の声も途切れて、静寂の中に叢のざわめく音が僅かに漂ってくる。…
時に甦ってくるたび、何か不思議なおもいに包まれる記憶であった。小学校の低学年か、もっと前かも知れない。二楽荘は阪急岡本の北、山の中腹にあり、そこは幼時の私の生活圏のぎりぎり外縁に当たる。夏休みのささやかな冒険だったのだろう〔…〕」 (同 p.179-80)
汗をかきかき丘を登り、古いお屋敷の中へ…。
いかにも昭和の少年らしい冒険譚です。しかし、問題はこの次です。
「〔…〕と納得していたが、長じて二楽荘の詳細を知った私は愕然とした。建物の写真は記憶そのままで懐かしかったけれども、しかし、それは昭和7年(1932)、放火と疑われもした不審火によって全焼してしまっていたのである。〔…〕建築家の伊東忠太が≪本邦無二の珍建築≫と評したこの内部へ、たとえ幻であったにしろ、あの時どうして踏み入れなかったのか、悔やまれてならない。」 (同 p.180)
この前後に、納得のいく説明は一切ありません。ただ、幼時の思い出として、こういうことがあった…と述べられているだけです。
一読ヒヤッとする話ですが、西氏亡き今、真相はすべて闇の中ですし、西氏ご自身にしたところで、真相不明であることは読者と同じでしょう。これを記憶の錯誤や、記憶の再構成で説明するのは簡単ですが、こういうことは軽々に分かった気にならず、心の中でしばし味わうことが大切だと思います。
★
私が西氏の文章に強く共感するのは、次のような文章を目にしたことも一因です。
足穂の「星を売る店」の舞台となった、中山手通付近の景観を叙す中で、氏はこう述べています。
「中山手通の南、市電が走っていたこの箇所は、兵庫県公館として活用されている元の兵庫県庁舎と神戸栄光教会のあるあたりである。往時はこれらの北側、いま「県民オアシス」という公園になっている地に、ドームを乗せた石造りの「兵庫県会議事堂」と煉瓦造りの「兵庫県試験場」が隣り合って建っていた(ともに昭和46年解体)。
その竣工年を調べて、面白いことを発見した。
兵庫県庁舎は明治35年(1902)で古いが、栄光教会、兵庫県会議事堂、兵庫県試験場はいずれも同年で、大正11年(1922)なのである。そして、「星を売る店」 の発表は、翌大正12年ではないか。
すなわち、この作品の≪ちよっと口では云はれないファンタジー≫、≪ちよっと表現派の舞台を歩いてゐるやうな感じ≫は、実に出現したばかりの最先端の都市景観が醸し出すものであったのだ。まことに、ウルトラモダニスト・タルホの面目躍如と言わねばならない。」 (同 p.158)
その竣工年を調べて、面白いことを発見した。
兵庫県庁舎は明治35年(1902)で古いが、栄光教会、兵庫県会議事堂、兵庫県試験場はいずれも同年で、大正11年(1922)なのである。そして、「星を売る店」 の発表は、翌大正12年ではないか。
すなわち、この作品の≪ちよっと口では云はれないファンタジー≫、≪ちよっと表現派の舞台を歩いてゐるやうな感じ≫は、実に出現したばかりの最先端の都市景観が醸し出すものであったのだ。まことに、ウルトラモダニスト・タルホの面目躍如と言わねばならない。」 (同 p.158)
この文章を読んで、私はかつて自分が書いた記事を思い出しました。
何となれば、私もこれらの建物の建築年代と、それが「星を売る店」の成立に及ぼした影響に思いをはせていたからです。
(画像再掲。元記事は以下)
■「星を売る店」の神戸(10)…星店へのナビゲーション(後編の下)
西氏の文章は、拙文より数年前に発表されたものです。
私はそれを全く知らずにいましたが、同じ景観を前に、類似した結論に至ったという、その思路の共通性に、今回一方的に近しいものを感じて、大いに嬉しく思いました。
上の記事を書いた時は、西氏とお目にかかる機会も、かすかに残されていました。
その糸も断たれた今、私自身、夢の名残を反芻するばかりですが、しかし、そのこと自体が西氏の追体験でもある…と思えば、単に寂しいばかりではありません。
(この項つづく)
神戸の夢(3) ― 2017年03月05日 14時38分06秒
西秋生氏が筆にした夢幻的な神戸。
その世界に入り込むための「鍵」をしきりに探したのですが、ここは足穂つながりで、彼の朋友であり、神戸モダニズムを代表する詩人、竹中郁(1904-1982)に注目してみます。
恥を忍んで告白すると、私は西氏の本を読むまで、竹中郁という人物をまるで知らずにいました。他にもそういう人はいらしゃるかもしれないので、最初に『ハイカラ神戸幻視行―紀行篇 夢の名残』の巻末に記された、その略伝を挙げておきます。
竹中郁
詩人。明治37年(1904)、兵庫永沢町生れ、昭和57年(1982)歿。
イナガキ・タルホと並ぶ「神戸モダニズム」のシンボル。特に昭和7年の詩集『象牙海岸』はモダニズム詩の最高峰と高く評価される。生まれ育った神戸を離れなかったため、東京中心の詩壇の評価は高くなかったが、生誕百年を機に、二十世紀を代表する詩人としての再評価が進んでいる。随筆集『私のびっくり箱』(のじぎく文庫、1985年)には主に戦前の美しい神戸の思い出が満載されている。
全詩集に『竹中郁全詩集』(沖積舎、2004年)がある。
詩人。明治37年(1904)、兵庫永沢町生れ、昭和57年(1982)歿。
イナガキ・タルホと並ぶ「神戸モダニズム」のシンボル。特に昭和7年の詩集『象牙海岸』はモダニズム詩の最高峰と高く評価される。生まれ育った神戸を離れなかったため、東京中心の詩壇の評価は高くなかったが、生誕百年を機に、二十世紀を代表する詩人としての再評価が進んでいる。随筆集『私のびっくり箱』(のじぎく文庫、1985年)には主に戦前の美しい神戸の思い出が満載されている。
全詩集に『竹中郁全詩集』(沖積舎、2004年)がある。
略伝で挙げられた『象牙海岸』(1932)の現物がこれです。
上品なモロッコ革を用いた四分三装幀(総革ではなく、背と角のみを革装としたもの)。
さすがの神戸も、出版に関しては東京に一目置かざるを得なかったのか、刊行は瀟洒な美本出版で知られた、第一書房(東京市麹町区)に任せています。
とびきりのモダニズム詩を向うに控え、静かに佇む扉の表情。
言葉もなく…
私は白い帽子をかむつて海の中へ入つてゆく。
私に親しいのはこの冷たさと緊密さとだけだ。
私は海の底を匍つてゆく。
私を発見(みつ)けるのは月だけだ。
私が私のものになるのは、この月が廻転し遂(おほ)せてからだ。
私は待つ。小石のやうに。
私に親しいのはこの冷たさと緊密さとだけだ。
私は海の底を匍つてゆく。
私を発見(みつ)けるのは月だけだ。
私が私のものになるのは、この月が廻転し遂(おほ)せてからだ。
私は待つ。小石のやうに。
白い帽子、海、冷たさ、緊密さ、月、小石、私になるのを待つ私。
少しく難解です。しかし、わかるような気もします。でもやっぱり、言葉ではうまく言えません。その言葉にならない思いを言葉にするのが詩なのでしょう。
和紙に捺された、美しい活版の文字。
詩集『象牙海岸』には、並製本のほか、50部限定で和紙に刷られた特製版があり、これがそれに当たります。
★
この詩集の表情が、戦前の神戸の空気を伝えていることは間違いありません。
しかし、手元の1冊には、それ以上に直接的な「鍵」が含まれています。
それは見返しに書かれた署名です。
この一冊は、竹中郁本人が知友に贈ったもので、贈られた相手は竹中が創設した「海港詩人倶楽部」の同人として、詩作も行なった、チェロ奏者の一柳信二(いちやなぎしんじ、1902-?)。
竹中と一柳の親交については、高橋輝次氏による、以下の古書エッセイでも触れられています。
■『高橋輝次の古書往来』
「27.竹中郁と神戸・海港詩人倶楽部」
「27.竹中郁と神戸・海港詩人倶楽部」
外国船がしきりに行き交う港町。
そこに才気渙発な芸術家が集い、詩作し、音楽を奏で、絵を描いた時代。
戦争の闇が訪れるまで、神戸に確かに存在した伸びやかな空気が、この詩集を開けば、さっとあふれ出てくるのです。
★
戦争は、竹中の暮らしをすっかり変えてしまい、戦後は人並みの苦労もしました。
しかし、竹中の美意識は単なるポーズではなく、その骨格を形作る信条でしたから、敗戦の前年、昭和19年(1944)の初夏においても、その凛としたたたずまいは、全くぶれることがありませんでした。
「竹中は一見して舶来とわかる水色の背広をきちんと着こなし、薄茶色のソフト帽子を少し横にかぶっていた。ワイシャツも洗い立てらしく真白だ。ネクタイの色は忘れたが、身のこなしに寸分のゆるみもない。電車のなかは国民服かモンペ姿かである。それだけに竹中は目立ったが、少しも気にしているようすはない。それがとても立派なことのように見えた。」 (足立巻一、『評伝竹中郁』/西秋生『ハイカラ神戸幻視行―コスモポリタンと美少女の都へ』から再引用)
うーむ、カッコいい。
しかし、当時の世相を考えると、このカッコよさは相当の覚悟がなければできません。
★
竹中が手に取り、自ら文字を書き付け、友人の音楽家に贈った自著を、85年経った今、わたしがこうして手に取っている…。思えば、夢のようですが、これは夢ではなく、たしかな現実です。それは85年前の神戸が、決して夢ではなく、現実に存在したことをも、はっきりと思い出させてくれます。
宇宙鉛筆 ― 2017年03月07日 07時09分12秒
博物趣味っぽいモチーフを含む、ヴィンテージな絵柄のステーショナリーで知られる、サンフランシスコのカヴァリーニ社。
■Cavallini & Co.
レターセットとか、付箋とか、紙物が目立つラインナップの中、同社のペンシルセットに目が留まりました。
銀の缶ペンケースに入った「Celestial Pencil Set」。
こういう過去の絵柄をそのままパクっただけの商品は、何となく芸がないと感じますが、普段使いする分には、ちょっといいかなと思いました。
絵柄は2種類、各5本の10本セット。
天球図と日食説明図の2種の天体モチーフが、一本一本に刷り込まれています。
お尻に消しゴムが付いているのもいいし、付属のシャープナーが木製なのも、好感が持てます。
カヴァリーニ社の製品は、日本でも流通しているので、すでに国内でも売られているかもしれませんが、これはeBayで見かけて、そのまま注文しました。
送料のいちばん安いイギリスの業者から送ってもらったのですが、製品自体は台湾で作られているので、エネルギー効率を考えると、ちょっと無駄が多かったです。ここは「地球をぐるっと一周して届いた宇宙鉛筆」という、その微妙な有難さに免じて、地球環境に許しを乞いたいと思います。
壺の中にも天地あり ― 2017年03月08日 07時20分18秒
つくづく思うのですが、このブログの画像は、毎度毎度背景が同じですね。
たぶん見る人もそう感じるでしょうし、私自身苦にしているのですが、これはもうどうしようもないです。
自然光が入って自由になる空間は、とにかくこれだけしかないので、いつもこの赤茶けた机の上、わずか30cm四方のスペースにモノをのっけて、縦にしたり、横にしたり、苦労して写真を撮っているのです。まさに「方寸の地」。
しかし、「goo辞書」によれば、この「方寸」という言葉には、
胸の中。心。「万事―の中にある」
《「蜀志」諸葛亮伝から。昔、心臓の大きさは1寸四方と考えられていたことによる》
《「蜀志」諸葛亮伝から。昔、心臓の大きさは1寸四方と考えられていたことによる》
という意味もあるのだそうです。
となれば、まさに人の心は自由自在な一大天地ですから、この極端な制約の中でも、思いだけは気宇広大、精神を縦横無尽に羽ばたかせて、大地と海と空へ、さらに遠い宇宙へと向かうことにします。
まあ、四字熟語を使って無理に力む必要もないですが、これからも背景は変らねど、懲りずにお付き合いいただければと存じます。
日本のグランドアマチュア天文家(1) ― 2017年03月11日 08時17分30秒
さて、どこまで話を遡らせればよいか…。
これまで何度か言及した、アラン・チャップマン著『ビクトリア時代のアマチュア天文家』(産業図書)には、19世紀のイギリスを生きた、多様なアマチュア天文家が登場します。
彼らは、星に興味がある…という唯一の共通点を除けば、その社会的・経済的地位は実にさまざまで、まさに赤貧洗うがごときだった人もいれば、あきれるほどの富に恵まれ、巨大な機材を備えた私設天文台を作り、飽かず星を眺めた人もいます(チャップマン氏は、後者を「グランドアマチュア」と呼びます。即ち「大アマチュア」の意です)。
★
そんな昔の天文マニアの生きざまに関心を持ち、キョロキョロしているうちに、かつての日本にも堂々たる貧窮スターゲイザーがいたことを知って、大いに勇気づけられました。それが、戦前に独学で詳密星図を作った草場修(1900-?)という人物です。
草場氏が活躍したのは昭和ヒトケタ、すなわち1930年前後のことで、英国ビクトリア時代の同輩と並べて論じるのは、いささか無理がありますが、氏の場合も、孤独な日雇い人夫として、さらには聾というハンデを持ちながらの活躍でしたから、まさに貧窮スターゲイザーの名に恥じぬ――というのは褒め言葉にならないかもしれませんが――あっぱれな御仁であったと言い切って差し支えありません。
★
草場氏のことは、これまで何度も記事にしているのですが、下のページを足掛かりにして、前後をたどっていただければ、およそお分かりいただけると思います。
■貧窮スターゲイザー、草場修(7)…カテゴリー縦覧:天文趣味史編
私はその一連の記事の中で、山本一清の内弟子のような格好で、京大のスタッフにまでなった草場氏に対して、いく分揶揄するような記事を、雑誌「天界」に投稿した「萑部進・萑部守子」という人物について言及しました。そのときは、「これは草場氏を排撃するための匿名記事であり、萑部云々は仮名だろう」…というようなことを書きました(当時はそういう記事がわりと多かったです)。
■貧窮スターゲイザー、草場修(10)…カテゴリー縦覧:天文趣味史編
でも、それは私の完全な間違いでした。
この萑部(ささべ、と読みます)というのは、紛れもなく両氏のご本名だということを、上の記事のコメント欄で、青木茂樹氏にご教示いただきました。
★
しかも驚いたことに、この萑部氏夫妻(進氏と守子氏はご夫婦です)は、草場氏とは対照的な、まさに日本における「グランドアマチュア」のような方だったのです。草場氏に注目したことで、期せずして、日本のアマチュア天文家の多様な姿を知ることができたのは、大きな収穫でした。
以下、萑部氏のことについて、今現在分かっていることを心覚えとしてメモ書きしておきます。
(この項つづく)
―――――――――――――――――――――---------
▼閑語 (ブログ内ブログ)
安倍氏に対しては、何となく小物感を感じて、軽侮の念を抑えかねていました。でも、それは安倍氏にとって甚だ不本意なことでしょう。
ここはひとつ「平成の妖怪」と尊称すれば、氏としても、敬愛するお祖父さん(昭和の妖怪、岸信介)に大いに面目を施した形になりますし、さらに「平成の巨悪」として「平成の大疑獄事件」の果てに引退した…となれば、相当な大物感が漂いますから、氏にとって悪い気はしないはずです。平成の終わりが近い今、早く決断しないと、永遠にその機会が失われます。ぜひ英断を望みたいです。
…と、皮肉まじりに書くのは、私の信条に反しますけれど、でも安倍さんにはそんな矜持もないのかなあと、つくづく侘しく思います。
日本のグランドアマチュア天文家(2) ― 2017年03月12日 09時04分08秒
青木氏からお知らせいただいたのは、萑部(ささべ)氏と、その私設天文台の様子を伝える、同時代の雑誌記事の存在でした。
それは、反射望遠鏡の鏡面製作者として有名な、木辺成麿(きべしげまろ、1912-1990)氏がかつて書いた、「六甲星見台の萑部氏の新反射赤道儀」という一文です。
掲載誌は、東亜天文協会(現・東亜天文学会)の機関誌『天界』1935年2月号。
■「六甲星見台の萑部氏の新反射赤道儀」
木辺氏の文章は、少し要領を得ないところもありますが、概略は以下の通りです。
〇1934(昭和9)年7月、木辺氏は萑部氏から依頼を受け、翌8月からそのメイン機材の製作に取り掛かった。
〇萑部氏は、同年(1934)春に、イギリスから47cm 径の巨大な反射鏡〔註:他資料によればリンスコット社製〕を取り寄せていたが、それをすぐ望遠鏡に組み上げることは困難だったので、差し当たり、もう少し小型の眼視用機材を木辺氏に作ってもらいたい…というのが、依頼の趣旨。
〇望遠鏡の主な使途は、火星をはじめとする惑星面の観測、掩蔽観測、微光変光星の追跡。
〇依頼を受けて木辺氏が製作したのは、口径31cm の反射赤道儀式望遠鏡(自動追尾の運転時計付き)。ただし、実際に組み込んだのは31cm 鏡ではなく、暫定的に26.5cm 鏡を使用。
〇これに、15cm 径の屈折望遠鏡(レンズは英国レイ製)を同架。
〇光学部以外の一切は、京都の西村製作所が担当。
〇同年(1934)12月に機材完成。
その完成した機材と観測施設の外観が、上掲誌に載っています。
(キャプションは「新設された六甲星見台(萑部氏宅)の望遠鏡」。この上に更にルーフやドームが乗ったのかどうか、おそらく乗ったと思うのですが、その辺がはっきりしません。)
(同じく「六甲星見台の外観。白亜六角形の建物が観測室」。何だか、ジブリの「耳をすませば」に出てくる地球屋みたいな風情です。)
★
これだけの大仕事を、当時まだ22歳の木辺氏が請け負ったというのも驚きですが、何と言っても目を引くのは、萑部氏というアマチュア天文家の存在です。しかも、その星見の舞台がハイカラ神戸と聞けば、これはもうタルホ世界に向けて一直線で、俄然興味をそそられます。
日本の「グランドアマチュア」と呼ぶにふさわしい萑部氏の事績を、さらに追ってみます。
(この項つづく)
日本のグランドアマチュア天文家(3) ― 2017年03月14日 07時20分31秒
萑部進・守子両氏のお名前は、『改訂版 日本アマチュア天文史』(日本アマチュア天文史編纂会編、恒星社厚生閣、1995)、および『続 日本アマチュア天文史』(続日本アマチュア天文史編纂会編、同、1994)に、複数回登場します(以下、前者を『正編』、後者を『続編』と記すことにします)。
★
まず夫君である進氏の名は、『正編』に9か所、『続編』に1か所出てきます。また、守子氏の名は、『正編』に7か所登場します。これは両氏がアマチュア天文家の中でも、相当熱心な活動家だったことを示す数字です。
その天文家としての活躍ぶりは、前回、木辺氏の文章でも挙げられていたように、惑星面、掩蔽(星食)、微光変光星と多岐にわたっていました。
東亜天文協会(現東亜天文学会)は、観測対象に応じてセクション体制をとっており、昭和9(1934)年には、進氏は「掩蔽課」に、守子氏は「遊星面課」に、それぞれ課員として名を連ね、昭和11(1936)年には、守子氏も掩蔽課員となっています。
(なお、当時の掩蔽はもっぱら月によるものを指し、惑星や小惑星による掩蔽観測は一般的ではありませんでした。)
また、変光星についても、夫婦揃って熱心な観測家で、進氏は438個、守子氏は29個の観測データを、東亜天文協会に報告しており、さらにアメリカのAAVSO(アメリカ変光星観測者協会)にも、進氏は249個、守子氏は14個のデータ報告を行なっています。
変光星の観測報告は、すべて昭和10(1935)年に行われたものですが、萑部氏に限らず、この年は東亜天文協会の内部で、ちょっとした「変光星ブーム」があったらしく、その前後に比べて、報告者も、報告数も、格段に多くなっています。
そのことは、『正編』172ページに所載の「東亜天文協会変光星観測リスト」に明瞭ですが、ここでいっそう注目されるのは、このリストに挙がっている55名の観測者中、女性は萑部守子氏と、京都の成川梅子氏の2名のみであることです。
さらに、『正編』の319ページには、以下の記述も見られます(筆者は重久長生氏)。
「萑部夫妻は10吋反射(赤)、6吋屈折(赤)などを持ち、変光星観測をやっていた〔註:吋はインチ、「赤」は赤道儀式の意〕。とくに夫人の方が熱心だったという。その他に18吋・リンスコット反射鏡(末組立品)を持っており、これは戦後横浜市で開かれた産業貿易博覧会に出品された。」
横浜云々のことは、また後でも触れますが、守子氏の熱心な観測ぶりは、こんなふうに周囲にも広く聞こえていたのでしょう。
★
1930年代の神戸。美しい六甲の山裾に瀟洒な山荘風の屋敷を構え、専用の観測室と大型機材を持ち、夫婦そろって熱心に星を観測した人たち。
口径10インチが放つオーラも、女性が星を観測することの社会的意味合いも、当時と今では全く異なることにご留意いただきたいですが、何だか本当にタルホの小説に出てきそうな、いかにも浮世離れした二人です。
★
そもそも萑部氏とは、どんな経歴の人物なのか?
興味は自ずとそこに向きますが、ネット上にはきわめて情報が乏しいので、図書館に行って、当時の人名録(いわゆる紳士録の類)を見てきました。さすがにこれだけの資産家ですから、その名前は載っていて、萑部氏の仕事向きのことも分かったので、日本アマチュア天文史の一断章として、簡単に触れておきます。
(この項つづく)
日本のグランドアマチュア天文家(4) ― 2017年03月15日 07時20分37秒
戦前の神戸で、「おしどり天文家」として活躍された萑部進・守子夫妻。
そのライフスタイルの背景に注目してみます。
★
萑部進(ささべすすむ)氏は、明治25年(1892)、島根県松江市の生まれ。
大正5年(1916)に東京高商、今の一橋大学を卒業すると同時に、三井物産に入社し、船舶部に勤務されました。その後、大正8年(1919)にはアメリカ、そして大正9年(1920)にはロンドンと、海外勤務を経験された後、「船舶部遠洋掛主任」となり、さらに昭和11年(1936)には「船舶部長代理」の要職に任じられています。
その自宅に「六甲星見台」を建て、星の観測に熱中していたのは、ちょうど船舶部長代理のポストに就く前後のことになります。もちろん、商社の海上輸送部門の責任者が閑職だったはずはないので、相当な激務の中、余暇の時間を大切にしながら、天体観測に励まれたのでしょう。
昔のイギリスの「グランドアマチュア」には、「働かなくても食べていける人」というニュアンスがあったので、萑部氏の場合、そこだけはちょっと違うかもしれません。
★
で、肝心の「六甲星見台」の位置ですが、萑部氏のご自宅は「灘区高羽曽和山」にあった…と資料には出ています。地図を見ると、神戸大学の六甲キャンパスの南麓に、今も高羽町という町名があって、その近くに「曽和山マンション」というのが、グーグルマップだと表示されます。たぶん、その付近に白亜の「六甲星見台」はあったのでしょう。
この間、萑部氏のお名前が人名録に登場するのは、管見の範囲では、昭和3年(1928)発行の交詢社版『日本紳士録』(第32版)が最初で、会社員ながら所得税の高額納税者として、紳士録に名を連ねています。
著名な企業のエリートサラリーマンとはいえ、一介の勤め人が何故?…と、一瞬思いましたが、でも改めて考えたら、この事実こそ当時の「財閥」というものの性格を、はっきり物語るものではないでしょうか。もちろん、三井物産は今も大企業ですが、その社会的意味合いにおいて、戦前の同社は、現在とは少なからず異なっていたように思います。
★
一方、守子氏の方も、夫君と同じ島根県の生まれで、生年は明治31年(1898)。
地元の高等女学校を卒業され、その後、進氏と結婚されたわけですが、長女を出産されたのが大正10年(1921)、守子氏23歳のときですから、おそらく学校を出て、あまり間を置かずに萑部家に嫁がれたのではないでしょうか。そして、進氏と共に海外生活も経験されたのでしょう。
ここで、洋装が板につく、細面で活発な、ジブリ的キャラクターを連想するのは、私の無邪気な空想に過ぎませんが、でも、夫妻を取り巻くムードはとにかくハイカラなのです。
(新緑を楽しむハイカラな二人。戦前の神戸のタクシー会社のマッチラベル)
昭和15年(1940)発行の『大衆人事録 近畿篇』を見ると(上に記した内容は、ほぼ同書に拠っています)、進氏の趣味は「声楽と天文学」であり、宗旨はキリスト教だと記されています。
前回、夫妻が変光星観測のデータを、アメリカのAAVSO(アメリカ変光星観測者協会)に報告していたことに触れましたが、そこにおける守子氏のお名前は、「Sasabe, Beatrice M.」となっていました(進氏はふつうに「Sasabe Susumu」)。夫妻は揃って洗礼を受け、ベアトリーチェ(あるいはベアトリス)が、守子氏の洗礼名なのでしょう。
1935年の当時を思い浮かべると、進氏43歳、守子氏37歳。
一男二女に恵まれたお二人は、六甲の高台から毎日海を眺め、星を眺め、音楽を愛し、そして神を賛嘆したのです。
私自身の生活経験とはあまりにかけ離れているので、この館で日々どんな生活が営まれたのかは、ぼんやり想像するほかありませんが、それでも何となく良い香りのする、いかにも戦前の神戸らしい、上質な生活がそこにはあったのでしょう。
★
しかし、光あれば影あり。
その生活が光に満ちていればいるほど、その後、お二人が戦中・戦後をどう過ごされたのかが気にかかります。一応、図書館で戦後の人名録にも当ったのですが、そこに萑部氏のお名前は確認できませんでした。
戦時中は、船舶の徴用をめぐって軍との際どい折衝もあったでしょうし、戦争が終れば終わったで、例の財閥解体があり、新円への切り替えがあり、世の中がすっかり変わってしまったので、お二人の暮らしぶりも激変したであろうことは、想像に難くありません。でも、この辺のことは今のところ全く不明です。
ただ、あの巨大な望遠鏡がどうなったかについては、若干の伝聞情報があるので、最後にその点を見ておきます。
(この項さらにつづく)






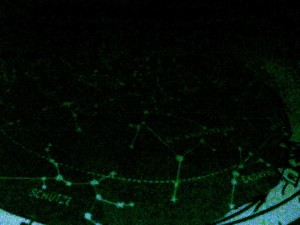























最近のコメント