結晶形態学の薫香 ― 2017年11月18日 08時30分59秒
創作ユニット「ルーチカ」のお一人であるTOKOさんから、「ルーチカ結晶形態学プロジェクト」のご案内をいただきました。
■(公式サイト)ルーチカ結晶形態学プロジェクト
「百年前にX線結晶構造解析の歴史が始まるより以前、結晶学は鉱物の外観から対称性を見出し、分類同定する学問であった。今日では元素組成と粉末X線パターンによる鉱物の同定が一般的となり、古い結晶学は「結晶形態学」として結晶学の導入部に登場するのみとなっている。しかしながら、結晶の点群と格子定数、ミラー指数から定義付けられる多面体『結晶形態図』の意匠の美しさは現在でもなお人々の心を魅了し続けている。」 (上記サイトより)
★
各種鉱物の美しい色・形―。
それももちろん素敵ですけれど、さらにそうした感覚美を超えた、「理」の美しさと呼ぶべきものが、鉱物にはある…と、先日書きつけました。それこそが、まさに「結晶形態の美」だと思います。
それは抽象度の高い美ですが、それを図示したり、立体模型化したりすれば、そこには理知の篩(ふるい)にかけられた、「純粋な感覚美」と呼ぶべきものが、また新たな輝きを放ち出します。
さらに、その解説文を拝読すると、結晶形態学の面差しには、その歴史性に根ざした深い雅味が寄り添っているようにも感じられます。
総じていえば、木製キャビネットや真鍮製の偏光顕微鏡を備えた、古風な鉱物学研究室の空気を、私はそこに感じ取ります。(私信を勝手に引用して恐縮ですが、TOKOさんからのお便りには、「クランツ標本をみて多面体に本格的に目覚めてしまった人のなれの果てみたいな」という一節があって、思わず膝を打ちました。)
★
ここで私自身のことを振り返ると、私には「いつか欲しいなあ」と願い続けてきたものがいくつかあります。指折り数えると、ちょうど7つ。まあ、私にとってのドラゴンボールみたいなものです。そのうちのいくつかは、すでに見つけることができたので、神龍が出現することはないにしろ、完全ゴールも徐々に近づいています。(でも、ゴール間近になると、また新たな目標が生まれそうな気もします。真の完全ゴールは永遠に来ないかもしれません。)
そのうちの1つ、自分の中ではこれぞという逸品を、結晶形態学プロジェクト始動を祝し、勝手協賛企画として登場させます。(尻馬に乗る、とも言います。)
<大いに勿体ぶりつつ、次回につづく>
Crystals of Crystal(前編) ― 2017年11月19日 07時00分27秒
(昨日のつづき)
「結晶形態学プロジェクト」の雅味に沿い、かつ私が以前から憧れていたもの。
それがこの黒い箱に入っています。
(箱の大きさは、約29×20cm)
この箱が届いたのは、去年の夏のことです。
かなり無理な算段をしてこれを購入したのは、わずかなボーナスが入って、ちょっと気が大きくなっていたせいもありますが、でもこれは、たとえ財布がスッカラカンでも買うしかないと、見た瞬間に思いました。
その中身は(大方お察しのとおり)「結晶模型」です。
でも、よく見る木製ではありません。クリスタルガラス製のまさに Crystals of Crystal、「クリスタルでできた結晶たち」なのです。
もちろん、木製の結晶模型にも独特の味わいがありますし、それに木製だろうが、ガラス製だろうが、結晶の形自体に変わりはないんですが、無色透明なガラスで作られた結晶模型には、昨日書いたような、抽象的な「理」の美しさや、「理知の篩(ふるい)にかけられた純粋な感覚美」が、なおのこと溢れているように感じたのです。
結晶形態は全部で20種類。ひとつひとつが小箱に入り、真綿の上に鎮座しています。
私はこうした風情にすこぶる弱く、また「正方晶系完面像晶族」とか「六方晶系菱面体晶族」とかいった言葉の響きに、脳幹反射的に反応してしまうところがあります。
何だか、「理」の美しさと言ったそばから、妙に幼稚な感想を書き付けていますが、結晶美の王道はルーチカのお二人にお任せするとして、私の方はモノにこだわって、この模型の素性をちょっと考えてみます。
(この項つづく)
Crystals of Crystal(後編) ― 2017年11月20日 06時49分40秒
クリスタルガラス製の鉱物結晶模型の全容はこうです。
(販売時の商品写真の流用。奇妙な手は、大きさ比較用のラバーモデル)
この結晶模型セット、メーカー名の記載がどこにもありませんが、売り手であるイギリスの業者の見立てでは、1890年ころのドイツ製。
年代については、1890年前後で特に矛盾はありませんが、下で触れるように、この種のセットは1920年代にも販売されていたので、もう少し時代は幅を持たせた方が安全かもしれません。
また、販売を手がけたのはドイツの会社かもしれませんが、生産国はおそらくチェコでしょう。つまりドイツの業者――おそらくクランツ商会あたり――が、チェコのガラス工房に発注して、商品として販売していたのだと思います。
★
ガラスの結晶模型への憧れを書いたのは、今回が初めてではなく、以前も心情を吐露したことがあります。
上の記事は、ガラス製の結晶模型の実例を紹介するページにリンクを張っており、そこで紹介されているのは、透明ガラスと色ガラスの模型が同居する可憐なセットでした。しかし、一種の親バカかもしれませんが、手元のオール透明ガラスのセットの方が、結晶美という点では、一層純粋で好ましいと思います。(結晶美とは、畢竟、無味・無色・無臭の抽象世界に成立するものでしょう。)
(結晶の面角を正確にカットしたガラス塊の輝き。おそらくボヘミアガラスの職人技)
★
ガラスの結晶模型セットを、往時の博物用品カタログに探したところ、パリの博物ショップ・デロールのカタログに載っているのを見つけたので、参考までに挙げておきます。
1929年のカタログですから、デロールの歴史の中ではわりと時代の下るものです。
当時のデロールは、学校への理科教材の卸販売が中心の店で、こうしたカタログを盛んに出しており、カタログ掲載の品も自社製品とは限らず、むしろ他社製品の取次ぎのほうが多かったように思います。
頁をめくると、そこに「Séries cristallographiques en cristal dur」(硬質クリスタル製結晶学シリーズ)というのが見つかります。説明文には「鉱物の結晶形態とその主要な変異を含む、周到かつ十全な科学的正確さを備えたシリーズ」とあり、360フランの20種セットから、1,650フランの90種セットまで、全部で6種類のラインナップ。
当時のフランの価値はよく分かりませんが、質問サイトの回答(https://oshiete.goo.ne.jp/qa/5617201.html)を参照すると、フラン切り下げ後の1928年の時点で、1フラン=200~250円程度(金の価格を基準にしています)。これに従えば、20種セットで7~9万円、最上位の90種セットは33万~41万となります。
手元のセットが、デロールが扱っていた商品と同一である保証はありませんが、20種セットというのは、まあ一般的にいって「入門シリーズ」なのでしょう。それも今となってはすこぶる希少な品で、その希少さの背景には、素材の性質上、きわめて毀れやすかった…という事情があると思います。
手元の模型も、よく見ると縁が欠けているものが何点かあります。
この品を無事次代に引き継げるよう、せいぜい用心しなければ…と、少なからず責任を感じています。
★
ときに、ドイツのクランツ商会は、鉱物関連の品で扱ってない物はないと言ってよいので、このガラスの結晶模型も、探せばきっとカタログに載ってると思うんですが、まだ見つけられずにいます。それでも1894年頃のカタログを見て、「おっ」と思いました。
そこには「Glas-Krystallmodelle(ガラス結晶模型)」の文字があって、一瞬「これだ!」と思ったんですが、よく見たら、こちらは板ガラスをカットして、結晶形に組み合わせたものでした。
同種のものは、上記デロールのカタログの同じページにも載っていて、そちらは「Séries cristallographiques en glace」(ガラス製結晶学シリーズ)と称しています。
これは「結晶形態学プロジェクト」にコラボ参加されている、ステンドグラス職人・ROUSSEAU(ルソー)さんの作品に通じる雰囲気があり、その祖型といって良いかもしれません。
(「結晶形態学プロジェクト」フライヤーより、ROUSSEAUさんの作品2種)
至高の石 ― 2017年11月23日 07時42分30秒
結晶形態学にちなむ優品――と敢えて呼びましょう――に続き、「至高の鉱物」を登場させます。
ラ・ピエール・フィロゾファル、すなわち「賢者の石」です。
卑金属を黄金に変える力を持つとされ、古来多くの錬金術師が探し求めた幻の石。そして、錬金術が神秘の学問体系で覆われるにつれて、賢者の石はいよいよ謎めいたシンボルとなっていきました。
隠秘学の世界における賢者の石は、
「自らは死することなく、すべての死せる者を再生させるもの」であり、
「人々に究極の治癒、すなわち救済をもたらす霊薬」であり、
「始原より来たれる第二のアダム」であり、
その究極の実体は、イエス・キリストその人である…と言われます。
この赤い小箱に、その賢者の石が入っているというのですが、いったいそれは?
これこそ、聖なる方の不朽体を収めた聖櫃(せいひつ)なのか?
★
…と、無理やり話を盛り上げましたが、中身はただの子供向け玩具です。
(おそらく1900年ころのフランス製)
中に入っているのは、紙製のゲームボードとチップ、それに1枚のルール解説書。
遊び方は簡単です。
最初に15個あるボードのマス目に、15個のチップを全部並べ(色は特に関係ありません)、2人のプレーヤーが交互に1~3個のチップを取り去り、最後の1個を取った方が負け…というもの。日本にも「石取りゲーム」という、同様のゲームがありますし、替わりばんこに数字を1から順に(1個ないし3個ずつ)唱え、最後に30(あるいは20)を言った方が負け…という遊びも、同工異曲でしょう。
この手の遊びには必勝法があって、「賢者の石」のルール解説書には、そのことも書かれています。
★
何だか羊頭狗肉な気もします。
でも、このゲームの何が「賢者の石」なのかと考えると、それはボードでもチップでもなくて、形のない必勝法こそそれなのだ…という事実に気づきます。そして、必勝法の存在に目覚めた子供たちの幾人かは、「あらゆる問題にはアルゴリズムが存在する」という強固な観念に取りつかれ、その長い探求の道へと歩み出す…。それこそが、このゲームの「賢者の石」と呼ばれる所以ではないでしょうか。
(具象の石と抽象の石。左はドイツの半貴石標本)
月の空を飛んだ兄弟の記憶(前編) ― 2017年11月24日 07時03分59秒
年の瀬が近づき、街はすっかりクリスマスムードです。
2017年ももうじき終わりですけれど、遅ればせながら2017年にちなんだ話題です。
★
今からちょうど半世紀前の1967年。
人間の背丈ほどの人工天体が、月の周りを回りながら、課せられたミッションにせっせと取り組んでいました。すなわち、アメリカの「ルナ・オービター」4号機および5号機です。そして、彼らのミッションとは、月面の詳細な写真地図を作ること。
(NASAのロゴ。下に紹介する書籍の扉より)
ルナ・オービター計画自体は1964年からスタートしており、月への接近も前年の1966年から始まっていました。ただし、前任の1号機から3号機までは、アポロ計画の露払いとして、その着陸予定地点を精査することを目的としており、月面地図作りの大仕事を任されたのが、後継の4号機と5号機だった、というわけです。
その期待に応えて、4号機は月面の大半を写真撮影することに成功し、さらに5号機が、4号機の撮り洩らしたエリアもすべて写真に収め、一連の計画はすべて成功裡に終わったのです。
…というのは、例によってウィキペディア(「ルナ・オービター計画」の項)の受け売りに過ぎませんが、受け売りついでに書くと、同じ項の以下の記述も一寸驚きです。
「ルナ・オービター計画の撮影システムは非常に複雑であった。まず、月面を撮影した後、軌道上にてフィルムの現像を自動で行い、濃淡を帯状にアナログスキャンし、データを地上に送信する。地上では、データをモニターに表示し、それを再び撮影する。そして最後に、帯状の画像をつなぎ合わせて全体の画像を作成していた。」
何といっても月探査機ですから、そこには当時の最先端技術が投入されたのでしょうが、画像処理に関しては、予想以上にローテクというか、アナログ一色の世界でした。しかし、それでも見事な成果を上げたところが、やっぱり偉いといえば偉いし、スゴいといえばスゴかったわけです。
★
ここでルナ・オービターの話題を持ち出したのは、先日、ルナ・オービターによる当時の月写真集を手にしたからです。
(高さ35cmを超える大判の写真集)
■L. J. Kosofsky & Farouk El-Baz,
『The Moon as Viewed by Lunar Orbiter』 (ルナ・オービターが見た月)
National Aeronautics and Space Administration (NASA)、1970
『The Moon as Viewed by Lunar Orbiter』 (ルナ・オービターが見た月)
National Aeronautics and Space Administration (NASA)、1970
下は同書に掲載されている撮像システム。
(左:撮像システム、右:フィルムフォーマット概念図(部分))
搭載のカメラは、中解像度の80mm広角レンズと高解像度の610mm狭角レンズを備え、装置内には79mの長大な70mmコダックフィルムが装填されていました。そこに、写角が広狭の画像を、互い違いに写し込んでいく仕組みです。
同じくフィルムスキャンシステム。
光源は電子線を当てた蛍光物質から発する光で、それをレンズで点状に集光し、フィルム上の画像を舐めるように走査した結果が対向面で記録され、画像信号として地上に送信されました。
★
かつて月上空を旋回した5機のルナ・オービターは、運用終了後、いずれも月面に落下し、その貴重な撮影フィルムも探査機本体と運命を共にしました。今となっては、ルナ・オービターの「声」を遥かな地上で聞き取って、それを元に画き起こした「絵」が、彼らの形見として残るのみです。
彼らの半世紀前の偉業をしのんで、ちょっと古めかしい写真集のページを開いてみます。
(この項つづく)
さよならの時 ― 2017年11月25日 16時29分33秒
犬や猫を飼っている人がよく漏らすのが、ペットの死を看取る辛さです。それが嫌さにペットを飼わないという人も多いようです。しかし、ヒトと犬・猫は、異なる時間の流れを生きている以上、そうしたすれ違いは避けがたいことです。
私は犬も猫も飼っていませんが、似たような看取りの辛さは、何度か経験しました。
ちょうど今も、そうした別離の時が近づいていることを感じて、何だか暗澹たる気持ちになっています。
★
今朝からPCの不調が続いていて、今もだましだまし使っています。
このところ、ちょっとしたエラーが頻発しており、それはソフト的なものではなく、ハード的なものであることを、HDDのかすかな異音に、微熱が続く本体に、ディスプレイの不可解な色滲みに感じ取り、死の予兆に戦(おのの)いています。
弱音を吐かずに付き合ってくれる彼/彼女に、ついつい無理をさせてしまった私も悪かったのでしょう。しかし、別離の根本原因は、ヒトと機械は違う時の流れの中で生きているという冷厳な事実です。
人が人であるがゆえに味わう「愛別離苦」。
別離に苦しむことは、私が人である証でもあります。
(ムンク作 「病める子」)
★
とはいえ、今は限りある命を全うできるよう、延命に最大限力を尽くしているので、昨日の記事の続きはお休みです。今後、ブログの更新が予告なく途絶えたら、上のような事情によるものとお考え下さい。
月の空を飛んだ兄弟の記憶(後編) ― 2017年11月26日 12時04分38秒
でも、そこで味わえるのは人類史における「一大事件」を追体験する喜びであり、そこにこそ、この写真集の価値はあると思います。
★
1959年、ソ連のルナ3号によって、初めて月の裏側の写真が撮られて以来、米ソの月探査機は、次々と月の知られざる風景を絵手紙にして我々に送ってくれました。
(ルナ3号が送ってきた月の裏側の最初の写真。Wikipedia「Luna 3」の項より)
そして、その後の急速な技術の進展は、10年も経たないうちに、ルナ・オービター計画による、この鮮明な月写真集を生み出すに至りました。
人類は過去何万世代にもわたって、空に月を見上げ、物思いにふけり、神話を紡ぎ、観測を続けてきましたが、20世紀後半に至って初めて――文字通り天地開闢以来初めて――「機械の眼」と「機械の神経系」を使って、月の裏側や月の空に浮かぶ地球といった、新奇な光景に接することとなったのです。その感動を思いやるべし、です。
上空から見渡す、峩々たる月の山脈と荒涼とした平原。それは、19世紀の人が夢に思い描いた光景そのものでした。
(エドムント・ヴァイス、『星界の絵地図』(1892)より)
新たに獲得した視界は、地上からはぼんやりしていた月の細部が、次々と明らかになっていく爽快感に満ちています。
(深さ1300mに達するシュレーター峡谷)
(ウサギの尻尾に当たる「湿りの海」と、そこに穿たれた三つ星のような小クレーター)
巨大な目玉模様の「東の海」は、地上から観望する際は、ほんの端役に過ぎませんが、こうして正面から見れば超一級の役者であることが、よく分かります。
(月球儀に見る「東の海」)
さらにこの写真集は、高解像度写真で「東の海」の偉観を伝えてくれます。
上は「東の海」周辺と部分図(エリアA~F)の位置表示。
下はエリアA(左)とエリアB(右)の拡大図。
ちょっと変わったところでは、ルナ・オービター3号機は、1年前に月に降り立った先輩、「サーベイヤー1号」の姿もとらえています。
(円内がサーベイヤー1号の姿。右は拡大)
それは、月探査が着実に歴史の年輪を重ねつつあり、人類史が新たな局面に入ったことを物語るものでした。
★
NASAが作ったこの写真集は本当によくできていて、全写真の詳細データと、ルナ・オービター全5機が撮影した写真のインデックス・マップを完備しています。
(収載写真のデータ表(部分))
(8枚あるインデックス・マップの内の1枚)
(同凡例)
さらにおまけとして、同一地点をわずかな時間差で撮影した2枚を、赤青で重ね刷りしたステレオ写真(アナグリフ写真)が何枚か載っているのも楽しい工夫です。
(赤青の立体メガネも付属)
この歴史的写真集は当時大量に刷られたせいか、現在の古書価はごく低廉で、私は2千円ちょっとで買いました。こういうのをリーズナブルな買い物と言うのではないでしょうか。
-----------------------------------------------------
【補遺】
この写真集、今の目で見ると何となくボンヤリした画像に見えるかもしれません。
でも、それは「前編」で触れたように、ルナ・オービターによる画像取得が、
①月面撮影 → ②フィルムをアナログスキャン → ③電送 →
④受信データを地上でテレビモニターに映写 → ⑤モニター画面を撮影 →
⑥撮影画像を継ぎ合わせて全体を撮影
④受信データを地上でテレビモニターに映写 → ⑤モニター画面を撮影 →
⑥撮影画像を継ぎ合わせて全体を撮影
という、非常にまどろっこしい方法を採っているせいです。
オービターの眼が捉えた本来の画像は、もっと鮮明なものでした。
原撮影に使用されたフィルムは、コダックの「SO-243」、すなわち航空写真用に作られた高解像度の超微粒子フィルムで、記録できるライン数は450本/mm。これに対して、オービターのスキャンシステムは、解像度が76本/mmだったので、スキャンの段階で、実は大半の情報が脱落してしまったのです。
単純化していえば、オービターの「生写真」は、我々が地上で目にする電送写真の約6倍(単位面積では36倍)の記録密度を持っており、その情報が機体と共に失われたことは、当時の科学者にとって一大痛恨事だったことでしょう。
飛び出るクレーター ― 2017年11月27日 21時14分50秒
ルナ・オービターにちなむ品として、印刷ではない「生写真」が手元にあるので、この機会に載せておきます。
「生写真」と言っても、昨日述べたような理由で、ルナ・オービターが撮影した本当の生写真は地球上に存在しないのですが、NASAが配布した紙焼き写真には、何となくルナ・オービターの体温や肉声に近いものが感じられます。
この2枚組は、ステレオ写真を狙って撮影されたもの。写真が顔を覗かせている枠の大きさは約13×11cmですから、そんなに大きなものではありません。撮影したのは、月面地図作りに活躍したルナ・オービター4号機、5号機ではなく、アポロの着陸候補地の調査を担当していた3号機。
額縁から出すと、こんな感じです。
欄外の「NASA-LRC」というのは、NASAの一部門である「ラングレー研究センター(Langley Research Center)」を指します。LRCは1965年、センター内に月着陸研究施設(Lunar Landing Research Facility )を開設し、月面着陸に備えて、実物大モジュールを使った模擬着陸に取り組んでいました(…と、知ったかぶりして書いていますが、もちろんネットで知ったことの受け売りです)。
写真裏側の印字情報。
この写真が月で撮影されたのは、1967年2月19日で、プレスリリースされたのは、1969年2月13日です。
アポロ11号の月着陸は1969年7月20日のことですから、それを目前にして、全米が熱狂ムードにある中、2年前の業績を振り返りつつ、報道陣に提供された1枚なのでしょう。
中央に写っているのは、直径は約3.8kmの「メスティングC」クレーター。(“MOSTING”と印字されていますが、正確には“MÖSTING”です。)
月の経緯表示は、地球から見た時、ちょうど月の真ん中にくる位置が原点で、メスティングCはその中心近く、南緯1.8度、西経8.1度の位置にあります(月のウサギのおへその辺りと言ったほうが早いかも)。月を眺めれば、嫌でも目に入る位置ですから、アピール性があったのかもしれません。
★
あれから半世紀―。
月探査の話題は、アポロ以後もたびたびニュースになりますけれど、かつての熱気に比べれば、随分おとなしいものです。人類史における「一大事件」も、人間の生来の飽きっぽさの前には顔色なし…といったところで、そこに人類の頼もしさと同時に限界を感じます。
THE MOON, Real & Decorative ― 2017年11月29日 07時20分16秒
時代はよく分かりませんが、古い月のブローチを見つけました。
差し渡し約3cmの、かわいらしいサイズ。
銀製で、しかもムーンストーンがはめ込まれている点が、いかにも月らしいと思いました。
三日月の外縁部は、いぶし加工が施されているので、光の当たる角度によって、こんなふうに「黒い月」にも見えます。
(裏面)
月をかたどったブローチは、それこそ星の数ほどあるでしょうが、このブローチにいたく心を惹かれたのは、上に述べたような理由のほか、このデザインそのものに「これは!」と思うものがあったからです。
ムーンストーン、アメシスト、オパール、そして銀の小粒が並ぶ月の内縁部。
デザイナーがどこまで自覚的だったかは不明ですが、この部分の表現が、いかにも月の欠け際に大小のクレーターが居並ぶ光景に思えて、「これぞ迫真性と装飾性を兼ね備えた、月ブローチの優品だ!」と、勝手に盛り上がった…というわけです。
まあ、単に私の独り相撲かもしれないんですが、それを差し引いても、このブローチはなかなか美しいと思います。
ムーンストーンの月 ― 2017年11月30日 21時01分59秒
Moonstone ―「月の石」。
アポロが持ち帰ったのも「月の石」で紛らわしいですが、こちらは英語だと「Moon rock」で、まったくの別物です。でも、英語版Wikipediaで「Moonstone」の項を見たら、「両者を混同してはならない」と、冒頭に断り書きがしてあったので、アメリカにも混同する人がいるのでしょう。
★
ムーンストーンは、日本では「月長石」と訳されました。
(インド産の月長石)
月長石と聞けば、銀河鉄道の線路沿いに咲く、「月長石ででも刻まれたような、すばらしい紫のりんどうの花」を思い出します。そして、賢治はほかにも自作で、月長石に幾度か触れていることを、加藤碵一・青木正博両氏の『賢治と鉱物』(工作舎、2011)を読んで知りました。
孫引きすると、
眼をつぶると天河石です、又月長石です
(「小岩井農場」先駆形A)
(「小岩井農場」先駆形A)
あるいは、
うすびかる 月長石のおもひでより かたくなに眠る 兵隊の靴
(大正5年8月17日付け保阪嘉内あて葉書)
(大正5年8月17日付け保阪嘉内あて葉書)
などなど。
これらを読み比べると、両氏が記すように、賢治の脳裏にある月長石には、青く光り輝くイメージと、冬の日を思わせる寂しい乳白色のイメージの両様があったようです。
これは宝石のムーンストーンにも、その輝色によって、青光を放つものと、白光を放つものの2種類があることに対応しています。
ただ、月長石をストレートに「月」と重ねて詠んだ例は見られないので、詩人・賢治は、そういう幼稚な――よく言えば素朴な――比喩を用いるのを、潔しとしなかったのかもしれません。
でも、私は以前から「ムーンストーンでできた月」があれば素敵だなと思っていました。昨日の月のブローチもムーンストーンをあしらったものですが、もっと月そのものというか、たとえば月長石を刻んで拵えた三日月があれば…と考えていたのです。
残念ながら、まだそういう品を目にしたことはありません。
そういう切削加工そのものが困難なのか、あるいは通常のカボションカット以外だと、ムーンストーン独自の輝きが生まれないので、ムダな努力をあえてしないのか、正確な理由は門外漢には、よく分かりません。
★
現実にあるのは、例えば三日月形の台座に、円いムーンストーンを並べた、こんな品です。
こういう莢(さや)豆型のブローチは、ヴィクトリア時代にずいぶん流行ったらしく、今でもよく目にします。手元のブローチは、これまた時代不明ですが、つややかなムーンストーンの列は、空を転がる満月を思わせ、また月の女神セレネーの皓歯のようでもあります。当初のイメージとは違いますが、これはこれで愛らしい品。
★
ときに、月にも月長石は産するのでしょうか?
長石の仲間は、地球でも月でもありふれた造岩鉱物ですから、探せばきっとあるでしょう。Moon rock から採ったMoonstoneで月を刻み、それを月光にかざしたら、どんな光を放つのか?…なんてちょっとベタですが、連想はそんなところにも及びます。


















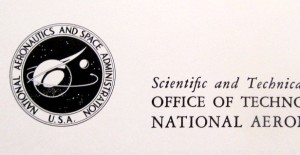
































最近のコメント