賢治と土星と天王星 ― 2022年12月17日 11時24分30秒
先日話題にした、賢治の詩に出てくる「輪っかのあるサファイア風の惑星」。
コメント欄で、件の惑星は、やっぱり天王星という可能性はないだろうか?という問題提起が、S.Uさんからありました。これは想像力をいたく刺激する説ですが、結論から言うと、その可能性はやっぱりないんじゃないかなあと思います。
★
1970年代後半に、恒星の掩蔽観測から発見された天王星の環ですが、そのはるか昔、18世紀の末にも天王星の環を見たという人がいました。他でもない、天王星の発見者であるウィリアム・ハーシェル(1738-1822)その人で、彼は天王星本体のほかに、天王星の衛星と環を発見したという追加報告を行っています(※)。
しかし、他にこの環は見たという人は誰もいないので、まあハーシェルの見間違いなんだろう…ということで、その後無視され続けていました(父を尊敬していた息子のジョン・ハーシェルでさえも、自著『天文学概論』(1849)で、「天王星に関して我々の目に映るものは、小さな丸く一様に輝く円盤だけである。そこには環も、帯も、知覚可能な斑文もない」と、にべもない調子で述べています)。
当然、明治以降に日本で発行された天文書で、それに言及するものは皆無です。
この点も含めて、取り急ぎ手元にある天文書から、関係する天王星と土星の記述(色とか、「まん円」かどうかとか、衛星の数とか)を抜き出してみたので、参考としてご覧ください。
★
それともうひとつ気になったのは、これもS.Uさんご指摘の「7個の衛星」の謎です。
土星の衛星は17世紀に5個(タイタン、テティス、ディオーネ、レア、ヤペタス)、18世紀に2個(ミマス、エンケラドス)、19世紀に2個(ヒペリオン/1848、フェーベ/1899)発見されており、その後1966年にヤヌスが発見されて、都合10個になりました。賢治の時代ならば9個が正解です。
ただし、19世紀には上に挙げた以外にも、キロンやテミスというのが報告されており、後に誤認と判明しましたが、同時代の本はそれを勘定に入れている場合があるので、土星の衛星の数は、書物によって微妙に違います(上の表を参照)。
いずれにしても、サファイア風の惑星が土星であり、その衛星が7個だとすれば、それは19世紀前半以前の知識ということになります。
賢治の詩に出てくる
ところがあいつはまん円なもんで
リングもあれば月も七っつもってゐる
第一あんなもの生きてもゐないし
まあ行って見ろごそごそだぞ
リングもあれば月も七っつもってゐる
第一あんなもの生きてもゐないし
まあ行って見ろごそごそだぞ
というのは、夜明けにサファイア風の惑星に見入っている主人公ではなくて、脇からそれに茶々を入れている「草刈」のセリフです。粗野な草刈り男だから、その振り回す知識も古風なんだ…と考えれば一応話の辻褄は合いますが、はたして賢治がそこまで考えていたかどうか。賢治の単純な勘違いかもしれませんし、何かさらに深い意味があるのかもしれませんが、今のところ不明というほかありません。
(※)ハーシェルは彼の論文「ジョージの星〔天王星〕の4個の新たな衛星の発見について」(On the Discovery of four additional Satellites of the Georgium Sidus, Philosophical Transaction, 1798, pp.47-79.)の中で、以下の図7、8のようなスケッチとともに、1787年3月に天王星の環を見たという観測記録を提示しています。
--------------------------------------------------------------------
【閑語】
岸田さんという人は、もともとハト派で、どちらかというと「沈香も焚かず屁もひらず」的な人だと思っていました。でも、途中からどんどん印象が悪くなって、尾籠な言い方で恐縮ですが、どうも屁ばかりひっているし、最近は動物園のゴリラのように、それ以上のものを国民に投げつけてくるので、本当に辟易しています。
まあ岸田さんの影にはもっとよこしまな人が大勢いて、岸田さんを盛んに揺さぶっているのでしょうが、でも宰相たるもの、そんな簡単に揺すられ放題ではどうしようもありません。
それにしても、今回の国民的増税の話を聞くと、ここ数年、政府がマイナンバーカードの普及に血道を上げていた理由もよく分かるし、大盤振る舞いをもくろんでいる防衛費が、めぐりめぐって誰の懐に入るのか、雑巾や油粕のように搾り取られる側としては、大層気になります。
コメント
_ S.U ― 2022年12月17日 13時22分35秒
_ 玉青 ― 2022年12月17日 16時06分19秒
あはは、お役目大義に存じます。
勧進帳をそらで読み上げた弁慶の役を果たせたかどうかは心もとないですが、とりあえず富樫の温情により、無事関を越えられたことにいたしましょう。(^J^)
ときに「鎮星色青」の件。むむ、これは!と思いました。
さっき書棚をごそごそやっているとき、抱影の『星の美と神秘』(昭和21)も開いたのですが、その「惑星の美」の章には、「土星はリングがあるので有名だが〔…〕肉眼には青ずんだ、陰気な光の惑星であるに過ぎない」という記述がありました。抱影はその直前で、木星の「惑星の王者にふさはしい大らかな金色」に言及しているので、それとの対比でこう書いたのかもしれませんが、古典好きの抱影翁のことですから、ひょっとして吾妻鏡の「鎮星色青」も同時に念頭に置いていたかもしれません。いずれにしても、賢治も抱影も土星に「青」を感じたというのが興味深いです。
>黒幕は…どちらなのでしょうか
おそらく利用できる間はせいぜい盛り立て、利用価値がなくなれば弊履の如く捨て去って顧みないという、よくあるパターンかと。
勧進帳をそらで読み上げた弁慶の役を果たせたかどうかは心もとないですが、とりあえず富樫の温情により、無事関を越えられたことにいたしましょう。(^J^)
ときに「鎮星色青」の件。むむ、これは!と思いました。
さっき書棚をごそごそやっているとき、抱影の『星の美と神秘』(昭和21)も開いたのですが、その「惑星の美」の章には、「土星はリングがあるので有名だが〔…〕肉眼には青ずんだ、陰気な光の惑星であるに過ぎない」という記述がありました。抱影はその直前で、木星の「惑星の王者にふさはしい大らかな金色」に言及しているので、それとの対比でこう書いたのかもしれませんが、古典好きの抱影翁のことですから、ひょっとして吾妻鏡の「鎮星色青」も同時に念頭に置いていたかもしれません。いずれにしても、賢治も抱影も土星に「青」を感じたというのが興味深いです。
>黒幕は…どちらなのでしょうか
おそらく利用できる間はせいぜい盛り立て、利用価値がなくなれば弊履の如く捨て去って顧みないという、よくあるパターンかと。
_ S.U ― 2022年12月18日 09時07分21秒
お知らせありがとうございます。抱影翁に「青ずんだ」があったのですね。
土星は文句なく黄色に見えますが、私が小口径の望遠鏡で150倍くらいの高倍率で土星を見ると輝度が落ちたくすんだ黄色が、緑色がかかって見え、灰緑色というか、鶯色、萌葱色のような色に見えることがあります。抱影もロングトムで倍率を上げたらそのように見えたかもしれません。肉眼でその色に見えるかはわかりません。『吾妻鏡』も抱影も昔の人ですので、くすんだ緑を「青い」と表現する(あるいは感じる)ということもあるのかもしれないと思います。
土星は文句なく黄色に見えますが、私が小口径の望遠鏡で150倍くらいの高倍率で土星を見ると輝度が落ちたくすんだ黄色が、緑色がかかって見え、灰緑色というか、鶯色、萌葱色のような色に見えることがあります。抱影もロングトムで倍率を上げたらそのように見えたかもしれません。肉眼でその色に見えるかはわかりません。『吾妻鏡』も抱影も昔の人ですので、くすんだ緑を「青い」と表現する(あるいは感じる)ということもあるのかもしれないと思います。
_ 図版研 ― 2022年12月19日 10時07分39秒
川本幸民『氣海觀瀾廣義』卷四に、直交する二つの輪と六つ(あるいは八つ)の衛星を持つ「穀星」として天王星が出てきます
https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ni03/ni03_01391/ni03_01391_0004/ni03_01391_0004_p0009.jpg
ので、あるいはこれが念頭におありだったのかもしれませんね(ご参考までに、丁を開いた図版を☝URLのファイルストレージに仮置きしてあります)。
https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ni03/ni03_01391/ni03_01391_0004/ni03_01391_0004_p0009.jpg
ので、あるいはこれが念頭におありだったのかもしれませんね(ご参考までに、丁を開いた図版を☝URLのファイルストレージに仮置きしてあります)。
_ 玉青 ― 2022年12月24日 08時30分58秒
貴重な情報をありがとうございます!
PCの不調によりお返事が遅れたことをどうかご容赦ください。
この「気海観瀾広義」は図版研さんの架蔵書でしょうか?本当に何でもお持ちですね!
この本は、私も関係している日本ハーシェル協会のサイトで話題になったことがあります(http://www.ne.jp/asahi/mononoke/ttnd/herschel/a-text/Herschels_in_Japan.html)。話題にしたのは、他ならぬ上でコメントをいただいたS.Uさんです。
そんなわけで何となくデジャヴがあるのですが、本文で天王星の環に言及していたことは意識から欠落していました。この「直交する環と6つの衛星」はウィリアム・ハーシェルの所説を祖述したものと思いますが、西洋でその説が下火になった頃に、極東でその説が「復活」したのは面白いですね。例の「草刈男」は昔聞き覚えた知識を、こうして今も振り回して賢治の心を悩ませているのかもしれません。こうなると天王星説も大いに見込みありですね。
とはいえ、冷静に考えると、そもそも薄明の空で天王星を肉眼で見ることは困難ですから、土星説をひっくり返すことはやっぱり難しいんじゃないかなあ…と思うんですが、文学作品には読む側の自由もあるので、暁の空に、サファイア色の天王星を幻視し、それに心奪われる賢治を思い浮かべるのは興の深いことと思います。
PCの不調によりお返事が遅れたことをどうかご容赦ください。
この「気海観瀾広義」は図版研さんの架蔵書でしょうか?本当に何でもお持ちですね!
この本は、私も関係している日本ハーシェル協会のサイトで話題になったことがあります(http://www.ne.jp/asahi/mononoke/ttnd/herschel/a-text/Herschels_in_Japan.html)。話題にしたのは、他ならぬ上でコメントをいただいたS.Uさんです。
そんなわけで何となくデジャヴがあるのですが、本文で天王星の環に言及していたことは意識から欠落していました。この「直交する環と6つの衛星」はウィリアム・ハーシェルの所説を祖述したものと思いますが、西洋でその説が下火になった頃に、極東でその説が「復活」したのは面白いですね。例の「草刈男」は昔聞き覚えた知識を、こうして今も振り回して賢治の心を悩ませているのかもしれません。こうなると天王星説も大いに見込みありですね。
とはいえ、冷静に考えると、そもそも薄明の空で天王星を肉眼で見ることは困難ですから、土星説をひっくり返すことはやっぱり難しいんじゃないかなあ…と思うんですが、文学作品には読む側の自由もあるので、暁の空に、サファイア色の天王星を幻視し、それに心奪われる賢治を思い浮かべるのは興の深いことと思います。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
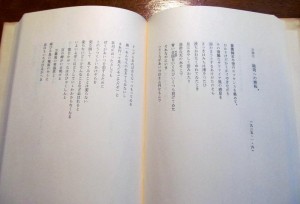


普通なら、「ハーシェルの見間違いだろう。放っておけ」ということで済ますところでしょうが、ハーシェル協会だとそうもいかず、お役目上、一応口に出さざるをえず、いたって役の軽い者からでも口に出た限りは、安宅の関守と同様、難詰せねばなりません。協会の荷の重いところです。
お調べの結果、土星と天王星の衛星数は、賢治の在世中の日本書で一応リーズナブルな範囲に収束していたようですね。ちゃんとした西洋文献ソースを見ているなら当然かもしれませんが、私にはちょっと驚きでした。
衛星数7個は、19世紀前半の土星だろうということで、とりあえず退却します。
ちょっと余録の情報です。
「鎮星色青」で、ネット検索すると、これがけっこうヒットします。これは、鎌倉時代の歴史文献『吾妻鏡』にある、「鎮星色青赤にて芒角有り」の記述で、治承5年(1181)に現れたカシオペヤ座の超新星の記録です。超新星が低空で青赤色に変化して見えたのだと思いますが、それが土星に喩えられた理由は不明です。この種の色の記述は、SN1181の色としても土星の色としても他に例は見つからず、今のところ、『吾妻鏡』の著者の創案とみるしかありません。ネット検索では、中国語のサイトも多くかかりますが、すべて日本の『吾妻鏡』の引用で中国に独立した同様のソースはないようです(もし、他の文献があればお知らせいただけますとありがたいです)。この超新星は、平清盛の死んだ年に出たもので、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』に出ないかと見ていましたが、残念ながら出ませんでした。
>閑語
岸田さんは確かに豹変しましたね。広島出身の平和主義とか、所得倍増目標はどこに行ったのでしょうか。確かに、黒幕がついたのでしょう。黒幕は、岸田さんをもり立てていっしょにがんばろうとしているのか、岸田さんを不人気にして下ろしてやろうとしているのか、どちらなのでしょうか。