現代の古地図(後編) ― 2018年03月26日 22時55分53秒
かつて、夏から秋へと季節が移るころ、2隻の船が相次いで故郷の港を後にしました。
その姿は、彼らがこれから越えようとする大洋の広さにくらべれば、あまりにも小さく、かよわく、今にも波濤に呑み込まれそうに見えました。
しかし、彼らは常に勇敢に、賢くふるまいました。彼らは声を掛け合い、互いに前後しながら、長い長い船旅を続け、ついに故郷の港を出てから3年後に、それまで名前しか知られていなかった或る島へと上陸することに成功します。その島の驚くべき素顔といったら!
後の人は、彼らが残した貴重な記録をもとに、その島の不思議な地図を描き上げ、2隻の船の名前とともに、永く伝えることにしたのでした…
★
勇気と智慧に富んだ2隻の船。それは、ずばり「航海者」という名前を負った、惑星探査機の「ボイジャー1号、2号」です。
1号は1977年9月5日に、2号は同年8月20日に、ともにフロリダのケープカナベラルから船出しました。途中で1号が2号を追い抜き、1号は1980年11月に、2号は1981年8月に土星に到達。(したがって、正確を期せば、2号の方は3年ではなく、4年を要したことになります。)
そして、彼らは上陸こそしませんでしたが、土星のそばに浮かぶ「島」の脇を通り、その謎に包まれていた素顔を我々に教えてくれたのでした。その「島」とは、土星の第一衛星・ミマスです。
★
この時のデータを使って、1992年にアメリカ地質調査所(U.S. Geological Survey)が出版したミマスの地図は、確かに「現代の古地図」と呼ばれる資格十分です。
例によって狭い机の上では広げることもままなりませんが、全体はこんな感じです(紙面サイズは約67.5×74cm)。地図は、北緯57度から南緯57度までを描いた方形地図(200万分の1・メルカトル図法)と、南極を中心とした円形地図(122万3千分の1・極ステレオ図法)の組み合わせからできています。
多数のクレーターで覆われた地表面は、何となくおぼろで鮮明さを欠き、データの欠落が巨大な空白として残されています。
そんな茫洋とした風景の中に突如浮かび上がる奇地形が、他を圧する超巨大クレーター「ハーシェル」です。
★
ボイジャーがミマスを訪れてから四半世紀近く経った2004年。
別の新造船が土星を訪れ、10年間の長期にわたって土星観測を続けました。
それが惑星探査機「カッシーニ」です。
このとき、ミマスについても一層詳細な調査が行われ、2014年には下のように精確な地図が作られました。
(ウィキペディア「ミマス」の項より)
解像度も高く、空白もないこの新たな地図を手にした今、ボイジャーがもたらした地図は価値を失ったのか…といえば、そんなことはありません。昨日の自分は、こんなことを書きました。
「古地図を見れば、当時の人が利用できたデータの質と量が分かる仕組みで、古地図には<地理的=空間的>データと、<歴史的=時間的>データが重ね合わされていると言えます。〔…〕古地図は古版画芸術であると同時に、人類の世界認識の変遷を教えてくれる、貴重な史資料でもあります。」
ボイジャーのミマス地図についても、まったく同じことが言えます。
繰り返しになりますが、これこそ「現代の大航海時代」が生んだ、「現代の古地図」なのです。(ボイジャーの地図は紙でできている…というのが、また古地図の風格を帯びているではありませんか。)
飛び出るクレーター ― 2017年11月27日 21時14分50秒
ルナ・オービターにちなむ品として、印刷ではない「生写真」が手元にあるので、この機会に載せておきます。
「生写真」と言っても、昨日述べたような理由で、ルナ・オービターが撮影した本当の生写真は地球上に存在しないのですが、NASAが配布した紙焼き写真には、何となくルナ・オービターの体温や肉声に近いものが感じられます。
この2枚組は、ステレオ写真を狙って撮影されたもの。写真が顔を覗かせている枠の大きさは約13×11cmですから、そんなに大きなものではありません。撮影したのは、月面地図作りに活躍したルナ・オービター4号機、5号機ではなく、アポロの着陸候補地の調査を担当していた3号機。
額縁から出すと、こんな感じです。
欄外の「NASA-LRC」というのは、NASAの一部門である「ラングレー研究センター(Langley Research Center)」を指します。LRCは1965年、センター内に月着陸研究施設(Lunar Landing Research Facility )を開設し、月面着陸に備えて、実物大モジュールを使った模擬着陸に取り組んでいました(…と、知ったかぶりして書いていますが、もちろんネットで知ったことの受け売りです)。
写真裏側の印字情報。
この写真が月で撮影されたのは、1967年2月19日で、プレスリリースされたのは、1969年2月13日です。
アポロ11号の月着陸は1969年7月20日のことですから、それを目前にして、全米が熱狂ムードにある中、2年前の業績を振り返りつつ、報道陣に提供された1枚なのでしょう。
中央に写っているのは、直径は約3.8kmの「メスティングC」クレーター。(“MOSTING”と印字されていますが、正確には“MÖSTING”です。)
月の経緯表示は、地球から見た時、ちょうど月の真ん中にくる位置が原点で、メスティングCはその中心近く、南緯1.8度、西経8.1度の位置にあります(月のウサギのおへその辺りと言ったほうが早いかも)。月を眺めれば、嫌でも目に入る位置ですから、アピール性があったのかもしれません。
★
あれから半世紀―。
月探査の話題は、アポロ以後もたびたびニュースになりますけれど、かつての熱気に比べれば、随分おとなしいものです。人類史における「一大事件」も、人間の生来の飽きっぽさの前には顔色なし…といったところで、そこに人類の頼もしさと同時に限界を感じます。
月の空を飛んだ兄弟の記憶(後編) ― 2017年11月26日 12時04分38秒
でも、そこで味わえるのは人類史における「一大事件」を追体験する喜びであり、そこにこそ、この写真集の価値はあると思います。
★
1959年、ソ連のルナ3号によって、初めて月の裏側の写真が撮られて以来、米ソの月探査機は、次々と月の知られざる風景を絵手紙にして我々に送ってくれました。
(ルナ3号が送ってきた月の裏側の最初の写真。Wikipedia「Luna 3」の項より)
そして、その後の急速な技術の進展は、10年も経たないうちに、ルナ・オービター計画による、この鮮明な月写真集を生み出すに至りました。
人類は過去何万世代にもわたって、空に月を見上げ、物思いにふけり、神話を紡ぎ、観測を続けてきましたが、20世紀後半に至って初めて――文字通り天地開闢以来初めて――「機械の眼」と「機械の神経系」を使って、月の裏側や月の空に浮かぶ地球といった、新奇な光景に接することとなったのです。その感動を思いやるべし、です。
上空から見渡す、峩々たる月の山脈と荒涼とした平原。それは、19世紀の人が夢に思い描いた光景そのものでした。
(エドムント・ヴァイス、『星界の絵地図』(1892)より)
新たに獲得した視界は、地上からはぼんやりしていた月の細部が、次々と明らかになっていく爽快感に満ちています。
(深さ1300mに達するシュレーター峡谷)
(ウサギの尻尾に当たる「湿りの海」と、そこに穿たれた三つ星のような小クレーター)
巨大な目玉模様の「東の海」は、地上から観望する際は、ほんの端役に過ぎませんが、こうして正面から見れば超一級の役者であることが、よく分かります。
(月球儀に見る「東の海」)
さらにこの写真集は、高解像度写真で「東の海」の偉観を伝えてくれます。
上は「東の海」周辺と部分図(エリアA~F)の位置表示。
下はエリアA(左)とエリアB(右)の拡大図。
ちょっと変わったところでは、ルナ・オービター3号機は、1年前に月に降り立った先輩、「サーベイヤー1号」の姿もとらえています。
(円内がサーベイヤー1号の姿。右は拡大)
それは、月探査が着実に歴史の年輪を重ねつつあり、人類史が新たな局面に入ったことを物語るものでした。
★
NASAが作ったこの写真集は本当によくできていて、全写真の詳細データと、ルナ・オービター全5機が撮影した写真のインデックス・マップを完備しています。
(収載写真のデータ表(部分))
(8枚あるインデックス・マップの内の1枚)
(同凡例)
さらにおまけとして、同一地点をわずかな時間差で撮影した2枚を、赤青で重ね刷りしたステレオ写真(アナグリフ写真)が何枚か載っているのも楽しい工夫です。
(赤青の立体メガネも付属)
この歴史的写真集は当時大量に刷られたせいか、現在の古書価はごく低廉で、私は2千円ちょっとで買いました。こういうのをリーズナブルな買い物と言うのではないでしょうか。
-----------------------------------------------------
【補遺】
この写真集、今の目で見ると何となくボンヤリした画像に見えるかもしれません。
でも、それは「前編」で触れたように、ルナ・オービターによる画像取得が、
①月面撮影 → ②フィルムをアナログスキャン → ③電送 →
④受信データを地上でテレビモニターに映写 → ⑤モニター画面を撮影 →
⑥撮影画像を継ぎ合わせて全体を撮影
④受信データを地上でテレビモニターに映写 → ⑤モニター画面を撮影 →
⑥撮影画像を継ぎ合わせて全体を撮影
という、非常にまどろっこしい方法を採っているせいです。
オービターの眼が捉えた本来の画像は、もっと鮮明なものでした。
原撮影に使用されたフィルムは、コダックの「SO-243」、すなわち航空写真用に作られた高解像度の超微粒子フィルムで、記録できるライン数は450本/mm。これに対して、オービターのスキャンシステムは、解像度が76本/mmだったので、スキャンの段階で、実は大半の情報が脱落してしまったのです。
単純化していえば、オービターの「生写真」は、我々が地上で目にする電送写真の約6倍(単位面積では36倍)の記録密度を持っており、その情報が機体と共に失われたことは、当時の科学者にとって一大痛恨事だったことでしょう。
月の空を飛んだ兄弟の記憶(前編) ― 2017年11月24日 07時03分59秒
年の瀬が近づき、街はすっかりクリスマスムードです。
2017年ももうじき終わりですけれど、遅ればせながら2017年にちなんだ話題です。
★
今からちょうど半世紀前の1967年。
人間の背丈ほどの人工天体が、月の周りを回りながら、課せられたミッションにせっせと取り組んでいました。すなわち、アメリカの「ルナ・オービター」4号機および5号機です。そして、彼らのミッションとは、月面の詳細な写真地図を作ること。
(NASAのロゴ。下に紹介する書籍の扉より)
ルナ・オービター計画自体は1964年からスタートしており、月への接近も前年の1966年から始まっていました。ただし、前任の1号機から3号機までは、アポロ計画の露払いとして、その着陸予定地点を精査することを目的としており、月面地図作りの大仕事を任されたのが、後継の4号機と5号機だった、というわけです。
その期待に応えて、4号機は月面の大半を写真撮影することに成功し、さらに5号機が、4号機の撮り洩らしたエリアもすべて写真に収め、一連の計画はすべて成功裡に終わったのです。
…というのは、例によってウィキペディア(「ルナ・オービター計画」の項)の受け売りに過ぎませんが、受け売りついでに書くと、同じ項の以下の記述も一寸驚きです。
「ルナ・オービター計画の撮影システムは非常に複雑であった。まず、月面を撮影した後、軌道上にてフィルムの現像を自動で行い、濃淡を帯状にアナログスキャンし、データを地上に送信する。地上では、データをモニターに表示し、それを再び撮影する。そして最後に、帯状の画像をつなぎ合わせて全体の画像を作成していた。」
何といっても月探査機ですから、そこには当時の最先端技術が投入されたのでしょうが、画像処理に関しては、予想以上にローテクというか、アナログ一色の世界でした。しかし、それでも見事な成果を上げたところが、やっぱり偉いといえば偉いし、スゴいといえばスゴかったわけです。
★
ここでルナ・オービターの話題を持ち出したのは、先日、ルナ・オービターによる当時の月写真集を手にしたからです。
(高さ35cmを超える大判の写真集)
■L. J. Kosofsky & Farouk El-Baz,
『The Moon as Viewed by Lunar Orbiter』 (ルナ・オービターが見た月)
National Aeronautics and Space Administration (NASA)、1970
『The Moon as Viewed by Lunar Orbiter』 (ルナ・オービターが見た月)
National Aeronautics and Space Administration (NASA)、1970
下は同書に掲載されている撮像システム。
(左:撮像システム、右:フィルムフォーマット概念図(部分))
搭載のカメラは、中解像度の80mm広角レンズと高解像度の610mm狭角レンズを備え、装置内には79mの長大な70mmコダックフィルムが装填されていました。そこに、写角が広狭の画像を、互い違いに写し込んでいく仕組みです。
同じくフィルムスキャンシステム。
光源は電子線を当てた蛍光物質から発する光で、それをレンズで点状に集光し、フィルム上の画像を舐めるように走査した結果が対向面で記録され、画像信号として地上に送信されました。
★
かつて月上空を旋回した5機のルナ・オービターは、運用終了後、いずれも月面に落下し、その貴重な撮影フィルムも探査機本体と運命を共にしました。今となっては、ルナ・オービターの「声」を遥かな地上で聞き取って、それを元に画き起こした「絵」が、彼らの形見として残るのみです。
彼らの半世紀前の偉業をしのんで、ちょっと古めかしい写真集のページを開いてみます。
(この項つづく)
飛べ、スペース・パトロール ― 2017年10月13日 06時52分33秒
くるくる回るのは星座早見のみにあらず。
1950年代のルーレット式スピン玩具。アメリカから里帰りした日本製です。
紙製の筒箱の脇から突き出た黒いボタンをプッシュすると、
スペースパトロールの乗った宇宙船が、クルクルクル…と高速回転し、やがてピタッと目的の星を指し示します。
★
初の人工衛星、ソ連のスプートニク1号が飛んだのが1957年。
それに対抗して、アメリカがエクスプローラー1号を打ち上げたのが1958年。
ここに米ソの熾烈な宇宙開発競争が始まり、わずか12年後(1969年)には、有人月面探査という格段の難仕事を成し遂げるまでになりました。
こうした現実の技術開発を背景として、更にその先に予見された「宇宙旅行」や「宇宙探検」に胸を躍らせ、SFチックな「宇宙ヒーロー」に喝采を送ったのが、1950~60年代、いわゆるスペース・エイジの子どもたちでした。
★
上の玩具を作ったのは、もちろん子どもではなく大人ですが、そこはかとなく当時の子どもたちの気分を代弁しているかなあ…と思えるのが、「惑星の偉さの序列」です。
まずいちばん偉いのは何と言っても火星で、火星は100点満点。
今でも火星は人々の興味を引く天体でしょうが、この火星の突出した偉さというか、崇めたてまつる感じが、まさに時代の気分だと思います。
火星に次いで偉いのは、太陽系最大の惑星・木星80点、そして土星50点。
金星はややロマンに欠けるのか40点どまり。
さらに、ごく身近な月は30点で、地球はなんと0点です。
スペース・エイジの子どもたちの憧れが、どこに向いていたかを窺うに足る数字です。と同時に、当時の「宇宙」イメージが、いかにコンパクトだったかも分かります。
空の旅(18)…新しい旅のはじまり ― 2017年05月06日 09時22分28秒
時代が19世紀を迎えるころ、市民社会が訪れた…と、先日書きました。
そして20世紀を迎えるころ、今度は「大衆社会」がやってきたのです。
天文趣味にかこつけて言えば、それは天文趣味の面的広がりと、マスマーケットの成立を意味していました。
18世紀の末に、お手製の望遠鏡で熱心に星を眺めていたイギリスの或るアマチュア天文家は、道行く人々に不審と好奇の念を引き起こしました(後の大天文学者、ウィリアム・ハーシェルのことです)。でも、100年後の世界では、もはやそんなことはありません。望遠鏡で星を見上げることは、すでにありふれた行為となっていました。
19世紀末~20世紀はじめに発行された、望遠鏡モチーフの絵葉書類を一瞥しただけで、望遠鏡と天体観測が「大衆化」した様相を、はっきりと見て取ることができます。
それは大人も子供も、男性も女性も、富める者も貧しい者も楽しめるものとなっていましたし、ときに「おちょくり」の対象となるぐらい、日常に溶け込んでいたのです。
★
この頃、並行してアカデミックな天文学の世界では、革命的な進展が続いていました。銀河系の正体をめぐる論争は、最終的に「無数の銀河の存在」を結論付けるに至り、宇宙の大きさは、人々の脳内で急速に拡大しました。また、この宇宙を形作っている時間と空間の不思議な性質が、物理学者によって説かれ、人々を大いに眩惑しました。そして、高名な学者たちが厳かに認めた「火星人」の存在。
まあ、最後のは後に否定されてしまいましたが、そうしたイメージは、見上げる夜空を、昔の星座神話とは異なる新たなロマンで彩ったのです。
★
宇宙への憧れの高まり、新たな科学の時代に人々が抱いた万能感、そして実際にそれを裏付ける技術的進歩―。その先にあったのは、宇宙を眺めるだけではなく、自ら宇宙に乗り出そうという大望です。
(像の台座部分拡大)
ツィオルコフスキー自身は、自ら「宇宙時代」を目にすることはありませんでしたが、新しい時代の象徴として、これをぜひ会場に並べたいと思いました。
(ふと気づきましたが、今年はツィオルコフスキー生誕160周年であり、スプートニク打ち上げ60周年なんですね。「宇宙時代」もようやく還暦を迎えたわけです。)
★
こうして旅人は、現在、我々が立っているところまでたどり着きました。
長い長い空の旅。
ここで、この連載の第1回で書いたことを、再度そのまま引用します。
-------------------------------------------------------
1920~30年代に、ギリシャの学校で使われた天文掛図。
その傍らには、私の思い入れが、こんなキャプションになって添えられていました。
「古代ギリシャで発達した天文学が、様々な時代、多くの国を経て、ふたたびギリシャに帰ってきたことを象徴する品です。天文学の長い歴史の中で、惑星の名前はラテン語化されて、木星は「ジュピター」、土星は「サターン」と呼ばれるようになりましたが、この掛図ではジュピター(木星)は「ゼウス」、サターン(土星)は「クロノス」と、ギリシャ神話の神様が健在です。」
この掛図を眺めているうちに、ふと上の事実に気づいたとき、私の心の中でどれほどの長い時が一瞬にして流れ去ったか。「やっぱり、これは旅だ。長い長い旅なんだ…」と、これは私の個人的感懐に過ぎませんが、その思いの丈を、しばしご想像願えればと思います。
その傍らには、私の思い入れが、こんなキャプションになって添えられていました。
「古代ギリシャで発達した天文学が、様々な時代、多くの国を経て、ふたたびギリシャに帰ってきたことを象徴する品です。天文学の長い歴史の中で、惑星の名前はラテン語化されて、木星は「ジュピター」、土星は「サターン」と呼ばれるようになりましたが、この掛図ではジュピター(木星)は「ゼウス」、サターン(土星)は「クロノス」と、ギリシャ神話の神様が健在です。」
この掛図を眺めているうちに、ふと上の事実に気づいたとき、私の心の中でどれほどの長い時が一瞬にして流れ去ったか。「やっぱり、これは旅だ。長い長い旅なんだ…」と、これは私の個人的感懐に過ぎませんが、その思いの丈を、しばしご想像願えればと思います。
-------------------------------------------------------
こうして連載の最後に読み返すと、我ながら感慨深いものがあります。
(画像再掲)
会場のあの展示の前に、10秒以上とどまった方は、ほとんどいらっしゃらないでしょうが、私の単なる自己満足にとどまらず、あのモノたちの向うに広がる旅の光景は、やはりそれなりに大したものだと思います。
ともあれ、ご来場いただいた方々と、冗長な連載にお付き合いいただいた方々に、改めてお礼を申し上げます。
(この項おわり)
宇宙競争(後編) ― 2016年09月02日 06時38分31秒
(画像再掲)
正確にいうと、左側のは1952年版の「スペースレース」で、右側のは1957年版です。
57年版と52年版を比べると、惑星カードはまったく同じですが、トラブルカードの方を見ると…
57年版と52年版を比べると、惑星カードはまったく同じですが、トラブルカードの方を見ると…
(1957年版「スペースレース」のカード。昨日写っていたのは1952年版です)
あ!左下に何か見慣れぬカードが。
57年版では、52年版の「宇宙海賊」と「宇宙怪獣」が、「味方の衛星」と「スプートニク」に置き換わっているのでした。さらに、単純にプレイヤーが順番交代するのではなく、「味方の衛星」を引くと、さらに2枚カードを引けるラッキー要素が、「スプートニク」を引くと、「2回休み」という罰ゲーム要素が付け加わって、ゲームに一層変化を与えています。
★
それにしても、宇宙怪獣(あるいは宇宙海賊)がスプートニクに変化し、更なるマガマガシサを振り撒いている…というのが、まさに時代です。
1957年は、いわゆる「スプートニク・ショック」の年で、人工衛星の打ち上げでソ連に先んじられたアメリカが、猛然と追い上げを決意した年でもあります。まだ見ぬ「味方の衛星」に夢を託し、スプートニクに敵愾心を燃やしたアメリカの少年少女も多かったのでしょう。
(ただし、前々回の「土星の頭」の話に出てきたように、「スペースエイジは新たな地球同朋の時代だ。国同士のちっぽけな争いはもうやめよう」という論もあったので、当時の子どもたちの心が、ソ連憎し一色に染まっていたわけでは、当然ありません。)
★
アメリカはその後、有人月着陸を成功させて、大いに溜飲を下げました。
そして、「スペースレース」ゲームも、1969年にアポロ・バージョンのパッケージに衣替えし、それを盛大に祝ったのでした(何だか執念深い話ですね)。
そして、「スペースレース」ゲームも、1969年にアポロ・バージョンのパッケージに衣替えし、それを盛大に祝ったのでした(何だか執念深い話ですね)。
(69年版は持っていないので、これはeBayの商品ページから寸借。パッケージは変りましたが、中身は57年版と今度こそ本当に同じです。)
これぞ「スペースレース」、米ソの宇宙開発競争を体現したゲームだなあ…と、しみじみ思います。
宇宙競争(前編) ― 2016年09月01日 09時34分36秒
「スペースレース」と題されたカードゲーム2種。いずれも1950年代のものです。
「2種」といっても、版元は同じニューヨークのEd-U-Cards(エデュカーズ)社で、中身も一緒です。結局違うのはパッケージのデザインだけ。
カードは1から10まで、同じ絵柄が2枚ずつ含まれています(つまり2組のカードデッキが1セットになっています)。
ゲームは、2人のプレイヤーが、自分のデッキ(山札)をめくって、1番の「離陸」から10番の「地球着陸」まで、どちらが早く引き当てられるかを競うものです。(意中のカードが出なければ、ハズレカードは隣に積み上げて第2の山札とします。プレイヤーはどちらの山札をめくっても構いません。)
しかし、この旅の行程はかなり奇妙なものです。
地球を出発したプレーヤーは、まずいきなり土星に向います。それから木星→火星と引き返して、今度は一転して天王星へ。さらに海王星→金星→水星を経て、今度は一気に冥王星へ。何だか目が回りそうです。何かここには隠された秩序があるのか、ないのか…?
そしてカードデッキには、惑星カードのほかに、トラブルカードが含まれています。
モーターの故障、宇宙船の修理、燃料補給…etc.、これらのカードを引くと、相手のターンになって、今度は相手が山札を引く番になるというルールです。
モーターの故障、宇宙船の修理、燃料補給…etc.、これらのカードを引くと、相手のターンになって、今度は相手が山札を引く番になるというルールです。
★
この50年代チックな、微笑ましいカードゲーム。
しかし、そこにはある種の「時代相」が刻まれています。
しかし、そこにはある種の「時代相」が刻まれています。
冒頭、「違うのはパッケージデザインだけ」と書きましたが、実はこの2種類の「スペースレース」には、それ以外にも違うところが1つだけあります。
(この項つづく)
再びレーニン号 ― 2016年07月22日 06時16分39秒
ついでに、レーニン号の絵葉書も載せておきます。
星のまたたく暁の空(それとも夕暮れ?)。
砕氷船レーニン号と、軍艦のシルエットから照射されたサーチライトが、ソ連のロケットを真一文字に照らしています。
砕氷船レーニン号と、軍艦のシルエットから照射されたサーチライトが、ソ連のロケットを真一文字に照らしています。
何か政治的プロパガンダなのだろうと想像はつくものの、こういうのは背景が分からないと、何を表現しているか、さっぱり分からないですね。
絵葉書の下に書かれたロシア語をグーグルに尋ねたら、「Glory to the October!」の意味だと教えてくれました。すなわち、1917年に勃発した十月革命を讃える言葉だそうです。そうは分かっても、依然謎めいた感じは残りますが、おそらくソ連の技術力と軍事力が新しい時代を照らし、かつ切り拓く…みたいなイメージなのでしょう。
裏面には1961年の消印が押されており、これまた「熱くて冷たい」冷戦期の空気を今に伝えています。
まあ、強権政治の暗い記憶はそれとして、この砕氷船と青い星空の取り合わせには、たしかに涼味を感じます。
スプートニクの青いマッチラベル ― 2016年02月28日 09時25分47秒
スプートニクをモチーフにした、1950~60年代のマッチラベル。
こんなものをパッと見せられたら、「これは!」と思わず声が出るのでは?
何とも軽やかな色使いとデザイン。これは旧ソ連のプロパガンダ用とは到底思えず、フランスあたりで作られものではないでしょうか。
こんなものをパッと見せられたら、「これは!」と思わず声が出るのでは?
何とも軽やかな色使いとデザイン。これは旧ソ連のプロパガンダ用とは到底思えず、フランスあたりで作られものではないでしょうか。
こちらも同じシリーズ。浜辺?で見上げるスプートニク。
これも「やられたなあ」感が強いです。
これも「やられたなあ」感が強いです。
★
ここでタネを明かすと、これらはフランスでもソ連でも、ましてやアメリカでもなく、わがニッポンで作られたものなのでした。
神戸燐寸〔マッチ〕株式会社製。
戦後になっても、神戸はこの手のハイカラさに事欠かなかったようです。
戦後になっても、神戸はこの手のハイカラさに事欠かなかったようです。
うーむ、こういうのを「偉大な小芸術」というのでしょう。
それにしても、こういうデザインを手がけた人って、どんな経歴の人たちだったんでしょうね。
それにしても、こういうデザインを手がけた人って、どんな経歴の人たちだったんでしょうね。

























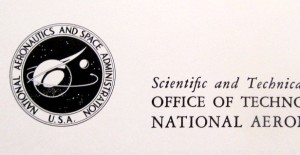



























最近のコメント