ジョバンニが見た世界…大きな星座の図(1) ― 2013年02月02日 19時46分54秒
(特に記事とは関係ありませんが、↑は平成7年に、千葉市立郷土博物館 と 府中市郷土の森博物館 で開催された「星座の文化史」展の図録)
このシリーズ、まずは「午後の授業」の場面、次いで「時計屋」の場面を順々に検討してきましたが、7年かけてついに最後のアイテムまでたどり着きました。実に長い長い道のりでした。
このシリーズ、まずは「午後の授業」の場面、次いで「時計屋」の場面を順々に検討してきましたが、7年かけてついに最後のアイテムまでたどり着きました。実に長い長い道のりでした。
★
煩をいとわず、もう一度「時計屋」の場面を全文引用します。
■ □ ■
ジョバンニは、せわしくいろいろのことを考えながら、さまざまの灯や木の枝で、すっかりきれいに飾られた街を通って行きました。時計屋の店には明るくネオン燈がついて、一秒ごとに石でこさえたふくろうの赤い眼が、くるっくるっとうごいたり、いろいろな宝石が海のような色をした厚い硝子の盤に載って星のようにゆっくり循(めぐ)ったり、また向う側から、銅の人馬がゆっくりこっちへまわって来たりするのでした。そのまん中に円い黒い星座早見が青いアスパラガスの葉で飾ってありました。
ジョバンニはわれを忘れて、その星座の図に見入りました。
それはひる学校で見たあの図よりはずうっと小さかったのですが その日と時間に合せて盤をまわすと、そのとき出ているそらがそのまま楕円形のなかにめぐってあらわれるようになって居り やはりそのまん中には上から下へかけて銀河がぼうとけむったような帯になって その下の方ではかすかに爆発して湯気でもあげているように見えるのでした。またそのうしろには三本の脚のついた小さな望遠鏡が黄いろに光って立っていましたし いちばんうしろの壁には空じゅうの星座をふしぎな獣や蛇や魚や瓶の形に書いた大きな図がかかっていました。ほんとうにこんなような蝎だの勇士だのそらにぎっしり居るだろうか、ああぼくはその中をどこまでも歩いて見たいと思ってたりして しばらくぼんやり立って居ました。
(「四、ケンタウル祭の夜」より)
■ □ ■
ジョバンニはこのあと、お母さんの用事を思い出して、牛乳屋へと向かいます(そこに「ミルキーウェイ」のイメージを重ねる解釈もあるようです)。
その直前に出てくるこの星座図、叙述の順序としては最後に登場しますが、おそらくショーウィンドウの中では、一番大きな面積を占めていたはずで、当然ジョバンニの目をまっさきに捉えたことでしょう。そして、これこそジョバンニをして銀河の旅へと向かわしめた品でもあります(=「ああぼくはその中をどこまでも歩いて見たい」)。したがって、作品世界においては非常に重要な役割を果たしている小道具だと言えます。
★
この星座図は、午後の授業に出てきた星座の掛図とイメージがかぶっていますが、ある意味、星座掛図以上に候補を探すのは難物です。世に星座絵はさまざまあれど、壁面を飾るぐらい大きな図はなかなかないからです。
もちろん、現代の星座ポスターは論外です。
クラシックかつアンティークな品で、それほど大きな星図が存在するかどうか?
…というわけで、そもそも過去に存在した星図は、どれぐらいの大きさがあるのか、調べてみることにしました。
(この項つづく)
ジョバンニが見た世界…大きな星座の図(2) ― 2013年02月04日 20時58分41秒
「大きな星座の図」の「大きな」とは、どれぐらいの大きさを言うのか。
あまり意味のある問いではないかもしれませんが、話の流れからちょっと調べてみました。
あまり意味のある問いではないかもしれませんが、話の流れからちょっと調べてみました。
前提として、ジョバンニが見たのは、空一面の星座を1枚の紙に描きこんだ集合星図ですから、おそらくは天の北極/南極を中心とする円形星図か、メルカトル式の星図でしょう。実際の作例としては前者のほうが圧倒的に多いので、ここでは主に円形星図の直径で考えることにします。
参照したのは、デボラ・J.ワーナーという人が著した、『The Sky Explored:Celsetial Cartgraphy 1500-1800』 です。これは過去に出版された星図総覧のような本で、データも豊富なので、それをざっと見て、大きそうな星図を選り出してみました。
その中で最大のものは、何と直径192センチ。
フランスのド・ラカイユ(Nicolas Louis de Lacaille 1713-1762)が、1754~5年にかけて作ったものです。
ただし、これは一般向けに出版されたものではありません。彼が南アフリカの喜望峰で南天観測を行った成果を、王立科学アカデミーで発表する際に、プレゼン用に作ったもので、現在はパリ天文台の展示ホールに掲げられているそうです。
(うまくスキャンできませんでした)
パリ天文台にあるという現物の画像を探したのですが、見つけられなかったので、上は参考図です。ラカイユ自らが原図に手を入れて、1756年に公刊した図を、さらに1776年に転載したもの。パリで出版された『フラムスティード星図(第2版)』の付図として収められています。(出典:『フラムスチード天球図譜』、恒星社厚生閣)
というわけで、これはまったくの例外。これほど大きな星図は、これ以外にワーナーの本には載っていません。
★
では、それに次ぐ大きさはといえば、イギリスのラム(Francis Lamb)が1679年に作った天球図で、直径は30インチ(約75センチ)。ラカイユの図の半分以下ですが、それでもずいぶん大きなものです。そのため、図↓のように、紙を4枚接いであります。これは南天図ですが、同じ大きさの北天図もあります。
(これまた画像を見つけられなかったので、ワーナーの本よりスキャン)
以下、ボーデ(Johann Elert Bode 1747-1826)やカッシーニ(Gian Domenico Cassini 1625-1712)等が手がけた、直径60センチの星図が3点、次いで、直径50センチ台の星図が5点ほど、ワーナーの本には記載されています。以上がいわば大きさ十傑。
要するに、古星図の世界では、直径50センチもあれば「巨大な星図」と呼んで差し支えなく、40センチ程度でも十分「大きな星図」と呼ばれる資格はあるといえます。
もちろん、ジョバンニがそういう星図界の事情に通じていたわけではないでしょうが、現実を踏まえれば、時計屋の店先に飾られていた星図は、「午後の授業」で使われた掛図ほど大きくなくても良い…というのが、ここでの一応の結論です。
(この項つづく)
小忙し ― 2013年02月07日 22時15分36秒
不測の用務が重なったため、「ジョバンニが見た世界」の筆が止まっています。再開まで数日かかりそうです。
ジョバンニが見た世界…大きな星座の図(3) ― 2013年02月10日 10時47分05秒
天気晴朗なれども、昨日も今日も冷えこみます。
記事の書き方を忘れないように、ぼちぼち話を進めます。
記事の書き方を忘れないように、ぼちぼち話を進めます。
★
時計屋の店先に飾られていた星座の図。
<サイズ>については、前回の記事で書いたように、円形星図ならば直径4~50cmクラスの大きさだと想像します。まあ、絶対的に「大きい」とも言い難いですが、脇に置かれた星座早見盤よりはずっと大きいですし、店先の飾り付けとしては、それぐらいの方が扱いやすいかもしれません。
次に、その<内容>を考えてみます。
もう一度原文に帰ると、
「〔…〕空じゅうの星座を ふしぎな獣や蛇や魚や瓶の形に書いた大きな図〔…〕ほんとうに こんなような蝎だの 勇士だの そらにぎっしり居るだろうか、ああぼくはその中をどこまでも歩いて見たい」
とあります。
ここに登場する星座の候補を、順不同で挙げてみます(黒は黄道星座、青は黄道よりも北、赤は南の星座)。
▼獣 (しし、おうし、おひつじ、やぎ、やまねこ、こじし、おおぐま、こぐま、りょうけん、きりん、ペガスス、こうま、こぎつね、おおかみ、おおいぬ、こいぬ、うさぎ、いっかくじゅう)
▼蛇 (へび、うみへび、みずへび)
▼魚 (うお、みなみのうお、とびうお、かじき)
▼瓶 (みずがめ)
▼蝎 (さそり)
▼勇士 (ヘルクレス、ペルセウス、オリオン)
候補が1つしかない「瓶」と「蠍」は即座に決定です。したがって、この星図に黄道12星座が描き込まれていることは確実。…となると、「魚」も「うお座」が有力ですし、「獣」はたくさんいるので1つに決まらないにしろ、獅子や牡牛の姿がそこに含まれることも、確からしく思えます。
「勇士」候補のうち、オリオンは勇士よりは「狩人」のイメージなので、ここではペルセウスないしヘルクレスが穏当かも。(ちなみに、賢治が愛読したとされる、吉田源治郎著『肉眼に見える星の研究』には、「オリオンは…世界に比無き偉い猟師」、「ペルセウスと云ふ勇士」、「ヘルクレスは…古代の半神のうちでも尤も名のある勇士」と叙述されています。)
とすると、この星図は黄道から北を表現した北天星図ということになりますが、即断は禁物。物語中に登場するのは以下の星座ですから、銀河鉄道の旅は、むしろ南に偏っています(その範囲は、だいたい赤緯+40度から-65度にわたります)。
はくちょう、わし、いるか、くじゃく、インディアン、つる、さそり、ケンタウルス、みなみじゅうじ
ジョバンニは、華麗な星座絵に惹きつけられ、夢の中でこれらの星座を縫って旅しました。とすれば、ジョバンニが見た星座絵には、北天のみならず南天の星座も含まれていなければならないはずで、結論をいえば、そこには南北両天の星座 ―文字通り「空じゅうの星座」― が描かれていたと思います。
(長いので、ここで記事を割ります。)
ジョバンニが見た世界…大きな星座の図(4) ― 2013年02月10日 10時58分38秒
(本日は2連投です。前回の記事からお読みください。)
星図のパターンとしてよくあるのは、南北両天を左右に並べた形式です。
たとえば↓に掲げたのは、ドイツのゾイッター(Mattheus Seutter 1678-1756)の天球図、「Planisphaerium Coeleste」(1750)。
星図のパターンとしてよくあるのは、南北両天を左右に並べた形式です。
たとえば↓に掲げたのは、ドイツのゾイッター(Mattheus Seutter 1678-1756)の天球図、「Planisphaerium Coeleste」(1750)。
(アメリカの古地図専門店のページから借用。リンク先の画像をクリックすると、ものすごく大きく拡大できます。http://www.swaen.com/antique-map-of.php?id=20220)
サイズは55.7 x 48.7 cmとありますから、ほぼ新聞紙大。それなりに大きいですが、1枚の紙に両天を収めた分、前回述べたことからすると、やや小ぶりになるのはやむを得ません。
もうちょっと大きいものを探すと、たとえば↓のドッペルマイヤー(Johann Gabriel Doppelmayr 1671-1750)の南天図、「Hemisphaerium Coeli Australe」(1730)。
(これまたアメリカの古地図店のサイトから借用。http://www.raremaps.com/gallery/archivedetail/31558/ )
星図部分の直径だけで約45センチと、なかなか大判です。ドッペルマイヤーの星図帳には、同じ形式の北天図も含まれますから、この2枚を並べて額装すれば、ひとまずジョバンニが見た光景の再現としては十分でしょう。
★
しかし、「十分でしょう」と澄ましているだけではダメです。
この企画は、何といっても実際にその場面を再現することを目指しているので、私の手元に現物がないことには話になりません。
しかしながら、上のゾイッター天球図は売価3000ドル。下のドッペルマイヤーの南天図は売却済みのため価格不明ですが、ネット情報を見ると、やっぱりそれぐらいはするようです。南北両天揃えれば、さらにその倍。
ジョバンニと心中するつもりで、思い切ってローンを組めば買えなくもないのでしょうが、その間ずっとお粥を啜って暮らさなければなりません。たとえ天文古玩堂の主でも、そこまではしたくないので、もう少し現実味のあるところで算段することにしました。
(この項さらにつづく)
星と荒事…團十郎逝く ― 2013年02月11日 10時24分44秒
ジョバンニの話題は小休止。
★
十二代目・市川團十郎(以下、団十郎)、本年2月3日寂。享年66歳。
歌舞伎役者の彼が、天文趣味人であったことは、わりと知られているエピソードのようで、ウィキペディアにもチラッと書かれています。
団十郎さん…という呼び方は据わりが悪いので、ここでは敬称を略しますが、その団十郎が天文に目覚めたのは、小学生の頃の火星大接近がきっかけだそうです。調べてみると、これは昭和31年(1956)のことで、最接近は9月でした。ときに団十郎は小学4年生。もちろんまだ「団十郎」を名乗る前ですが、彼はすでに初舞台を済ませ、歴とした役者の一員でした。このとき彼は父親(十一代目団十郎)にせがんで、口径5センチの屈折望遠鏡を買ってもらい、以後天体観測に励むことになります。
翌年(1957)は宇宙時代の画期、スプートニク打ち上げの年。ライカ犬が宇宙に飛び立ち、西側世界に衝撃を与えたのはこの時のことです。さらに肉眼で観測できる彗星が2個出現(アランド=ローランド彗星、ムルコス彗星)し、こうした出来事にあおられて、団十郎少年の天文趣味はますます熱を帯びた…のだと想像します。
★
団十郎の訃とともにその天文趣味を耳にし、かつて読んだ雑誌の記事を思い出しました。それは2009年の世界天文年を記念して、雑誌「東京人」が8月増刊号として、三鷹の国立天文台特集を組んだ折りのものです。
その中で団十郎は、国立天文台を見学しながら、当時の台長・観山正見(みやましょうけん)氏と対談しています(名前から想像される通り、観山氏の実家はお寺だそうで、記事では団十郎と仏教的宇宙観の話題で盛り上がっています)。
実は、上で書いた団十郎と天文趣味の出会いのエピソードも、この対談記事が元になっているので、改めてご本人の言葉を引いておきましょう。
*************************
団十郎 小学生の小学生の頃に火星の大接近がありましてね。
ふだん父は物をあまり買ってくれなかったんですが、「望遠鏡が
欲しい」と言ったら「いいよ」と、口径五センチくらいの屈折望遠鏡を
買ってくれたんです。それを一生懸命覗いたら、火星もね、
赤っぽいものがけっこう大きく見えたんですよ。父も息子に
買わせて自分が覗きたかったんでしょう、望遠鏡を合わせると、
「どれどれ」なんて庭に出てきて見ていました。
ちょうど、ソ連のスプートニク1号、アメリカのエクスプローラ1号
という人工衛星が打ち上げられて、地上からでも見えると言われて
いた頃です。
観山 子ども時代から、今も天体観測を続けられているわけですね。
団十郎 ええ。月日が経って、また火星の接近があったので、
さらに大きな口径の望遠鏡を買ったんですが…以前に見た火星よりも
小さいんです。つまり性能がよくなって、ぼやけていたものが、
はっきり見えるようになったんですね(笑)。その代わり表面の模様は、
以前よりもずっとよく見えました。
それから日周運動で動く天体に合わせて星を追尾する赤道儀を
使いました。北極星のほうをめがけて垂直に立てて、誘導の望遠鏡を
ちょっとずらして、大変な思いをしながら、市販のカメラで月や土星の
写真を撮ったりしました。
*************************
団十郎 小学生の小学生の頃に火星の大接近がありましてね。
ふだん父は物をあまり買ってくれなかったんですが、「望遠鏡が
欲しい」と言ったら「いいよ」と、口径五センチくらいの屈折望遠鏡を
買ってくれたんです。それを一生懸命覗いたら、火星もね、
赤っぽいものがけっこう大きく見えたんですよ。父も息子に
買わせて自分が覗きたかったんでしょう、望遠鏡を合わせると、
「どれどれ」なんて庭に出てきて見ていました。
ちょうど、ソ連のスプートニク1号、アメリカのエクスプローラ1号
という人工衛星が打ち上げられて、地上からでも見えると言われて
いた頃です。
観山 子ども時代から、今も天体観測を続けられているわけですね。
団十郎 ええ。月日が経って、また火星の接近があったので、
さらに大きな口径の望遠鏡を買ったんですが…以前に見た火星よりも
小さいんです。つまり性能がよくなって、ぼやけていたものが、
はっきり見えるようになったんですね(笑)。その代わり表面の模様は、
以前よりもずっとよく見えました。
それから日周運動で動く天体に合わせて星を追尾する赤道儀を
使いました。北極星のほうをめがけて垂直に立てて、誘導の望遠鏡を
ちょっとずらして、大変な思いをしながら、市販のカメラで月や土星の
写真を撮ったりしました。
*************************
時代を考えると、かなり本格的な天文少年ですね。「月日が経って」というのは、以下の記事によれば、高校生のときに反射式望遠鏡を入手したことを指すようです。
■WEB25ロングインタビュー 「宇宙と歌舞伎は同じこと」
http://r25.yahoo.co.jp/interview/detail/?id=20080306-90003639-r25&order=125
この間、昭和36年(1961)には、ガガーリンが初有人宇宙飛行。同年、アメリカがアポロ計画を発表。さらに昭和38年(1963)には、初の女性宇宙飛行士、テレシコワが登場しています。国内では本田実・関勉両氏による彗星発見の報が続き、昭和35年には岡山天体物理観測所が、昭和37年には埼玉の堂平観測所が開所し、本格的な大型望遠鏡時代がやってきました。
(昭和39=1964年の「天文と気象」誌。特集は「夏休み天体観測と天体写真術」。)
荒事の家に生まれた団十郎ですが、当時はごく内省的な傾向を持つ少年だったように思われます。その生活環境が大きく変わったのは、昭和40年(1965)に、父である十一代目の団十郎を亡くしてからで、彼は人間としても役者としても大いに苦労したらしいですが、その間も宇宙への関心を失わなかったのは、あっぱれな天文趣味人だったと言うべきでしょう。
★
以下に「東京人」の記事から、彼の言葉をいくつか書き抜いておきます。
「荒事」という形態の演技にも、仏教的な宇宙観があります。六方(ろっぽう)は、東西南北、天地の方向を指し、それぞれの方向の宇宙の果てまで鳴り響く、堂々とした歩き方です。ほかにも見得や、陰陽という光と影の世界を体で表そうという宇宙観があります。生物独特の吸う・吐くという「息」などの要素を基軸にしています。
+
私は外の宇宙はもちろんですが、この人体の中の宇宙にも関心があるんです。キリスト教はどちらかというと、外、次の世界へという一方通行のように思いますが、外の宇宙、中の宇宙、輪廻など、荒事の舞台をつとめる土台として考えています。
+
歌舞伎で「無から有を生じ、有から無を生じる」という台詞があるんですが、理論的に言ったらおかしいですが、もしかしたら宇宙は、無から有が生じて、有から無が生じる世界であるとも考えられる。
+
この先、月でも惑星でも水があるとわかったなら、そこで生活できる可能性はぐんと高まるわけですから、宇宙への大航海時代ですよ。そして将来、歌舞伎が存在しえたならば、日本にこういう文化があることを宇宙でも紹介したいし、やってみたいなと思います。
+
私にとって宇宙は、美しさを感じさせるものです。科学の法則、踊りや人間の動作にしても、美しいものには真理があると思います。
+
(人間の身体の構成物質が星の中で作られたという話を受けて)
昔から亡くなった人はお星さまになったというのは、本当に言い得て妙ですね。
★
私は歌舞伎には疎いですが、天文趣味に心惹かれる者として、同時代を生きた先達が星に還る姿を、静かに見送りたいと思います。
石田五郎氏のこと (1) ― 2013年02月13日 00時53分47秒
雨の音を聞きながら風呂に入っていたら、途中からシャリシャリという音がまじり出し、どうやら雨がみぞれに変わったようです。冷たい滴が空から無性に降ってきます。
★
かなたに星に惹かれる歌舞伎役者あれば、こなたに歌舞伎に惹かれる天文家あり。
団十郎の天文趣味について書いていて、ふと思い出したのは故・石田五郎氏(1924-1992)のことです。
石田氏は岡山の天体物理観測所に長く勤務され(1969年以後は副所長)、その経験を洒脱な文章でまとめた『天文台日記』は、私の大のお気に入りの本で…ということは、以前書いた記憶があります(今も中公文庫BIBLIOに入っているので手軽に読めます)。
石田氏が「万年副所長」に甘んじたのは、学界の種々の事情があったのかもしれませんが、思うに予算と人事に消尽させられるトップよりは、氏の精神活動をより自由ならしめるには、かえって好都合だったのではないでしょうか(本当のところは分かりませんが)。
まこと石田氏は、研究者の枠に収まらぬ、幅の広い趣味人でした。
少年時代から野尻抱影に私淑し(中学1年の時に、4か月分の小遣いをためて、抱影の『星座神話』を買い込んだというエピソードがあります)、のちに直接親交を結ぶと、自然そこには師弟の関係が生まれ、後に石田氏は翁のことを「初代天文屋」と呼び、自らは「二世天文屋」を名乗るようになりました。豊かな知識を背景にした星のエッセイストとして、両者は師弟であり、畏友でもありました。
二人を結びつけたものは、星に寄せる思いは言うまでもありませんが、芝居(歌舞伎)好きという共通の要素があったことも大きかったようです。抱影は浜っ子、石田氏は江戸っ子(生家は上野の商家)で、ともに洒脱なことが大好きで、芝居好きもその延長だったのでしょう。
★
手元に、『天文屋 石田五郎さんを偲ぶ』という、ご友人たちが出した私家版の追悼文集があります。そこには「天文関係」、「出版関係」、「親族」といった寄稿者の区分と並んで、特に「歌舞伎関係」の一章が設けられています。
石田氏は十七代目の市村羽左衛門(2001年没)と昵懇の間柄で、岡山で羽左衛門と梅幸の芝居巡業があったときには、特に許されて黒衣(くろこ)姿で舞台袖に座ったそうですが、これは素人としては破格のことで、それだけ石田氏が芝居に入れ込んでいた証しでしょう。
(口絵頁より。左・黒衣姿の石田氏、右・市村羽左衛門)
また羽左衛門の息子、当代の市村萬次郎さんも根っからの天文好きで、岡山の天文台には巡業のたびごとに10回訪れたと文集にあります。その関係もあって石田氏と羽左衛門とは家族ぐるみの付き合いがあったということです。以下はその萬次郎氏の文章より。
「父〔=羽左衛門〕が芝居の質問に手紙で答えたのが切っ掛けでした。この出合いは、物理・天文好きの私としては願ってもないことでした。事実、歌舞伎の地方巡業で岡山へ行った時には、必ずといっていい程、鴨方の天文台へおじゃますることになりました。たとえ台風が来てて、どしゃぶりの雨となり、雷が落ちて停電になろうとも、ロウソクの明かりの下、星と芝居の話に花を咲かせました。
後に先生が人に紹介して下さる時に、「僕より星のことにくわしいよ」と冗談を言われましたが、「先生の方が私よりずっと、芝居のことにくわしいです」とこれは本気で答えました。実に細かに芝居のことを御存じでした。それは決して表面的に数多くのことを知っているということではなく、芝居のことが心から好きだったからこそ、自然と身についた知識であったと思います。」
雨の宵、天文学者と歌舞伎役者が、ろうそくの明かりを点して、夜通し星と芝居の話題で語り明かす…。何とも風情がありますが、「主」が石田氏でなければ、とてもこうはいかないでしょう。
★
いろいろ湧いて出る思いに誘われて、石田氏の短文集『天文屋渡世』(筑摩書房)を手に取って、以前は気付かなかったことにいくつか気づいたので、ちょっとメモしておきます。
(この項つづく)
石田五郎氏のこと(2) ― 2013年02月13日 22時26分16秒
石田五郎氏の『天文屋渡世』。
この本は昭和63年(1988)、筑摩から出ました。昭和20年代から60年代まで、石田氏があちこちの新聞・雑誌に書いたものを集めた文集です。
この本を再読して、改めて「へええ」と思ったことがいくつかあります。それらはいずれも野尻抱影に関することで、星そのものよりは、いくぶん人事寄りの話題です。
(1)『星恋』はかつて稀書であった。
抱影と山口誓子の句文集『星恋』は、今では古書検索サイトにいけばいつでも買うことができます。しかし、この本はかつて「幻の書」と呼ばれたらしいです。
「久しく幻の書といわれていた抱影・誓子の珠玉集『星恋』がこのほど復刊された。星座研究の野尻抱影と俳句の山口誓子とが星に対する思いのたけを競い合うように文字にしたもので、初版は昭和二十一年六月、鎌倉書房の刊行、用紙も造本も敗戦直後の粗末なものであったが、星好きの人々には希望となぐさめとを与えるこよなき贈り物となった。再版は昭和二十九年、中央公論社の新書版で、あまり世に騒がれずに姿を消した。両者とも古書展などで目にとまる機会はほとんどない。このたび『定本・星恋』として深夜叢書社から復刊されたのは慶賀にたえない。」(p.35)
そうと知ってみれば、本棚の隅に立っているこの本が、いっそう有難いものに見えますし、同時にネット時代になって、一部の古書が値崩れを起こしている理由もよく分かる気がします。
(2)石田氏と抱影とは3度しか会ったことがない。
初代と二世の「天文屋」である両者は、生前深い親交を結んだことは間違いありません。しかし、直接会ったことは生涯に3度しかないと聞いて、ちょっと驚きました。
上記『星恋』の誓子と抱影にいたっては、一度も顔を会わせぬまま、この名著を上梓したそうですが、星つながりというのは、なかなか常識では律しきれぬものがあります。
「星の大家の抱影先生にはじめて会ったのは昭和三十二年三月、東京渋谷の駅前に新築なった五島プラネタリウムの開館レセプションの折であった。大勢の人込みの中で科学博物館の村山定男氏から紹介され、おそるおそる名乗りをあげると、
「石田君テ、もう少しやせた人かと思った」これが私のきいた端正な老先生の第一声であった。当時、私が朝日新聞にかきつづけていたコラム「星の歳時記」の文章には目を通しておられるようで、二、三の感想をのべられた。
その後間もなく、日本放送のラジオの対談の相手にとよび出された。また私自身のプラネタリウムでの講演の時に出会い、生前お目にかかったのはこの三度きりである。やがて私は岡山県の山奥の観測所に赴任し、以後ハガキの文通がはじまり、昭和五十二年に亡くなられるまでに三百通を超えるハガキが岡山に届いている。」
(pp.198-99)
(3)抱影は足穂の小説を読みとおしたことがない。
足穂は抱影のまことに純なファンで、戦後、草下英明氏の引き合わせで一度だけ顔を合わせた際も、含羞からまともにやりとりできなかったといいます。抱影は抱影で、足穂のことを「高踏派」と呼んで、手に余るものを感じたらしいですが、その後日談として、石田氏は抱影の次のような私信を紹介しています。
「昭和五十二年十月三十日に御他界、奇しくもその五日前の十月二十五日に宇宙論の詩人稲垣足穂氏が死去しているが、「タルホ君は昔小宅を訪れ、漢代出土の白玉の杯でビールを飲ませたところ喜んでゐました。全集(?)が出た時も寄稿を頼んで来たが、小説を貰つても内容がややこしくて読み通したことがないので断りました。」(46・6・29付)。早足の抱影先生のこと故、御両所はあるいは六道の辻あたりで会われたかもしれない。」 (p.206)
どうも、最後まで足穂の片思いに終わった気配です。見ようによっては、微笑ましいエピソードと言えなくもないですが、抱影もつれないといえばつれない。
Among the Stars ― 2013年02月14日 06時25分40秒
人の縁、人の出会いとは不思議なものです。
そのひとつひとつが、すべて星のあいだで起きる物語。
今日もまた星の世界で会いましょう。
★
「写真は本文とは関係ありません」と書くべきところですが、それではそっけないので、簡単に書誌だけ挙げておきます。
■Agnes Giberne
Among the Stars, or Wonderful Things in the Sky.
Seely (London), 1887
310p.
アグネス・ギバーンは19世紀の女流天文作家。
その文体は「平明で、時に叙情的な傾きがあるが、豊富な天文学の基礎知識を伝えることには十分成功している」と評されます(アラン・チャップマン、『ビクトリア時代のアマチュア天文家』)。
この『 Among the Stars 』は、夢見がちの少年Ikon(アイコンと読むのか?)が、周囲の大人たちと会話しながら天文学の知識を身につけていくという体裁の、まさに上で評された通りの児童書です。
ジョバンニが見た世界…大きな星座の図(5) ― 2013年02月15日 22時00分56秒
さて、ぼちぼちジョバンニの記事を再開せねばなりませんが、今回の星座図の話題は、けっこう書くのに苦労しています。というのは、あまり深く考えずに書き出したため、途中でいろいろほころびが生じてしまったからです。
たとえば、「ジョバンニが見たのは、直径4~50cmクラスの円形星図、それも北天・南天を並べて描いたものだろう」と、もっともらしく書きましたが、実は記事を書く前に思い浮べていたのは、全然別のタイプの星図で、その写真も用意しておいたのですが、でも、いったん記事がそっちの方向に進みだすと、いまさら軌道修正もきかなくて、この先どうすればいいのか、途方に暮れています。
うーん…どうしようかなあ…と迷いつつ、時間稼ぎに、ふと思いついたことを書きます。
★
そもそもこの時計屋の主人は、いったいどんな人物だったのか?
以前も書いたように、『銀河鉄道の夜』の舞台が1912年と仮定すると、19世紀の記憶もまだ生々しい時期であり、「古星図」の定義や、その相場も現在とはずいぶん違うはずですが、それにしたって古星図が高い買い物であることに変わりはないでしょう。
古星図のまとまった書誌として最初のものは、1933年にイギリスで出た、Basil Brownの『Astronomical Atlases, Maps and Charts』という本だとされます。それ以前、「銀鉄」の時代には、古星図についての情報は、一部の碩学、古書肆、それに熱心なコレクターが独占していたと思われ、そんな時代に、古い天文学の香気に惹かれ、せっせと古い星図や望遠鏡を買いこんだ店主の心意気に、私は深く感ずるものがあります。
この店主、作品の表には一切出てきませんが、実はエライ人なんじゃないでしょうか。
★
…という時間稼ぎをしても間がもたないので、話を前に進めて、手元で時計屋のショーウィンドウを再現する方法をいくつか(無理やり)考えてみました。
その1つが、セラリウスの『大宇宙の調和 Harmonia Macrocosmica』(初版1660)を持ち出すことです。もちろん、原著ではなくファクシミリ版。南北両天を同時に、というのは難しいですが、適当なページをはらりと開いて立てておけば、雰囲気は出るかも…と考えました。
この大判の美しい星図帳は、現在すべての画像をオンラインで見られますが(例えばhttp://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cellarius1661)、紙でペラペラやりたい人のために、ファクシミリ版が作られています。
そのファクシミリ版も、過去に何度か作られていますが、いちばん新しいのが2006年にベルリンのCoron-Kindler社から出たものです。定価は1,698ユーロを謳っていますが、なぜか古書市場に新本が流れていて、その実売価格は200~300ユーロ。
表紙の高さは52センチ、幅は33センチですから、新聞紙をやや細身にしたぐらいの大きさがあります。実際手に取ると、「巨大」といってもいい本です。
(この項つづく)












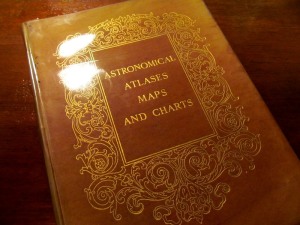


最近のコメント