好奇心の部屋で考えたこと ― 2025年11月23日 08時50分14秒
久しぶりの休日です。でも、昨日は40数年ぶりの高校の同窓会が東京の大手町であったので、のんびり寝ていたわけではありません。
その40数年ぶりで会った知人・友人の話を聞きながら、歳月の歩みと懐かしさを感じつつ、同時に記憶というのは不思議なものだな…とつくづく思いました。もちろん共通する記憶もあります。でも、相手に指摘されても、こちらはまるで覚えていないことや、あるいはその逆の例が想像以上に多くて、「事実」というもののあやふやさ、あるいはいっそ危うさを強く感じました。きっと民族の記憶とか一国の記憶とか称されるものも、事情は同じでしょう。
★
同窓会に出席する前、場所柄、東京駅前のインターメディアテクを再訪して、ここでもいろいろ物思いにふけっていました。
インターメディアテクは、アートに振れたり、学術に振れたりしながらも、「驚異の部屋」をその出自としていることは疑いようがなく、その一角に設けられた「ギメ・ルーム」には、今も「驚異の小部屋」の看板がかかっています。
でも、「果たしてここに驚異はあるのだろうか?」というのが、インターメディアテクに久しぶりに足を踏み入れてみての感想でした。どれもこれも古馴染みの品のような気がして、かつてのような圧倒されるワクワク感を感じられなかったからです。
ギメルームに置かれたソファに腰掛けながら、「驚異の反対語って何だろう?」と考えていました。「日常的」とか「陳腐」とか「familiar」とか、いろいろ考えているうちに、「それは確かに『驚異』が<新奇>や<珍奇>と同義ならばそうだろうけれど、でも『驚異』ってそんなものなのかな?」ということに思い当たりました。
「新奇性」というのはまさに水物で、それに接した瞬間からどんどん失われていき、いつのまにか影も形もなくなってしまいます。言葉は似ていますが、「珍奇性」の方は概してもう少し長もちします。「よそでは滅多に見られない品」は、似たような品が次々出てこない限り珍奇であり続けるからです。ただ見れば見るほどそこに既視感が生じて、陳腐化することはやはり避けがたいです。
「なるほど…」と思考は続きます。「たしかに日常性やfamiliarityは驚異の対義語ではないな。たとえ日常的で見慣れた存在でも、そこに驚異を感じる例はいくらでもあるからなあ」と。
結局、その場の結論は、「驚異とはモノの側にあるのではなく、モノに触発された自分の内部から湧いてくるものだ」という、わりと常識的なものでした。驚異の部屋(独 Wunderkammer)は、英語の「Chambers of Curiosities」を直訳して、ときに「好奇心の部屋」とも呼ばれます。上の論旨からすれば、「好奇心の部屋」の方がたぶん良い訳語ですね。好奇心はモノにあるわけではなく、純粋に見る側の問題ですから。
インターメディアテクに驚異を感じられないとしたら、それは私自身の好奇心がやせ細り、驚異生成能力が低下している証拠でしょう。
インターメディアテクにディスプレイされている骨格標本は、何も珍奇一辺倒ではありません。ヒキガエルにしろ、スズメにしろ、これ以上ないというぐらいの普通種です。でも、そこにあふれるような好奇心があれば、そうした普通種でも、とたんに驚異に満ちたものになるはずなのです。
★
以下、おまけ。
上のような結論をお土産に、ある意味いい気分で家路についたのですが、家で新聞を開いたら、下のような記事が目に付きました。
(中日新聞、2025年11月22日夕刊)
「京大 沖縄・奄美から持ち出し466体 遺骨リスト突如公開」
「沖縄差別 学知の植民地主義 今も」
「東大にも?有無答えず」
「沖縄差別 学知の植民地主義 今も」
「東大にも?有無答えず」
人類学の研究資料として、戦前の京大や東大の研究者が琉球・奄美で遺骨を採取し、大学に持ち帰ったことについて、返還運動が進められていることを報じる内容です。その東大側の関係者として名前の挙がっているのが、人類学者の鳥居龍蔵(1870-1953)で、その名はインターメディアテクでの展示でもしばしば目にします。
「あふれるような好奇心の発露」で、すべてが免責されるわけではありません。もちろん「権利」や「差別」が論点になったからといって、その前ですべての議論が無化するわけではありません。仮にそうなると、あたかも「不敬」の一語で天皇機関説が排撃されたような事態にもなりかねませんから。
要は常に思考を止めないことだと思います。
思考停止状態は好奇心から最も遠いものです。好奇心至上主義を唱え、それに疑問を感じないとしたら、それ自体好奇心の死を招きかねないと思います。
コメント
_ S.U ― 2025年11月23日 17時40分15秒
_ 玉青 ― 2025年11月24日 09時29分39秒
ルネサンス期の「元祖・驚異の部屋」の有力なアイテムは、大航海時代とともにもたらされた様々な異国の品々(人工物も自然物も)ですね。その根本にあるのは、「エキゾチシズム」であって、それは必ずしも「支配-被支配」の関係性を前提にしたものではなかったはずですが、残念ながらその後の博物館の歴史は、植民地主義や帝国主義的簒奪とともに歩むことになりました。その流れは20世紀前半まで色濃く続いたと思います。(私の子ども時代(S.Uさんもご同様でしょうが)、「土人」という言葉が普通に使われていたのは、その残滓だと思います。)
後発の日本も明治になってその隊列に伍したことが、そのまま今のインターメディアテクに接続しているわけで、インターメディアテク(すなわち東大)は、本来そのことに正面から向き合わないといけないはずですが、今に至るまでその視点は非常に弱いように見えます。
後発の日本も明治になってその隊列に伍したことが、そのまま今のインターメディアテクに接続しているわけで、インターメディアテク(すなわち東大)は、本来そのことに正面から向き合わないといけないはずですが、今に至るまでその視点は非常に弱いように見えます。
_ S.U ― 2025年11月24日 13時37分38秒
>その視点は非常に弱い
なるほど。これは、我々の世代を含む戦後昭和期の人たちの文化的不作為によるものかもしれませんね。おそらく、大学紛争の時代に解決されるべきことであったのでしょうが、そこまでは及ばなかったのがやむを得ないとしたら、我々の世代の責任といえそうに思います。もう、そういう経験的感覚自体がなくなったので、直接的なチャンスはおおむね過ぎてしまったように思います。
なるほど。これは、我々の世代を含む戦後昭和期の人たちの文化的不作為によるものかもしれませんね。おそらく、大学紛争の時代に解決されるべきことであったのでしょうが、そこまでは及ばなかったのがやむを得ないとしたら、我々の世代の責任といえそうに思います。もう、そういう経験的感覚自体がなくなったので、直接的なチャンスはおおむね過ぎてしまったように思います。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

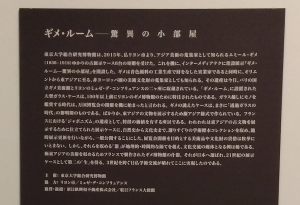



極めて個人的な主観ですが、もともとの驚異というのは、西洋の探検家がアフリカや南洋や極地を旅行して珍しいことを記録を書いたことではないでしょうか。それがお土産としての標本に反映されたとか。ただし、私の印象では、驚異とは、昭和時代にNHKテレビなどの輸入フィルムの「自然の驚異」というノンフィクションシリーズの記憶と繋がり、これが一般向けの意味だと思います。
でも、自然の驚異と言っても、その環境では、野生動物や植物の日常で、そこでは砂漠やらジャングルやら氷原やら嫌というほど続いているのですから、日常が驚異であってもぜんぜん支障がないわけで、今日では、日常も驚異に含められるようになっているのではないでしょうか。