人は彼女の法則に反抗するときといえども、それに服従する ― 2024年07月21日 08時37分58秒
昨日の名古屋の最高気温は35.2度。
そんな中で外仕事をしたら、年寄りに続いて、今度は自分が救急車のお世話になるかも…とは思いましたが、木を伐るのは休日しかできないので、身ごしらえをしてパチンパチンとやってました。しんどかったですが、これまで淀んでいた一角に日差しと風が入るようになり、少し気持ちが軽くなりました。
★
とはいえ、樹木の剪定というのは、たとえ園芸家や造園家がどう理屈をつけてみても、植物の世界の営みに、人間の都合や価値観を一方的に押し付けることに他ならず、いささか後ろめたい気持ちもまじります。(適正に管理された「健全な森」とか、管理の行き届かない「荒れた森」という言い回しにも、似たような感じを受けます。)
「庭」そのものが、そもそも人間が人間のために作ったものなので、そこでは万事人間が王様であり、人間の都合でやりたいようにやってもいいのだ…という理屈なのかもしれませんが、こうあからさまに書くと、いかにも傲慢な感じですね。
(植物は逆光で見るのがきれいだな…と思いますが、これも人間側の価値観でしょう)
そこにも自然のルールは働いているという意味で、庭は確かに小さな自然ですけれど、それ以上に、人がその自然のルールに抗い続ける場であり、人為の極とも言えます。
(人間によって維持されている小さな生態系)
★
まあ、庭木の枝を払ったぐらいで、「大自然に挑む人類の代表」みたいな顔をしなくてもいいのですが、そうとでも思わんと、この炎暑の中で庭仕事なんかとてもやれんぞ…と思ったのも事実です。
★
今日の記事のタイトルは、ゲーテの「自然についての断片」(1782)の一節から採りました。「彼女」とはもちろん自然のことです。
■出典:ARCHIVEプロジェクト
ゲーテ(著)・恒藤恭(訳)『自然についての断片(ほか6篇)』
ゲーテ(著)・恒藤恭(訳)『自然についての断片(ほか6篇)』
庭仕事と悟性 ― 2024年05月19日 16時15分30秒
アジサイの仲間である甘茶の花が咲き、山桜桃(ゆすらうめ)の実も少しずつ色づいてきました。この時期は植物がぐんぐん成長するので、ちょっと見ない間に庭の様子もずいぶん変わります。
それだけ庭仕事の忙しい時期で、殺伐とした最近のツイッター(X)でも、「庭仕事」で検索すると、日本中で庭仕事に励んでいる人たちの投稿がずらっと出てきて、しばし心がなごみます。私も狭い庭で汗を流すのが好きなので、大変だ大変だと口では言いながらも、それを十分楽しんでいます。
もちろん世の中には庭仕事が好きな人ばかりではありません。
親から相続した緑の濃い庭を、手入れが大変だという理由で、全面掘り起こしてコンクリートで固めた…という話も現に見聞きするので、そうした例を思えば、わが家の場合は庭にとっても、その主にとっても、幸せな関係だと言えると思います。
★
今から14年前、ヤフー知恵袋に某氏が投稿した質問【LINK】。
「長方形の面積についてですが、例えば長方形の周の長さを26cmとします。
縦11cm、横2cmとすると面積は、22平方cmとなります。
しかし同じ周の長さで、縦7cm、横6cmとすると面積は42平方cmとなります。
なぜ周の長さは、同じなのに比率を変えるだけで面積は変わるのでしょうか?
だれに聞いても答えられません。
だれか教えてください。」
縦11cm、横2cmとすると面積は、22平方cmとなります。
しかし同じ周の長さで、縦7cm、横6cmとすると面積は42平方cmとなります。
なぜ周の長さは、同じなのに比率を変えるだけで面積は変わるのでしょうか?
だれに聞いても答えられません。
だれか教えてください。」
そのベストアンサーはリンク先に書かれているので、興味のある方はご覧いただければと思います。
★
なんで唐突にこんな引用をしたかというと、わが家の庭仕事が(楽しいながらも)大変なのはなぜか?と考えたからです。
「庭仕事が大変だ」というと、「さぞお庭が広いのでしょうね」という反応をされる方もいると思うのですが、わが家の庭は言うまでもなく狭いです。しかし「長い」のです。
パースが簡単にとれるぐらい長くて、これはわが家が変形敷地、いわゆる旗竿地だからです。
狭いけれども長い…というのがこの場合味噌で、長ければ長いだけ、敷地境界沿いに植わっている植物も多くなり、それが多くの庭仕事を生んでいるわけです。ヤフー知恵袋が説く如く、周囲の長さが同じでも面積は異なる…つまり裏を返せば、同じ面積でも形状によって周囲の長さは大きく異なるのです。
(よく言えば「市中の山居」っぽい感じ)
★
余談に流れますが、この周囲の長さと面積に関連して、大変おもしろい論文を読みました。そもそも、人はなぜ上の知恵袋のような質問を発したくなるか?という点に関わるものです。
■西林克彦、「面積判断における周長の影響―その実態と原因―」
教育心理学研究 第36巻第2号(1988)、pp.120-128.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep1953/36/2/36_120/_pdf
教育心理学研究 第36巻第2号(1988)、pp.120-128.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep1953/36/2/36_120/_pdf
掲載誌名から分かる通り、教育心理学分野の論文です。その冒頭部より。
「ある図形の面積が、その周囲の長さ(周長)に影響されて誤判断されやすいことはよく知られている(銀林、1975)。とくに顕著 なのは周長が同じであると面積までが同一であるとみなされる傾向である。したがって小学校算数教科書に、その点に留意した記述が見られるものもある。細谷(1968)は、小学校2-4年生に周長を等しく保ちながら長方形を平行四辺形の形に押しつぶして面積の比較をさせ、各学年とも、面積は同じであって変わらないとする反応が過半数に達する結果を得たという。」
周長が等しければ面積も等しい…というのは、上の知恵袋で見たように、明らかに間違った考え方です。しかし小学生を被験者にして実験すると、そうした間違った考え方が2年生から4年生に至るまでずっと保持され続けている(つまりこの点では4年生も2年生と変わらない)という、不思議な結果を示しています。
著者・西林氏はこの点に焦点を当てて実験を重ね、その結論は以下のとおりです(太字は引用者)。
「周長の面積判断への影響は、面積概念の混乱や未成熟さに帰せられるものではないことは明らかである。それは保存の概念を経由して入り込んでくるのであり、成長し保存の概念を獲得したが故に誤るようになるのである。Bruner (Bruner et al., 1966) は、「成長によるエラー」を、「正確にいうなら、1つの表象システムと、いま1つの表象システムとの間に照応性や一致性をうちたてようとして、うまくゆかない最初の段階を示しているのである」として、表象システム間に限っているが、もっと一般化してよい概念だと思われる。」
つまり子供たちは成長につれて、見た目の変化に影響を受けない「保存」という概念を獲得し(これは高度に抽象的な概念です)、それを周長と面積の関係に不適切に応用してしまうため、結果的に誤った判断をしてしまうということです。ここで正しい判断を下すためには、さらにもう一段階成長を遂げる必要がありますが、次の段階にいけない人も多いことはヤフー知恵袋が証明しています。
★
上のことは人間理性のありようを考えるとき、きわめて示唆に富んだ話だと思いました。ひょっとして、人間がこの先いかに進化しようとも、神の視点からすれば同じようなことが繰り返されるのかもしれません。
庭仕事の合間にそんなことを考えました。
朝の教訓 ― 2024年04月04日 05時57分46秒
音楽家から天文学者に転身したウィリアム・ハーシェル(1738-1822)。
彼が天王星を発見したゆかりの地である、イングランド西部の町バースは、英国ハーシェル協会の本部があるところで、地元のバース王立文学科学協会(BRLSI)とも協力して、ハーシェル関連のイベントがなかなか盛んです(彼の旧居は現在ハーシェル天文博物館として公開されています)。
(Googleストリートビューで見るバースの町とBRLSIの建物(正面左手))
そのBRLSIが主催して、ウィリアムの息子で同じく天文学者のジョン・ハーシェル(1792-1871)に関する講演会があると聞き、たまには勉強しようと思ってオンラインで参加することにしました。
(同講演会の案内ページより。晩年のジョン)
しかし参加はしたものの、何だか様子がおかしい。
入室した時点で話がえらく進んでいて、おや?と思う間もなく「結論 Conclusion」というパワポのスライドが出て、そのまま講演は終わってしまったのでした。
★
「指折り数えても時間は合っているはずなのに、おかしいなあ」
…というのを読んで、「ははーん」と思われた方もいるでしょう。
そうです、私はやっぱり時間を間違えていたのです。
イギリスでは先月末からサマータイムが始まっていて、日本との時差は今は9時間ではなく、8時間で計算しないといけないのでした。イベント慣れしている人には何でもないことかもしれませんが、ごくたまに発心する程度の人間にはちょっと難易度が高かったです。
参加チケットを事前購入して、がんばって早起きまでしたのに、何たることか。
まさに時間どろぼうに遭った気分ですが、まあここで一度失敗しておけば、次回からはたぶん大丈夫でしょう。
一瞬先は闇 ― 2024年03月31日 17時49分00秒
怒涛の3月が終わり、明日からはいよいよ4月。
今年の年度替わりは、例年以上に心身を痛めつけられました。それでも、とりあえず年度を越すことができてホッとしています。落語に出てくる昔の大みそかは、庶民にとって今とは桁違いの大イベントだったらしく、借金取りとの手に汗握る?攻防が面白おかしく言い伝えられていますけれど、今の世の年度替わりも、一部の人間にはちょっと似たところがあります。とにかく無茶でも何でも、事務の形を整えねばならないので、日本中でずいぶん珍妙なやり繰り算段があったことでしょう。
★
そんな山場を越えて、今日はメダカの水を替えたり、小庭の草をむしったり、のんびり過ごしていました。ブログもそろりと再開せねばなりませんが、気ままなブログといえど、しばらく書いてないと、書き方を忘れるもんですね。まずはリハビリ代わりの気楽な話題から。
★
「ぼくの保険会社だって?もちろんニューイングランド生命保険に決まってるじゃないか。でも何でそんなこと聞くんだい?」
蝶ネクタイでワイン片手に望遠鏡を覗きこむ2人のアマチュア天文家。
実にお洒落な二人ですが、なんで保険会社が話題になっているかというと…
雑誌「タイム」1969年10月24日号に掲載された、ニューイングランド生命保険の広告イラストです。描き手は諧謔味のあるイラストで、「プレイボーイ」や「ザ・ニューヨーカー」の誌面も飾った Rowland B. Wilson(1930-2005)。思わずクスリとする絵ですが、今だとちょっと難しい表現かもしれませんね。まあ画題はいささかブラックですが、この青い空と白い星の取り合わせはいかにも美しいです。
現実のアマチュア天文家が、当時こんな小粋なムードを漂わせていたかどうか。実際こんないでたちの人もいたかもしれませんが、でもこの広告の裏面(この広告は雑誌の表紙の真裏に載っています)を見ると、小粋でも気楽でもなく、「うーん」と大きくうならされます。
(「WHAT IF WE JUST PULL OUT? このまま撤退したらどうなるのか?」)
市松模様になっているのは、ニクソン大統領とベトナム戦争の惨禍、そしてアメリカ国内の反戦運動の高まりです。当時はアメリカのみならず、日本も熱い政治の時代で、この年はそこにおっかぶさるようにアポロの月着陸があり、翌年には大阪万博(Expo’70)を控え、今にして思えば、かなり騒然とした時代でした。まあ、私はまだ幼児だったのでリアルな記憶は乏しいですが、でも半世紀あまりを経て、人間のふるまいはあまり変わらんもんだなあ…とつくづく思います。
夜の梅 ― 2024年02月14日 17時01分30秒
今日は職場を早めに辞し、手前の駅で下りて、夕暮れの町をぶらぶら散歩しながら帰ってきました。
表通りを避けて、裏道を選んで通ると、こんなにもあちこちに梅の木が植わっていたのかと、改めて驚かされます。紅梅、白梅、しだれ梅―。やはり日本人は梅が好きですね。そして咲き誇る梅の下を通れば、強い香りが鼻をうち、そこが桜とは異なる梅ならではの魅力。家に帰りつく頃には日も沈み、茜の残る西の空に細い月がかかっているのを見て、嗚呼!と思ったのでした。
★
というのは、実は昨日の出来事で、冒頭の「今日」とは「昨日」のことです。
そんなことで私の風流心は大いに満たされましたが、そういえば何かそんな詩があったなあ…と家で検索したら、それは菅原道真の『月夜見梅花』という漢詩でした。
月耀如晴雪 月の耀(かがや)くは晴れたる雪の如し
梅花似照星 梅花は照れる星に似たり
可憐金鏡転 憐れむべし 金鏡の転じて
庭上玉房馨 庭上に玉房の馨(かお)れることを
転句の「金鏡」は月、結句の「玉房」は咲き誇る梅の花のことです。
雪景色と見まごうばかりの明月と、満天の星のような梅の花。
天上を月がめぐり、庭に満開の梅が香っている光景を前にして、道真もまたただ一言「憐れむべし」(ああ、なんと見事な!)とだけ言って、口をつぐむのです。
満天の星を空の花畑にたとえることはあっても、梅の花を空の星にたとえるのは、中国に典拠があるのかどうか、もしこれが道真の創意とすれば、彼の鋭い感性に改めて驚かされます。そういわれてみれば、闇に浮かぶ五弁の小さな白い花は、たしかに星を連想させます。
となると、さしずめ天の川はどこまでも続く梅林を遠目に眺めているのに他ならず、想像するだに馥郁と芳香が漂ってきます。いずれにしても、道真が梅とともに星を愛したことは間違いないでしょう。
そう考えると、菅原道真が「天神さま」であり、「天満(そらみつ)大自在天神」の神号にちなんで、その神社を「天満宮」と呼ぶことも意味ありげに感じられますし、梅を愛した道真にちなんで、各地の天満宮が梅紋を神紋とする中にあって、京都の北野天満宮では特に「星梅鉢」を用いるというのも、実に素敵な暗合のように思えてきます。
(左が「星梅鉢」。これは星紋の一種である「六ツ星」(右)のバリエーションとも見られます)
(こちらは舌でめでる風流、とらやの「夜の梅」)
地上の星、天上の星 ― 2024年01月08日 13時22分44秒
先日、年末に注文した品が届きました。今年の初荷です。
それは現代の技術と感覚で作られた、1枚の美しい星図…のはずでした。
でも、輸送用チューブの中から出てきたのはマドンナのセクシーポスターで、「げげ!」と思いました。

このポスターは彼女のアルバム「Bedtime Stories」のリリース(1994)に合わせて作られたものらしく、まあマドンナもスターには違いないでしょうが、私が求めたのは別の星です。
もちろん売り手の方にはすぐ連絡を取りました。
その結果判明したのは、これは売り手ではなく、eBayインターナショナル・サービスセンターのミスだということです。eBayで買い物をされた方はご承知でしょうが、eBayの海外発送はかなり複雑で、途中いくつも業者が介在して荷物の受け渡しを行うのですが、その過程でラベルの貼り間違いが生じた…というのが、今回の出来事の原因でした。聞いてみれば「なるほどそんなこともあるのか…」と思いますが、これまでにない経験だったのでビックリしました。(ただし、その後のeBayの対応は早かったです。クレームを入れると、すぐに返金処理をしてくれました。この点は先日のPayPalと違うところです。)
それにしても、三者間の取り違えでない限り、私の星図はマドンナの到来を待ち望む人の元に届いたはずで、その人もずいぶん驚いたことでしょう。
大事小事、この正月は驚くことが多いです。
遊ぶ子供の声聞けば ― 2023年12月31日 10時23分00秒
いよいよ大晦日。
なんだかんだ言いながら、今年もいろいろなモノを手元に引き寄せて、当人は大いにご満悦です。(ついさっきも、「あ、いいな」と思った古絵葉書をまとめて注文しました。)
まあ、他人から見れば愚かしいことかもしれませんが、家族がちょっと迷惑に感じるぐらいで、世の中に特に害をなすことでもないし、愚は愚でも、わりと質(たち)のいい愚ではないか…と考えます(それこそ愚考かもしれませんが)。
★
昨日、買い物帰りに公園の脇を通ったら、遠目に満開の白い花木が見えました。「おや?冬桜かな?」と近づくと、それは桜でも花でもなく、ナンキンハゼの白い実でした。
ナンキンハゼは、人間を喜ばせようと思ってそうしているわけではないにしろ、樹木の冬の装いとしては至極上々の部で、自然というのは実に美しいものだと思いました。そして木の下で元気に遊ぶ子どもたちを見れば、人間のうちにも確かな美質があると直感できるのです。
★
今年一年「天文古玩」にお付き合いいただき、ありがとうございました。
2024年が、世界と人々にとってどうか良き年となりますように。
星夜独酌 ― 2023年12月28日 16時08分29秒
先月、11月21日の記事の一部を再掲します。
-----------(引用ここから)----------
ワインと12星座で検索したら、こんな記事がありました。
■What’s Your Sign? Matching Wine To Your Zodiac
(あなたの星座は?ご自分の星座にあったワインを)
(あなたの星座は?ご自分の星座にあったワインを)
もちろん真面目に読まれるべき内容でもないですが、ワイン選びに迷っている人には、案外こんなちょっとした耳打ちが有効みたいです。
私は射手座で、もうじき誕生日がくるんですが、「柔軟で、知的で、放浪心のある射手座のあなたには、フランスのカベルネ・フラン種や、イタリアのサンジョヴェーゼ種を使った赤ワインがお勧めだ」みたいなことが書かれていました(意訳)。
ウィキペディアによれば、サンジョヴェーゼの名はラテン語の sangius(血液)と Joves(ジュピター)の合成語で、ぶどう液の鮮やかな濃い赤に由来する由。そして誕生日当日(11月25日)には、木星と月齢12の月が大接近する天体ショーがあるそうなので、これはいよいよトスカーナワインを傾けねばならないことになるやもしれません。(まあ、ジュピターの血色をした赤ワインを傾けるのは、赤いちゃんちゃんこを着せられるよりも、確かにはるかに気が利いているでしょう。)
-----------(引用ここまで)----------
で、私は自分の言葉に励まされて、いそいそとサンジョヴェーゼのワインを買いに行ったものの、せっかくの思い付きも、風邪に阻まれて実行には至りませんでした。まあ、月と木星のドラマは寝床から観察できましたが、酒を口にするような気分と体調ではなかったからです。
(自分で自分の長寿を祝って、亀のラベルのワインを選びました)
そのボトルを、ようやく1か月後のクリスマスに開けることができました。
強靱なユピテルの血潮を口にしたことで、私ももうしばらくはこの世にとどまることができそうです。
★
そして今日は仕事納め。
せっかくだから正月向けのお酒も用意しようと、名古屋の星ヶ丘三越で「星美人」というのを奮発して買ってきました。「蓬莱泉」で有名な関谷酒造が、星ヶ丘店のために特に醸(かも)したものです。
こう書くと、なんだか酒ばかり呷(あお)っているようですが、正直、今年一年はだいぶ疲れがひどく、盃を手にすることが多かったです。
★
中国星座には、酒屋の軒にひるがえる旗に見立てた「酒星(しゅせい)」という洒落た星座があるそうで、李白はそれを踏まえて「天、若し酒を愛さざれば、酒星天に在らず」とうそぶきました。
まこと心を慰めるのには、盃を手に星をふり仰ぐにしくはありません。
疲れる話 ― 2023年12月10日 05時55分36秒
師走ということもあって、なんだかんだ忙しいです。
当分は「月月火水木金金」で、昨日も今日も出勤です。
★
その一方で、ずっと心に刺さっていたトゲが抜けて、ちょっとホッとしました。
それは9月に購入した本をめぐって、売り主であるスウェーデンの古書店主と揉めていた件で、このことは以前もチラッと書いた気がします。
購入したのは戦前の古い地図帳です。
古書店側の記載によれば、その地図帳には50枚の図版が含まれているはずでした。でも、届いた現物には36枚の図版しか含まれておらず、しかも図版が切り取られたとか、そういうわけではなくて、インデックス頁を見ても、最初から36枚の図しか含まれていないのでした。
そのことを先方に連絡した私は、これまでの経験から当然、「それは当方の手違いなので、すぐに返品してください。もちろん返送の送料は当方が負担します」とか、「ただちに返金しますので、お送りした本はそちらで処分をお願いします」とかの返答を期待しました。
でも、先方の回答はこちらの予想の斜め上を行くものでした。
「当方の記述はスウェーデン王立図書館のデータベースを転記したものです。それによれば、その地図帳の当該年の版には50枚の図版を含むものしか存在しません。どうぞご自分でデータベースをチェックしてみてください。残念ながら私にあなたの問題を解決できるとは思えません。」
「え!?」と思いました。スウェーデン王立図書館はたしかに大したものかもしれませんけれど、問題はそんなことではなく、50枚の図版を含むものとして販売された本に、36枚の図版しか含まれていなかったことが問題なのですよ…と、関連ページの写真も添えて、繰り返し説明したのですが、先方は頑として意見を変えず、さらには明らかに無礼な言葉まで投げてきました。これは埒が明かないと、PayPalに苦情を申し立てたのが10月のことです。
その裁定が延びに延びて、結局時間切れで、いったんは泣き寝入りでケース終了になるという嬉しくないオマケまで付いてきました。「そんな馬鹿な」と、再度不服申立をして、ようやくPayPalから返金の連絡があったのが昨日のことです。(時間がかかったのは、返品した本の受取りを先方が拒否し、現物がずっとスウェーデンの郵便局に塩漬けになっていたためです。その後、現物は再度送り返され、今は私の手元にあります。)
★
なんだかこう書いていても疲れます。
冤罪事件やスラップ訴訟に巻き込まれた人は、こんな気分なんでしょうかね。全体として釈然としない感じは残りますが、しかし全ては終わったのです。
重い目で月と木星を見る ― 2023年11月26日 19時38分45秒
風邪でずっと寝込んでいました。
でも月と木星の大接近は、私が風邪を引いたからといって待ってはくれませんから、昨夜は床の中から、この天体ショーを眺めていました。せっかくだから…と、だるい身体を起こして双眼鏡を持ってくると、双眼鏡の視野の中でも両者は仲睦まじく寄り添っていて、実にうるわしい光景です。ここでキャノンご自慢のスタビライザー機能をオンにすると、像はピタリと静止し、針でつついたような木星の月たちも見えてきます。地球の月、木星、そして木星の月たち。それを眺めている自分もまた、地球という惑星に乗って、今も宇宙の中を旅しているんだなあ…と今更ながら実感されました。と同時に、木星の4大衛星と地球の月は似たりよったりの大きさですから、両者を見比べることで、木星までの距離も直感されたのでした。
(いつも手の中で転がしている、木星の表面によく似た瑪瑙)
★
それにしても今回の風邪。金曜日の朝にいきなり39.4度まで熱がガッと上がり、これはてっきり…と思って近医に行ったんですが、インフルもコロナも検査結果は陰性でした。「まあ、ふつうの風邪でしょう」と言われて、薬をもらって帰ってきたものの、ふつうの風邪でこんなふうに突然高熱が出るものなのか?そこがちょっと不審です。
ひょっとして、コロナの後遺症で、免疫系がおかしくなってしまったのか…と、風邪で気弱になっているせいもありますが、そんな想像が頭をよぎり、不安に駆られます。













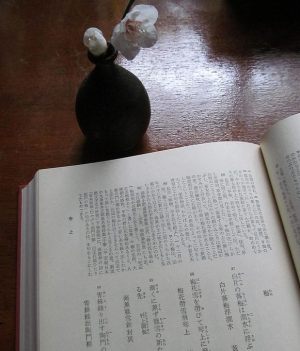











最近のコメント