十年一日、一日千秋 ― 2025年01月18日 17時21分13秒
今日の記事のおまけ。
同じ人間が書いているので当たり前ですが、自分の書いていることは、ちょっとカッコよくいえば変奏曲、有体にいえば十年一日、なんだかずっと同じことを言ってる気がします。今回そう思ったのは、以下の過去記事に目が留まったからです。
■無限の時、夢幻の出会い
13年前の自分は、ある男女の切ないストーリーに触発されて、「たとえ3日が60年に伸びても、別れの苦しみは変わらないし、反対に60年分の思いを3日間に詰め込むことだってできないわけではない」と書きました。さらに虫たちの生と死に「ヒトの有限性に根ざす、心の中の「根源的寂しさ」」を感じ、「永遠は一瞬であり、一瞬は永遠である」と、もっともらしく他人の褌を借りています。
まあ、表現の細部は違えど、今日の記事で言いたかったことは、13年前の自分もしんみり感じていたことです。「成長がないなあ…」と思いますが、しかし「ヒトの有限性」は私にとってこの13年間でいっそう切実なものとなったし、話の力点も男女の機微から寂滅為楽へと移ったことを思えば、やっぱりそこに幾分「成長」もあるわけです。
我ながら頼もしいような、心配なような。
いずれにしても13年という歳月は、面貌ばかりでなく、心にもしわを刻むのに十分な時間です。
笑う月 ― 2025年01月19日 10時56分26秒
男女の機微…というと、こんな絵葉書はどうでしょうか。
(ロンドンのCarlton Publishing社製、オフセット印刷。消印は下述のとおり1916年)
「At the End of the Honeymoon ハネムーンの終わりに」
悄然とする男と、さめざめと泣く女。
互いに背を向けて、いかにも穏やかでない雰囲気です。
それをにんまりと見ているお月様は、事の一部始終を空から見ていたからこそ、にんまりしているのでしょうが、何だか意地の悪そうな笑顔ですね。
★
おそらく甘いハネムーンの期間に、性格の不一致が露呈したか、いわゆる「性の不一致」があったということなんでしょうけれど、後者にしても単なるEDの問題に限らず、当時の世相を考えると、同性に惹かれる男性が、世間体を気にして女性と結婚するのはありふれた光景でしたから(逆もあったと思います)、そこにいろいろ悲劇があったはずで、そうなると、なかなかにんまり笑うどころではありません。
★
ところで「ハネムーン、蜜月」というのは、文字通り「結婚後の甘い時期」を指すわけですが、各種の語源解説ページを見ると、そこにはさらに「愛情は満ちれば欠ける月のようなものだ」という含意があるらしく、さもありなんと思います。まあ、満ちては欠け、欠けては満ちるの繰り返しの中で、徐々に安定した関係を築いていくのが理想なのでしょう。これは男女の関係に限らないことです。
★
冒頭の絵葉書に戻って、こんな皮肉な画題の絵葉書を、いったい誰がどんな目的で差し出したのか気になりました。
裏面を見ると、1916年4月16日にロッテルダムから、市内に住む未婚女性(Mejuffer.)に当てて送られたようですが、文面もオランダ語のため、気になる内容は残念ながら判読不能。ひょっとして、花嫁が同性の友人に新婚旅行の首尾を伝えたもの?
月下の恋人 ― 2025年01月20日 19時15分43秒
月と男女を描いた絵葉書は世間に無数にあって、本気で集めだすと、それだけで一大コレクションができることでしょう。
昔から月はロマンチックなものとされているので、月影さやけき晩に男女が睦言を交わすというのがデフォルトの設定で、下のような絵葉書がたぶん本来の姿でしょう。
(1922年のイギリスの消印が押された絵葉書。ロンドン南郊SevenoaksのJ. Salmon社製。オフセット印刷)
あるいは、下のようなべたべたした絵柄とか。
(20世紀初頭のドイツ製絵葉書。エンボス加工を施した多色石版。輸出仕様なので、消印はアメリカ国内になっています)
でも、この辺はなかなか一筋縄ではいかなくて、上の絵葉書にしても、しなだれかかる男と、それを抱きとめる女という描写に、伝統的な男女の役割規範から逸脱したものを感じる方が多いと思いますが、たしかにここには、何か皮肉な意図がこめられている気配があるのです。
それは月の表情からも感じ取れて、この歯をむき出しにした月は、男女の相愛を単に微笑ましく見守っているだけではないんじゃないか…という気がします。そのことは下の絵葉書になると一層明瞭で、この顔つきは決してカップルを祝福しているそれではないですよね。
(版元不明。20世紀初頭の多色石版刷)
「Mooning」という語は、一般的にはクレヨンしんちゃんみたいに、相手をコケにするために公衆の面前でお尻を丸出しにする行為を指すらしいですが、ここではそれとは違って、「Mooning over」の意味だと思います。「Mooning over」とは、「恋しい人のことを思ってぼんやり無駄な時間を過ごすこと」の意だとネットにはありました。そして「His Ownest Own!」というのは、「ぜったいに彼だけのもの!」という意味のようです。
要するにこの二人はデレデレの極致にあるわけですが、お月様はそれを突き放すような皮肉な笑いを浮かべて眺めています。たぶん、お月様は月の下で結ばれ、月の下で破局を迎えた無数のカップルを飽きるほど見ているので、いきおいそんな表情になるのでしょう。
その辺が昨日の絵葉書の描写とつながってくるわけです。
憎らしい月 ― 2025年01月25日 10時15分11秒
記事の間が空きましたが、前回の続きです。
「月下の男女」の画題は、考えてみるとなかなか興味深いものがあって、男女の方はさておくとして、ここに登場するいわゆる「月の男(The man in the moon)」の描かれ方が、大いに気になります。
もう少し類例を見てみます。
(エンボス加工を施した多色石版。ニューヨークのA. S. Meeker社製)
こちらは月下の接吻。
1908年9月、バージニア州ノーフォークの James 君が Miss May に当てたもの。「O Glee! Be Sweet to me Kid.(おお、愛しの君よ!どうぞ僕に優しくしておくれ)」と、James 君はだいぶ気持ちが高ぶっているようですが、しかしこの月の表情はなかなかどうして、一筋縄ではいきそうにありません。
★
(1898年、ウィーンで創業したKohn 兄弟社(Brüder Kohn Wien I;BKWI)製の石版絵葉書。ちなみに「Wien I」は、創業地の「ウィーン一番区」の意味【LINK】)
こちらはペーパームーンの趣向によるコミック絵葉書で、ベルギーのリールの消印(1904年付け)が押されています。あて先は「Mademoiselle Elise」で、差出し人は表面に書かれた Peeraer 氏でしょう(見慣れぬ姓ですが、ベルギー由来の名前だそうです)。
ペーパームーンとは「張りぼての月」のことで、当時、夜空の書き割りの前でペーパームーンに坐って記念写真を撮ることが欧米で大層流行ったと聞きます。
絵葉書の画面では、せっかくいいムードなのに、突如“破局”が訪れて男女はびっくり、お月様もポロポロ泣いています。でもこれは、その身を傷つけられて痛がってるだけのようでもあり、そうなるとこのお月様にしても、カップルに対して同情的というよりも、単に迷惑千万と思っているに過ぎないことになります。
★
20世紀初頭とおぼしいアメリカ製の多色石版絵葉書。
このお月様が、地上のカップルを見守る表情もちょっと微妙です。
この絵葉書は仕掛け絵葉書になっていて、「夢が叶うかどうか、月にきいてごらん」という、その答は…
これはおめでたい画題といえますが、反面、甘いロマンスの時期はすぐに終わり、やがて現実に立ち向かうことになるぞ…という戒めのようでもあります。月の微妙な表情も、それを言わんとしているんじゃないでしょうか。
★
無論、西洋の人だって、月は美しいもの、ロマンチックなものと感じるからこそ、「月下の男女」という画題が成立するのでしょうけれど、絵葉書に登場する月は、妙に訳知り顔だったり、皮肉屋だったり、酷薄だったり、それ自体が一つの「型」になっている気配があります。
東洋情緒の月は、ひたすら皓々(こうこう)として、いろいろな思いを託す存在ではあっても、月そのものが何かよこしまな性格を持っているとは、思いもよらぬことでしょう。西行法師が詠んだ「嘆けとて月やはものを思はする かこち顔なるわが涙かな」という歌にしても、月を見て嘆いているのは自分自身であって、月そのものが嘆かわしい存在であるとは、一言も言っていないわけです
まあ、平安歌人と20世紀初頭のコミック絵葉書を比べて何か言うのも無理がありますが、でもこういう「憎らしい月」、「くせ者めいた月」は、日本の文芸の伝統には絶えて無い気がします。江戸の古川柳には、何かそんな“うがち”の句があるかと思いきや、『古川柳名句選』を見ても、見つかりませんでした、
★
日本における唯一の…とまでは言いませんが、顕著な例外が(そして西洋のお月様以上にくせ者感の強いのが)、稲垣足穂の『一千一秒物語』に出てくるお月様で、足穂が幼少期に見た「ステッドラー鉛筆の三日月」【LINK】から、独力でああいうイメージを構築したのだとしたら、彼の鋭い直感とイマジネーションは、大いに称揚されるべきです。
積んどけ! ― 2025年01月26日 09時34分21秒
先日、Facebook上の「Vintage Astronomy Books」というグループに加えてもらったという話をしました。で、その過去記事を見ていて、「天文古書とは関係ないが、興味深い内容だ」として、以下の記事が紹介されているのを目にしました。
(日本人が「ツンドク」と呼ぶこの習慣は、永続的な効用をもたらし得る)
BIG THINK、2022年12月22日掲載
BIG THINK、2022年12月22日掲載
いきなり「tsundoku 積ん読」が出てきて面喰いますが、積ん読の功徳を大いに力説する内容で、私自身、根っからの積ん読派なので、少なからず勇気づけられました。
★
著者の主張をかいつまんで言えば、未読の本に囲まれて暮らすことは、自分の無知を自覚することにつながり、無知を自覚することは、自分の知っていることを自覚するよりもはるかに価値がある…ということです。
我々はみな多かれ少なかれ無知であり、無知それ自体を恥じ入る必要はありません。万巻の蔵書を誇るウンベルト・エーコだって、その全てを読んだわけではないし、人間の能力を考えれば、そもそもそれは物理的に不可能です。
未読の本の背表紙は、いかに広大な無知の領域が我々を取り巻いているか――著者の書斎の例でいえば、暗号学、羽毛の進化、イタリアの民間伝承、第三帝国における悪しき薬物使用、昆虫食とは何か等々――を教えてくれます。そして未知の対象があると知るからこそ、我々は新たな読書体験を求め続けるのです。
この「読まれざる本の山」を、著者は統計学者であるNassim Nicholas Talebの造語を借りて、「アンチライブラリー(反図書館)」と呼びます。しかし記事の後半では、アンチライブラリーの語感があまりよろしくないのと(『ダヴィンチ・コード』の著者、ダン・ブラウンの小説にでも出てきそうだ、と著者は言います)、普通の図書館だって多くの本が読まれないままなのだから、あえてアンチと呼ぶ必然性が薄いという理由で、日本語の「積ん読」に軍配を上げます。積ん読もまた「読書」の一形態だ…という点に魅力を感じたのでしょう。
★
著者はライターとして記事を量産している人なので、この記事にしても、どこまで本気で書いているのか、何となく常識の逆張りで人目を引こうという意図や、そもそも「こたつ記事」っぽい感じが無くもないですが、でもこうやって堂々と言ってもらうと、家族に対しても、「どうだ、Dickinson氏曰く…」と胸を張れるような気がします。
まあ、これも人は自分に都合のよい情報だけを取り入れがちという、「確証バイアス」の例に過ぎないといえば、その通りでしょうけれど…。
3億3300万円 ― 2025年01月29日 19時10分29秒
昨年の暮れに、天文学史の大家・故オーウェン・ギンガリッチ博士(1930-2023)の旧蔵書の売り立てがあるという記事を書きました。
■碩学の書斎から
クリスティーズが主催するこのオークションが昨日、無事終了。
出品されたギンガリッチ博士ゆかりの品74点(古典籍73冊とアストロラーベ1点)のうち、10点は入札がなく、オークション不成立でしたが、それ以外は概ね好調で、落札額の合計額は214万8400ドル、1ドル155円で換算すると、3億3300万円ちょっきりという、まことに天晴れな数字になりました。
これはクリスティーズが事前に公表していた、74点の最高評価額(評価額は、例えば「5千ドル~8千ドル」のように幅を持たせてあります)の合計である、160万5500ドルをも大きく上回る結果で、手数料で稼ぐクリスティーズにとってはホクホクでしょう。
もちろん私には無縁の世界の出来事ですし、他人の懐具合を気にするのも下世話な話ですが、やっぱりこういうのは気になるもので、今回の結果を改めてレビューしておきます。その盛会ぶりを知ることは、ギンガリッチ博士の遺徳を偲ぶよすがともなるでしょう。
以下、タイトルと書誌はクリスティーズによる表示のままで、落札額には日本円(1ドル155円で換算)も添えておきます。タイトルから元ページにリンクを張ったので、本の詳細はそちらでご確認ください。
<落札額ベスト10>
47,800ドル(740万円)
37,800ドル(585万円)
★
ちなみに、クリスティーズの最高評価額を大きく超えて、意外な高値を呼んだのは、
最高評価額2,500ドルのところ、5.54倍の13,860ドルで落札された
Mechanism of the Heavens, inscribed (Mary Somerville, 1831)や、同じく5万ドルのところ、3.53倍の176,400ドルで落札された、Stellarum Fixarum Catologus Britannicus (John Flamsteed, 1712-1716)〔これは高額落札の第3位に既出〕、あるいは同じく3,000ドルのところ、3.36倍の10,080ドルで落札された
★
これまたちなみに、19~20世紀に作られた旅行客用のお土産品らしいアストロラーベは、最高評価額6,000ドルのところ、10,800ドル(167万円)とかなりの健闘です。
★
これらの高価な品々を落札したのが誰かはまったく分かりません。
もちろん個人コレクターもいるんでしょうけれど、多くは名のある博物館とか図書館とかに収まることになるんでしょうか。こういうものは当然お金のあるところに吸い寄せられるので、以前記事にした上海天文館あたりにひょっこり登場する可能性もあるかな…と想像しています。
■ある天文コレクションの芽吹き
ギンガリッチ氏の書斎へ ― 2025年01月31日 12時36分46秒
(前回のつづき)
去年の暮れに書いた記事の末尾で、自分は「古典籍でなくてもいいので、ギンガリッチ氏の蔵書票が貼られた旧蔵書が1冊手に入れば、私は氏の書斎に足を踏み入れたも同然ではなかろうか…」と書き、そのための算段をしているとも書きました。
有言実行、その後、ギンガリッチ氏の地元・マサチューセッツの古書店で1冊の本を見つけ、さっそく送ってもらいました。
■Paul Kunitzsch,
『Arabische Sternnamen in Europa(ヨーロッパにおけるアラビア語星名)』.
Otto Harrassowitz (Wiesebaden, Germany), 1959. 240p.
『Arabische Sternnamen in Europa(ヨーロッパにおけるアラビア語星名)』.
Otto Harrassowitz (Wiesebaden, Germany), 1959. 240p.
パウル・クーニチュ氏(1930-2020)は、オーウェン・ギンガリッチ氏(1930-2023)に劣らぬ碩学で、生れた年も同じなら、長命を保ったことも同じです。…といっても、私は無知なので、恥ずかしながらクーニチュ博士のことを知らずにいたのですが、ウィキペディアの該当項目を走り読みしただけでも、氏は相当すごい人であることが伝わってきます。
氏はアラビア学というか、アラビアの知識・学問が中世を通じてヨーロッパにどう流入したかが専門で、その初期の代表作が、氏がまだ20代のとき世に問うた『ヨーロッパにおけるアラビア語星名』です。これは氏の博士論文を元に、それを発展させたものだそうで、氏の本領はアラビア科学の中でも、特に天文学だったことが分かります。
★
手元の一冊には、著者の献辞があります。
「オーウェン・ギンガリッチに敬意を表して。ディブナー会議でのわれわれ二人の出会いの折に。1998年11月8日 パウル・クーニチュ」
ディブナー会議というのは、MITにかつてあった「ディブナー科学技術史研究所」(1992年開設、2006年閉鎖)が主催した会議のひとつだと思いますが、このときクーニチュ氏も来米し、両雄は(ひょっとしたら初めて)顔を合わせたのでしょう。
ただ、いくら代表作とはいえ、クーニチュ氏が40年近く前の自著を献呈するのは変ですから、おそらくクーニチュ氏の来訪を知ったギンガリッチ氏が、自分の書棚からこの本を持参し、記念のメッセージを頼んだ…ということではないでしょうか。クーニチュ氏はメッセージの中で、ギンガリッチ氏を敬称抜きの「呼び捨て」にしていますから、仮に初対面だったにしても、両者は旧知の親しい間柄だったと想像します。
その場面を想像すると、まさに「英雄は英雄を知る」を地で行く感があります。
★
そして問題の蔵書票が以下です。
クリスティーズのオークションで見た、繊細な青緑の蔵書票(↓)でなかったのは残念ですが、これはギンガリッチ氏がもっと若い頃に使っていた蔵書票かもしれません。
ギンガリッチ氏の書斎の空気をまとった存在として、また両大家の友情と学識をしのぶよすがとして、これは又とない宝である…と自分としては思っています。このドイツ語の本を読みこなすのは相当大変でしょうが、スマホの自動翻訳の精度も上がっているし、文明の力を借りれば、あながち宝の持ち腐れにはならないもしれません。
(本書の内容イメージ。「アルデバラン」の項より)
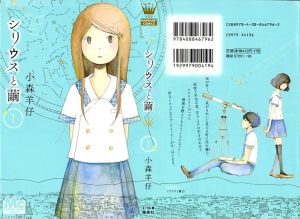




































最近のコメント