色絵誕生(5)…カテゴリー縦覧「印刷技術」編 ― 2015年08月02日 09時24分15秒
ずっと単眼鏡を覗いているので、目の調子がおかしいです。
網膜剥離になると嫌なので、この話題もそろそろ収束させます。
網膜剥離になると嫌なので、この話題もそろそろ収束させます。
読書百遍じゃありませんが、最初はさっぱり分からなかった印刷のことも、何度か本を読んでいるうちに、薄紙をはぐように、徐々に分かってきました。
★
この続き物の最初に戻って、「インゼル文庫」の図版にもう一度立ち向かいます。
最初に、私なりの結論を述べておくと、あそこで取り上げた4冊の本は、戦後に版行されたものも含め、「3色分解のプロセス平版+オフセット印刷」によって刷られたものは1冊もなく、いずれも石版によって刷られたものだと思います。
そのこと自体は、図版を拡大すれば簡単に分かります。
たとえば、上の本は1967年に出た本ですが、その複雑な色合いも、75倍のポケット顕微鏡で覗けば、たちどころに赤・青・黄―より正確にはマゼンタ・シアン・黄色―の3色のドットの集合でできていることが分かります(※)。
(※ただし、実際には墨版を加えて4色、さらに淡緋色や淡藍色を加えて、6~7版の重ね刷りとすることも多い由。)
(手元の安いスキャナでは最高1200dpiでしかスキャンできません。75倍に拡大すると、上の画像よりもさらにドットが大きく、くっきり見えます。なお、上の画像には部分的に円環模様の連なりが見えますが、これはドットが一定の条件で並んだ時、仮現的に現れるもので、実体的な模様ではありません。いわばモアレ干渉縞のようなものです)。
逆に言うと、ポケット顕微鏡で覗いても、そこに3色ドットが見えなければ、それは3色分解印刷ではないと自信を持って言うことができ(手元の本を片っ端から眺めて確認しました)、インゼル文庫の挿絵は、いずれも<非・3色分解製版>によっていることが分かります。
しかし、インゼル文庫の挿絵も、拡大するといろいろドットが見えます。
「じゃあ、あれは何なのか?」ということが問題になりますが、石版の製版方法を確認しながら、その謎を順々に見てみます。
「じゃあ、あれは何なのか?」ということが問題になりますが、石版の製版方法を確認しながら、その謎を順々に見てみます。
★
まず、第1回の最初に登場した蝶の画像。
(画像再掲)
その凄さを見るために、別の画像も見てみます。
(上の部分拡大)
当たり前の話ですが、印刷物とその刷版は同寸同大です。
つまり、この図とぴったり同じものを、その細かい毛の1本1本に至るまで、製版師(石版画家)は、手作業で版面に描き込んだわけです。おそらく拡大鏡を使い、持てる技術のすべてを傾けて制作にあたったのでしょう。
つまり、この図とぴったり同じものを、その細かい毛の1本1本に至るまで、製版師(石版画家)は、手作業で版面に描き込んだわけです。おそらく拡大鏡を使い、持てる技術のすべてを傾けて制作にあたったのでしょう。
そして色版ですが、朱色の部分を見ると分かるように、その色合いの濃淡は、細かい点の粗密によって表現されています。さらに目を凝らすと、青い模様も、黄色い羽も、その他の色も同様の表現をとっていることが分かります。これは恐らく細密な砂目石版と、手で描き込んだ点描(黙描)の併用によるものと推測します。
★
石版画の土台となる石版石は、製版に先立って、粗さの異なる金剛砂を使って表面を研磨し、さらに砥石でツルツルになるまで磨き上げてから用いるのが基本です。上の蝶の図も、シャープな画線が必要な、毛や輪郭線の部分(墨版)は、そうした石を用いていると思われます。
一方、濃淡表現が必要な色版には、目の細かい金剛砂を撒いた上から他の石版石でこすって一様な凹凸を付けた(「砂目を立てる」といいます)石版石を使います。その上から製版用のクレヨンで描画すると、筆圧に応じて濃淡のある版ができる仕組みです。
★
参考として、「印刷製版技術講座」から上記のことに関連する記述を抜き書きします。
■写真応用のH・Bプロセスが実用されるまでは、平版はすべて描き版(かきはん)によって、多色原稿を多年の修練をへた平版画家が、頭のなかで色を分解し、その原稿中に含まれている黄色なり赤色なりを石版石の面に描出して、1色ごとに描き別けて行ったものである。したがってうす黄色、中黄、濃い黄色というように段階をつけて行くから一つの原稿をまとめるためには十数色も色をかけることになる。(4巻、p.56)
■写真応用のH・Bプロセスが実用されるまでは、平版はすべて描き版(かきはん)によって、多色原稿を多年の修練をへた平版画家が、頭のなかで色を分解し、その原稿中に含まれている黄色なり赤色なりを石版石の面に描出して、1色ごとに描き別けて行ったものである。したがってうす黄色、中黄、濃い黄色というように段階をつけて行くから一つの原稿をまとめるためには十数色も色をかけることになる。(4巻、p.56)
■クレオン、鉛筆画のような濃淡のあるものを石版に製版するときには、前述のように砂目石版を使用する。このような砂目石版を製版するにはクレオンと称する脂肪性材料を使用する。クレオンの組成は、解き墨とほぼ同様である。クレオンは多量の脂肪を含有し、図画の精粗に応じて硬さの違ったものを用いる。〔…〕使用のときはその一端をけずり、クレオンの挟みにはめて石面に描画する。(4巻、p.12)
■そのほか磨き石版面に細いペンで細点を打ちながら点の大小によって濃淡を描き出したりする点ボツ、すなわち黙描製版などが高級色刷石版(これをクロモ石版という)に応用された。このように石版石の表面に細点を一つずつ打って行くことは、非常に技術を要し黙ポツの技術者となるには相当の年月を要した。(4巻、p.3)
■そのほか磨き石版面に細いペンで細点を打ちながら点の大小によって濃淡を描き出したりする点ボツ、すなわち黙描製版などが高級色刷石版(これをクロモ石版という)に応用された。このように石版石の表面に細点を一つずつ打って行くことは、非常に技術を要し黙ポツの技術者となるには相当の年月を要した。(4巻、p.3)
★
原図を与えられた製版師が、経験に基づき必要な色数を判断し、その色ごとに繊細な版をすべて手作業で作り、それらを寸分の狂いもなく重ねて刷り上げる…まったく気の遠くなるような作業です。
ともあれ最初の印象どおり、この蝶の図には、当時最高の石版技術が投入されていることは間違いなく、今ではとてもこれと同じものを作ることはできないでしょう。
★
つづいて、鉱物画を見てみます。
(画像再掲)
こちらについても、別の画像を見てみます。
(部分拡大①)
(部分拡大②)
どの図も共通して、絵にシャドーを付けて立体感を出すために、平面的な色版の上に黒い網目をかけています。さらに一番下の図(トルコ石)では、黒以外にブルーも網目で濃淡を表現しているのが分かります。
この網目は、いわゆるオフセットの網版ではないのか?
…というのが、私の中で大きな疑問でした。
…というのが、私の中で大きな疑問でした。
しかし、これも石版の技法の一種で、この網目は今でいう「スクリーントーン」のようなフィルムを手貼りしたものです。(それに対して網版は、ガラス板にダイヤモンド針で細い線を一面に刻んだ「網目スクリーン」を通して画像を撮影し、それを版面に転写することで作られます。)
これも上掲書に関連記述があったので、転記しておきます。
■石版に淡調をつくるには石版用フィルムが用いられる。
石版フィルムは、木框に張ったゼラチン透明膜(ときにはセルロイド膜)より成り、膜の表面に凸状の細い平行線、網点網目またはその他の地紋を有し、これらの表面に転写インキを着け石版石面に伏せて、フィルム網の裏面から圧力を加えて、石版に転写すると、そこに網線や網点の描出ができる。米英ではこれをベンデー製版法、ドイツではタンギール製版法と呼んでいる。(4巻、p.15)
石版フィルムは、木框に張ったゼラチン透明膜(ときにはセルロイド膜)より成り、膜の表面に凸状の細い平行線、網点網目またはその他の地紋を有し、これらの表面に転写インキを着け石版石面に伏せて、フィルム網の裏面から圧力を加えて、石版に転写すると、そこに網線や網点の描出ができる。米英ではこれをベンデー製版法、ドイツではタンギール製版法と呼んでいる。(4巻、p.15)
こうした技法がなぜ生まれたかといえば、蝶の図のような工芸的製版は、やはり時間的にも、経済的にも大変だったからです。
■このように石版石の表面に細点を一つずつ打って行くことは、非常に技術を要し黙ポツの技術者となるには相当の年月を要した。そこで一般の商業印刷用として黙描製版をもっと能率的にやるために、フィルム製版(別名ベンディフィルム製版)が行われるようになった。(4巻、p.3)
しかし、能率とともに失われるものもあることは、蝶と鉱物の図を比べれば、自ずと明らかで、繊細さという点で両者の懸隔は大きいです。
以下、具体的な作業についても抜書きしておきます。
■フィルムを用いて必要な部分に網線や網点をつくり出すとき不用の部分はあらかじめアラビアゴム液をぬっておおっておく。
フィルム製版をするには、フィルムの取付け枠装置や、フィルムの裏面から圧力を加えて転写するためのメノウ製スタンプ、小型ゴムローラーなどがあり、また網点のフィルムの場合には裏から加える圧力の大小によって網点の大小を作り出すことができる。(4巻、pp.15-16)
フィルム製版をするには、フィルムの取付け枠装置や、フィルムの裏面から圧力を加えて転写するためのメノウ製スタンプ、小型ゴムローラーなどがあり、また網点のフィルムの場合には裏から加える圧力の大小によって網点の大小を作り出すことができる。(4巻、pp.15-16)
★
ここまで見てくれば、鳥の巣の図の正体も明瞭です。
(画像再掲)
この卵と巣の部分も、要は描き版とフィルム製版の併用であり、オリーブ色と浅葱色の部分を見ると、フィルムの網点を手描きの点描によって補っていることも分かります。
★
問題はキノコの図です。
(画像再掲)
ここに見える円環状の模様は、明らかに鉱物や鳥の図とは異質に感じられ、そこに写真製版が応用されているのではないか…と最初は思いました。
しかし、75倍に拡大して観察すると、この円環模様も細かいドットの配列が生み出した仮現的なものに過ぎないことが分かります。要は使われている網点が小さく、密なために、鉱物や鳥の図とは、一見違った印象を生んでいるのでした。
ちなみに鳥の図でも、鳥の赤茶の羽の部分には、円環状のパターンが浮かんでいるのが分かります。
(画像再掲)
(部分拡大)
参考に別のキノコの図も見てみます。
(部分拡大)
褐色のキノコの傘も、緑の草も、ドットの隙間にも色が差されているのが見てとれます。この図が、平面的な色版と網目版の重ね刷りである証拠です。
また輪郭線の部分はドットではなく、連続線で描かれています。
そして、この図はあらゆる色が単色で表現されており(使う色の数だけ版を用意したわけです)、全体が三原色のドットに還元されるプロセス平版とは、根本的に違うものであることが明らかです。
以上のような特徴は、(網点の細かさを除き)すべて鉱物や鳥の図と共通するものですから、やはりこれも石版に分類できるのでしょう。(ひょっとしたら、版面は石版ではなく、金属版かもしれませんが、いずれにしても旧来の平版技法に拠っていることは確かです)。
(次回、網版と三原色分解の歴史的なことをメモ書きして、この項完結の予定)








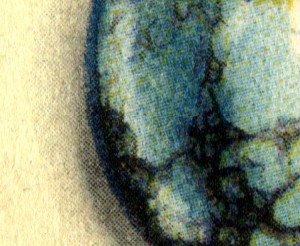






最近のコメント