ジョドレルバンクの話 ― 2025年08月17日 17時35分49秒
ブラック博士の本の話(8月10日付)の最後で、イギリスのジョドレルバンクの電波望遠鏡のことがチラッと出ました。そこから話を続けます。
★
ときに、ジョドレルバンクの知名度って、どれぐらいあるんでしょう?
もちろんその筋の人は知っているんでしょうが、たとえば私の家族に聞いても(まだ聞いてませんが)、「何それ?」となることは容易に予想できます。
ジョドレルバンクは、巨大な電波望遠鏡の立つ場所であり、望遠鏡自体の代名詞でもあります。2019年には世界遺産に登録され、日本はともかく、地元イギリスでは非常に有名な存在だと聞きます。
私が最初にジョドレルバンクに興味を覚えたのは、『ビクトリア時代のアマチュア天文家』(産業図書)の末尾に、ジョドレルバンクが登場したからです。それによると、ジョドレルバンクが完成した1957年は、後にBBCの長寿人気番組となったパトリック・ムーアの「The Sky at Night」の放送開始年であり、アラン・ローラン彗星が話題になった年です。こうした出来事を追い風に、イギリスのアマチュア天文活動は、戦前にもまさる勢いで復活し、発展を遂げたのです(日本製の廉価な天体望遠鏡がその発展に寄与したという記述も、私には他人事と思えませんでした)。
★
ジョドレルバンクはとにかく巨大です。アンテナの直径は76メートル、片や日本を代表する野辺山の45mm波電波望遠鏡は直径45メートルですから、並ぶと大体下の写真ぐらい違うはずです(あくまでもイメージです。正確な比較画像ではありません)。
(左:ジョドレルバンク、右:野辺山)
(ジョドレルバンクの場所)
ジョドレルバンクの歴史は、同観測基地のサイトに簡潔に述べられています。
そして上のページと同名の本が、かつて出版されたことがあります。
■Bernard Lovell
『The Story of Jodrell Bank』
Oxford University Press, 1968.
『The Story of Jodrell Bank』
Oxford University Press, 1968.
著者のバーナード・ラヴェルは、正式な名乗りをサー・アルフレッド・チャールズ・バーナード・ラヴェル(Sir Alfred Charles Bernard Lovell、1913-2012)といい、ジョドレルバンクを一から作り上げた電波天文学者です。したがってジョドレルバンクの電波望遠鏡も、彼の名をとって「ラヴェル望遠鏡」というのが、その正式な名称です。
(上掲書より。左はラヴェル、右はソ連の天文学者アラ・マセヴィッチ、1960年)
(手元の本には著者の献辞が入っています。「To Dr Keller, on the occasion of his visit to Jodrell Bank 14 November 1970 Barnard Lovell」。ラヴェルはかなり奔放な字を書く人ですね。なおケラー博士は未詳)
★
例によって、私はラヴェルのこの本も買っただけで満足して、積ん読のままになっていました。それをこの機会にパラパラしてみたわけですが、そこで強烈な印象を受けたのは、この本にしょっちゅう「お金の話」が出てくることです。
章題だけ見ても「最初の財政的危機」に始まり、「25万ポンドの負債」とか、「財務省と公会計委員会」とか、「財務問題解決に向けて」とかいった具合。私は勘違いしていたのですが、ジョドレルバンクは国費を投入した事業ではなく、ラヴェルの熱誠に支えられえた、文字通り徒手空拳のプロジェクトで、一部の熱心なサポーターがいたおかげで、ようやく日の目を見た存在だったのです。
(上掲書より。Papas画、ガーディアン紙掲載の一コマ漫画)
しかし、イギリスの人々はラヴェルの壮挙を支持しました。上の絵はラヴェルを皮肉るものではなく、むしろ三軍には気前よく予算を配分するのに、ジョドレルバンクは放置している政府を批判する趣旨の絵です。
★
瀕死のジョドレルバンクが突如息を吹き返したのは、当時の宇宙開発競争のおかげです。ジョドレルバンクの電波望遠鏡を使えば、人工天体の位置を正確に観測追尾できることが証明され、途端に「有用の長物」となったからです。そして上記のような大衆の支持もあり、ついにジョドレルバンクはイギリスの誇りとされるまでになったのでした。
まあ、人工天体の件はジョドレルバンク建設の本来の目的では全然なかったので、偶然の賜物といえばそうですが、「天は自ら助くる者を助く」で、ここはラヴェルの熱意が天に通じたのだと考えたいです。
★
(上掲書見返しより)
Jodrell Bank、すなわち「ジョドレルの丘」とは、エドワード黒太子とともに百年戦争を戦った弓兵、William Jauderellの名に由来し、かつてその所領だった場所だそうです。ラヴェル望遠鏡は、古の弓の射手よろしく、今後もその地で天空をにらみ、パラボラの弧を構え続けることでしょう。
パサチョフ博士の夏休み ― 2025年07月26日 09時46分45秒
ジェイ・パサチョフ(Jay Myron Pasachoff 、1943 –2022)という人がいます。
主に太陽と惑星大気の研究で知られた天文学者です。ハーバードで学んだ後、マサチューセッツのウィリアムズ・カレッジに籍を置きながら、サバティカルを利用して各地の大学や天文台で研究生活を送り、また天文教育にも情熱的で、多くの教科書を著した…というのは主にWikipediaの同氏の項目の受け売りですが、そこには彼がルネッサンス期以降の絵画における日食描写の分析といった、いわば「天文美術史」的研究にも手を染めていたことが書かれており、その関心の幅広さを知ることができます。
そのパサチョフ博士の書斎に置かれていたであろう、かわいい品を見つけました。
(台座の長辺は約18cm)
望遠鏡を操作する女性をかたどったオブジェで、その銘板に博士の名前があります。
アメリカで1959年以来続いている「サマー・サイエンス・プログラム(SSP)」という教育プログラムがありますが、その2004年の開講時に、博士がゲスト講師として招かれた際、記念品として博士に贈られたものです。
SSPは、アメリカ内外から集まった優秀な高校生が、5週間の共同生活を送りながら、第一線の研究者をはじめ、大学院生や学部生のサポートを受けつつ、専門的な研究を体験するプログラムです。研究や講義の合間には、各種のレクリエーションも用意されており、ここで共に学んだ仲間とは一生の友情がはぐくまれる…と聞くと、自分もそんな体験がしてみたかったなあと、羨ましい気がします。(プログラムについていく能力があれば、の話ですが。)
★
ときに、この小像のテーマになっている望遠鏡は何だ?ということですが、これはWikipediaの「Summer Science Program」の項に掲載されているのと同じものです。

昔はこの画像がSSPのシンボルであり、ロゴでもあったようですが、現在のSSP Internationalの公式サイトからは消えています。
たぶん…ですが、最近になってプログラムの内容が天文学にとどまらず、生物学や化学分野にまで広がったこと、そして開催地も南カリフォルニアのハイスクールを間借りする形から、全米各地の大学キャンパスを使った大規模なものに変わったことから、SSPのシンボルとして、最早そぐわなくなったからだろうと想像します。
以前のSSPの様子が、「Sky & Telescope」の2001年3月号にリポートされており、この望遠鏡も写真に写り込んでいます。それによれば、この望遠鏡は最初カリフォルニア州オーハイのサッチャー・スクールに置かれ、その後近くのベサントヒル・スクール(旧称ハッピーバレー ・スクール)に移設された、口径7インチのツァイス製アストログラフ(=写真撮影専用望遠鏡)で、ガイド用の屈折望遠鏡を同架しています。SSPの参加者はこれで小惑星を撮影し、位置測定と軌道計算をするのが定番だったようです。
★
アメリカも最近は貧乏くさい話が増えてきましたが、こういう物心伴う豊かさは、多様性を当然のものとして受け入れる度量の広さとともに、失ってほしくないものです。
(ちなみに、望遠鏡の操作者が女子学生として造形されているのは、1969年以来女性に門戸を開放してきたSSPの矜持でもあり、開明さの表明でもあるのでしょう。)
1896年、アマースト大学日食観測隊の思い出(1) ― 2025年06月29日 14時29分10秒
先に1936年の北海道日食の話題を取り上げ、その40年前、1896年にも北海道で日食があったことに触れました。
1896年というと、来年でちょうど130年。日本はまだ明治の半ばで、「ゴールデンカムイ」の舞台よりも、さらに10年余り先行する時代です。西暦でいっても何せ19世紀のことですから、思えばずいぶん昔の話です。
★
そんな昔、手つかずの大自然が広がる北海道を、アメリカの日食観測隊が訪れました。天文学者のデイヴィッド・トッド(David Peck Todd、1855-1939)率いるアマースト大学(マサチューセッツ州)の一行です。
(日食遠征後の1903年に建設されたアマースト大学天文台内部とアルヴァン・クラーク製18インチ(46cm)屈折望遠鏡。1908年、同地で投函された絵葉書)
(葉書の文面によれば、望遠鏡と一緒に写っているのがトッド教授で、隣はおそらく夫人のメイベル(Mabel Loomis Todd、1856-1932))
(同天文台の外観。同じく1900年代初頭の絵葉書)
★
このアマースト隊を偲ぶ品が手元にあるので、それを紹介しようと思うのですが、まずはアマースト隊来日の背景と概要を述べておきます。
(この項、ゆっくりと続きます)
星を近づけた先人たち…反射望遠鏡とプラネタリウムの黎明期 ― 2025年04月06日 13時01分37秒
何だかぼんやりと過ごしているときに、ハッとするメールをいただきました。
メールの主は、「中村要とクック25cm望遠鏡」のブログ主であり、戦前~戦後の日本の望遠鏡史や天文趣味史の先達であるdouble_clusterさんです。そこには、現在、京都産業大学・神山天文台で開催中の或る展示会のお知らせが記されていました。
■企画展「西村製作所と中村要~反射望遠鏡にかけた夢~」
○日程: 2025年3月15日(土)~6月20日(金) 月~金曜日 9:00~16:30
○場所: 京都産業大学神山天文台(京産大キャンパス内)
○料金: 無料・予約不要
以下、公式サイトより。
「20世紀初頭、アメリカやイギリスで鏡を使った望遠鏡(反射望遠鏡)が作られていく中、ガラス鏡の反射望遠鏡製造技術を日本に持ち帰った山崎正光、その技術を日本に広めた中村 要、そして中村 要と協働し日本で初めて、ガラス鏡の反射望遠鏡を製作・販売することになる京都の理化学機器メーカー 西村製作所。
企画展「西村製作所と中村要~反射望遠鏡にかけた夢~」では、2026年に100周年を迎える反射式望遠鏡の歴史を取り上げ、どのようにして国産の反射望遠鏡が作られたのか、人と人との繋がりや当時の技術者たちの天文学や望遠鏡に対する情熱が形になるまでの軌跡を紹介します。」
企画展「西村製作所と中村要~反射望遠鏡にかけた夢~」では、2026年に100周年を迎える反射式望遠鏡の歴史を取り上げ、どのようにして国産の反射望遠鏡が作られたのか、人と人との繋がりや当時の技術者たちの天文学や望遠鏡に対する情熱が形になるまでの軌跡を紹介します。」
…と、これだけでも興味深いのですが、会期中の特別企画として来る4月19日(土)に、以下の特別講演会が予定されている由。
■企画展関連講演会(プラネタリウム100周年記念事業公認企画)
「日本の天文普及の黎明-西村氏・江上氏・金子氏の時代-」
○日時: 2025年4月19日(土) 13:00~18:30
○開催方法: 対面とオンラインのハイブリッド開催
○対面会場: 京都産業大学 12号館5階 12502教室
○参加費: 無料
内容の詳細は公式ページをご覧いただきたいですが、西村製作所の初代社長・西村繁次郎(1910-1992)、戦後間もない時期に「江上式プラネタリウム」を開発した江上賢三(1920-1997)、同じく「金子式プラネタリウム」の開発者である金子功(1918-2009)の三氏の事績に焦点を当てながら、日本製プラネタリウムの草創期と、それが天文教育に及ぼした影響を振り返る…という内容のようです。
当日は上記特別講演に先立ち、本展を企画された神山天文台学芸員の青木優美香氏による基調講演とギャラリートークが、また講演会終了後には、希望者による天体観望会も予定されています。
天文古玩的にこれは見逃せない内容ですし、あんまりぼんやりして、このまま人事不省に陥ってもよくないので、4月19日当日は、企画展の参観を兼ねて会場に足を運ぶことにしました。関心のある方はぜひご一緒しましょう(特別講演の参加は予約制です)。
リンゴと望遠鏡 ― 2024年12月21日 07時22分13秒
もうじきクリスマスですね。
12月25日に降誕したのは、もちろんイエス・キリストですが、かのアイザック・ニュートン卿も、1642年の12月25日の生まれだそうです。もっとも、この日付はユリウス暦のそれで、グレゴリオ暦に直すと1643年1月4日だそうですが、イギリスは当時まだグレゴリオ暦の導入前で、イエス様だってグレゴリオ暦は使ってなかったのですから、まあ両者は同じ誕生日といっていいでしょう。
★
(名刺サイズよりちょっと大きい64×104mm)
上は1900年前後に刷られたクロモリトグラフの宣伝用広告カード。
広告主は、アメリカ東部のロードアイランド州でケータリング業(パーティ用配食サービス)を営んでいた、「L. A. Tillinghast」というお店です。
(裏面は白紙)
単にかわいい絵柄だな…と思って買ったんですが、その時の販売ページを見直したら、売り手であるバーモント州の紙モノ専門業者は、かなりこだわった紹介の仕方をしており、私も何だかひどく絵柄が気になりだしました。
「L. A. ティリングハーストは、ケータリング業者と書かれているが、この種の宣伝カードではあまり見かけない業種だ。リンゴ(?)の左側に「ソーダ」の文字があるが、どういう意味だろう?飲み物のことを言ってるなら、アップルソーダのことか?」
1900年前後というと、1892年にアメリカでボトルの王冠が発明され、炭酸水の輸送の便が生まれたことで、ソーダ水飲料が巷で大いに流行り出したころ…という背景がありそうです。
「もしこの絵がリンゴだとして、それが天文学といったいどう関係するのか?ひょっとして1890年代の市民の目には、この絵の意味するものが明瞭だったのかもしれないが、私の目にはもはやその意味がわからない。」
なるほど、アメリカの人にも分からないんですから、日本人の目にはいっそうわけが分かりません。
「この天文学者の服装は、魔法使いか道化師のもの?もし彼がリンゴを眺めているのだとしたら、いったいなんのために?カードにそう書かれているわけではないが、「〔ソーダが〕何よりも大事(apple of his eye)」ということだろうか。」
最後の一文、英語には「apple of one’s eye」という言い回しがあって、”My cat is the apple of my eye.”「うちの猫は目に入れても痛くない存在だ」のように使うそうで、そういわれると確かにそんな気もしてきます。
とはいえ、リンゴと天文学者といえば、誰でもニュートンの故事を真っ先に思い浮かべるでしょうし、地球と引っぱり合う存在である天体は、いわば「巨大なリンゴ」であって、それを小さな天文学者が望遠鏡で覗いているのは、大いに理にかなっています。
でも、それがケータリングやソーダ水とどう関係するのかは、私も売り手同様さっぱり分からず、ここはやはり1890年代のアメリカ市民に聞いてみるしかないのかもしれません。
(アップルソーダならぬアップルサイダーはクリスマスに付き物。Nicole Raudonis氏のApple Cider Christmas Cocktailのレシピはこちら。画像も同ページより)
かわいい天文学者とパリのカフェ ― 2024年09月01日 13時36分41秒
かわいい紙ものを見つけました。青いドレスの女の子が熱心に望遠鏡をのぞき込んでいるそばで、昔の天文学者風の男の子が「紙の星」を揺らして、女の子の興味を引きつけています。いかにもほほえましい絵柄。
この品の正体は、昔のメニューカードです。
パリ・オペラ座(ガルニエ宮)の脇に1862年開業した、老舗の「グラン・ホテル」(※)。現在はインターコンチネンタルの傘下に入り、「インターコンチネンタル・パリ・ル・グラン」となっていますが、その一角、ちょうどオペラ広場に面して今も営業しているのが、多くの文化人に愛された「カフェ・ド・ラ・ペ(Café de la Paix)」で、1878年のある日のランチメニューのカードがこれです。
(Google ストリートビューより。正面がオペラ座、左のグリーンの日除けの店がカフェ・ド・ラ・ペ)
メニューカードというのは、当日記念に持ち帰る人も多く、それが時を経て紙ものコレクターの収集対象となり、eBayでも古いもの、新しいもの、いろいろなカードが売られているのを見かけます。
カードの周囲に目をこらせば、ディナーは6フラン(ワイン代込み)、ランチは4フラン(ワイン、コーヒー、コニャック代込み)とあって、気になる献立はというと、その内容は裏面に記載されています。
1878年11月16日(土曜日)の午餐に供されたのは、以下の品々。
…といって、私にはまったく分からないんですが、ネットの力を借りて適当に書くと(違っていたらごめんなさい)、まずブルターニュの牡蠣に始まって、白身魚のフリット、オマールエビのマヨネーズ添え、ステーキとポテトのバターソース添え、鶏レバーの串焼き、キドニーソテーのキノコ添え、もも肉ローストのクレソン添え、ほうれん草入りハム、インゲンのバター風味、冷製肉、半熟卵、スクランブルオムレツと来て、最後にデザート。19世紀のフランス人は(今も?)だいぶ健啖なようですね。
ワインもお好みでいろいろ。料金4フラン(たぶん今の邦貨で1万円ぐらい)にはワイン代も含まれていたはずですが、こちらはグラスワインとは別に、ボトルを頼んだ時の別料金でしょう。
★
さて、飲み食いの話ばかりでなく、肝心の望遠鏡について。
そもそもランチメニューの絵柄が、なぜ望遠鏡なのか?
そこに深い意味があるのかどうか、とりあえずメニューの内容とは関係なさそうですね。この日、何か天体ショーがあって、それにちなむものなら面白いのですが、にわかには分かりません。この年の7月にアメリカで壮麗な皆既日食があり、天文画の名手、トルーヴェロ(Etienne Leopold Trouvelot、1827-1895)が見事な作品↓を残していますが、季節も国も違うので、これまた関係なさそうです。
(出典:ニューヨーク公共図書館
あるいは全然そういうこととは関係なく、単に見た目のかわいらしさだけでこの絵柄となった可能性もあるかなあ…と思ったりもします。というのは、これと全く同じ絵柄を別のところでも目にしたことがあるからです。
右側に写っている一回り小さいカードは以前も登場しました。
■紙の星
こちらはパリの洗濯屋の宣伝カードで、洗濯屋と望遠鏡ではそれこそ縁が薄いので、これは完全に見た目重視で選んだのだと思います。
こういう例を見ると、この種のクロモカードの製作過程も何となく想像がつきます。つまり、この種のカードはカスタムメイドのオリジナルではなく、出来合いの印刷屋の見本帳を見て、「今回はこれで…」とオーダーする仕組みだったんじゃないでしょうか。
★
同じ絵柄のカードを2枚買うのは無駄かとは思いましたが、洗濯屋よりはカフェの方がはるかに風情があるし、常連だったというゾラ、チャイコフスキー、モーパッサンらが、この日カフェ・ド・ラ・ペを訪れていた可能性も十分あるので、ベルエポックのパリで彼らと同席する気分をいっとき味わうのも、混迷を深める現世をのがれる工夫として、悪くないと思いました。
-----------------------------------------
(※) フランス語の発音だと「グラン・オテル」だと思いますが、ここでは「ホテル」とします。オペラ座やグラン・ホテルを含むこのエリアは、19世紀のパリ改造によって建物がすっかり建て替わった地域で、時系列でいうと、グラン・ホテルのほうがオペラ座(1874年竣工)よりも先に完成しています。ちなみに、カードにはグラン・ホテルに隣接する、これまた老舗の「ホテル・スクリーブ」の名も併記されていて、今では全然別経営だと思うんですが、当時は「グラン・ホテル別館」の扱いだったようです。
18世紀の版画「天文学」を読む ― 2024年07月15日 15時51分07秒
昨日の「天文学(Astronomy)」と題された18世紀の版画を、天文風俗史の観点から眺めてみます。全体としてこの絵は実景ではないと思いますが、この絵には当時の天文学が帯びていた文化的コンテクストが象徴的に表現されていると想像します。
(正面像がガラス反射で撮れないので、オックスフォード科学史博物館の画像をお借りします。出典:https://mhs.web.ox.ac.uk/collections-online#/item/hsm-catalogue-7467)
これを見てまず気になるのは不思議な背景で、これは明らかに同時代のロマン主義的廃墟趣味の表れでしょう。18世紀から19世紀にかけて、廃墟にロマンを感じる感性が西欧を席巻し(いわばヨーロッパ版わびさびの感覚です)、果ては人工的に廃墟っぽいものをこしらえて、それを庭園の景物に据えて喜ぶなどということも富裕層の間で流行したと聞きます。この絵に描かれているのも、おそらくそれでしょう。
(オーストリアのマリア・エンツァースドルフに作られた人工廃墟、1810-11年。Wikipedia 「Artificial ruins」の項より。撮影 C.Stadler/Bwag)
人工廃墟というのは、見かけは古くても、それを楽しむこと自体はお洒落でファッショナブルな行為ですから、その前で繰り広げられる紳士淑女の天文趣味にも、同様にファッショナブルな意味合いがあった…という風に読めます。彼らの気取ったポーズ、あでやかな服装にもそのことは表れています。
★
この版画に登場する天文機器類は、まずアーミラリースフィアと天球儀、
そして、足元に散らばるディバイダ、物差し、バックスタッフ(背杖)といった航海用天測具類です。
これらは通時代的に天文学のシンボルですから、「天文学」というタイトルの絵に登場するのは、ある意味当然ですが、傍らで仲睦まじく語らう男女に対して、アーミラリーと天球儀を手にした男性二人は、何だか孤立していますね。
虫眼鏡片手の学者先生と、メランコリックな若者といったところでしょうか。とはいえ、虫眼鏡でアーミラリーを覗く必然性は全くないので、これはいくぶん戯画化された学者像だと感じます。
★
こちらも男女のペアです。天文学がロマンスを連想させる――つまり、星を語ることは、当時すでにロマンチックなことであったことを示すものでしょう。
と同時に、この男性が女性をやさしく教え諭す姿は、一つの時代の型みたいなもので、女性が質問し、男性が答えるという問答体の科学入門書が、当時盛んに出版されましたが、そうした趣向を絵画化すると、こんな絵面になるのでしょう。(問答体の科学入門書はその後も健在ですが、時代の変化に応じて、対話するのは<子供と親>へ、さらに<素人と専門家>へと変わっていきました)。
(1772年にロンドンで出た『The Young Gentlman and Lady’s Philosophy』口絵)
そして、このカップルが手にするのが、近代天文学のシンボル・望遠鏡ですが、ここでこの絵の最大の謎にぶつかります。なぜ彼らは望遠鏡を反対向きに覗いているのか?
最初は、近くのものを遠くに眺めて楽しむ、一種の視覚玩具として望遠鏡を使っているのかな?とも思いましたが、もう一人の男性もやっぱり反対向きに覗いているので、ここには明瞭な作画意図があるのだと思います。
当時、「望遠鏡を反対向きに覗く」というのが、何か一般的なアレゴリーとして成立していたのかどうか、そこがはっきりしませんが、そこに意図があるとすれば、おそらくは皮肉な意図でしょう。
★
私はこの絵を最初、18世紀の典雅な天文学の営みを描いたもの…と素朴に考えていましたが、何かもうちょっと複雑な背景――例えば上流階級の浮薄さを揶揄するような意図を持った絵なのかもしれません。
【2024.7.21付記】 この図は「逆さ覗き」ではなく、こういう形状の、すなわち太い方から覗く古式の望遠鏡を描いたものであろうと、コメント欄で「パリの暇人」さんにご教示いただきました。状況証拠に照らしてそれが妥当と考えます。したがって、記事の後段は誤解に基づく無意味な文章ということになりますが、記録的意味合いからそのままにしておきます。
ひとひらのワーナー・アンド・スウェイジー ― 2024年04月20日 06時00分46秒
我が家には大きな天文台も小さな天文台もありませんが、ワーナー社をしのぶ品がひとつだけあります。
それは小さな双眼鏡で、
口径1インチ、倍率は6倍という、これ以上ないぐらい小さな製品です。
どういう光路になっているのか、ちょっと変わったシルエット。
これがワーナー社の製品であることは疑いようがなく、
そこにはクリーブランドのワーナー社の名前と共に、「1902年3月18日パテント取得」の文字が刻まれています。
ワーナー社の可憐な夢のかけらを前にして詠んだのが今日の記事のタイトルで、「ぶらんこ」が超感覚的に春の季語とされているように、「ワーナー・アンド・スウェイジー」も春の季語である…ということにしておきましょう。
自ら付け句してかくなむ。
ひとひらのワーナー・アンド・スウェイジー
月もおぼろに 星もおぼろに
月もおぼろに 星もおぼろに
ワーナー・アンド・スウェイジー、夢の跡(後編) ― 2024年04月19日 05時28分10秒
この写真集には、天文機器の写真とならんで、天文台の外観写真が何枚も載っています(全36枚の図版のうち10枚がそうした写真です)。
たとえば、ニューヨークのダドリー天文台。まさに「星の館」にふさわしい外観で、憧れを誘います。ワーナー社はここに12インチ(すなわち口径30cm)望遠鏡を提供しました。
同社の12インチ望遠鏡というと、これぐらいのスケール感。
ちょっと毛色の変わったところでは、中東シリアの首都ベイルートに立つ「シリア・プロテスタント大学」の天文台なんていうのもあります(ここはその後、無宗派の「ベイルート・アメリカン大学」となり、天文台も現存)。ここに納入したのも12インチ望遠鏡でした。
何度か名前の出たワシントンの米国海軍天文台。
ワーナー社とは縁が深かったようで、ここには26インチ(約66cm)大望遠鏡をはじめ、6インチ子午環、5インチ経緯儀、さらに46フィートドーム(差し渡し14m)や26フィートドーム(同8m)といった多くの備品を供給しています。
上の写真の左端に写っている建物のアップ。
26インチ大望遠鏡はここに据え付けられました。望遠鏡以外に、昇降床やドームもワーナー社製です。
その内部に鎮座する26インチ望遠鏡の勇姿。ヤーキス天文台の40インチ望遠鏡にはくらぶべくもありませんが、それでも堂々たるものです。
海軍天文台の白亜の建物を設計したのは、著名な建築家のハント(Richard Morris Hunt 、1827—1895)で、ここは彼の最晩年の作品になりますが、そのハントの名は本書にもう1か所登場します。
それが冒頭、第1図版に登場するこの愛らしい天文台です(写真の左下にハ
ントの名が見えます)。
「ワーナー、スウェイジー両氏の個人天文台」。
この小さな塔の上の
小さなドームの中で、ふたりはどんな夢を追ったのか?
巨大なドームにひそむモンスター望遠鏡ももちろん魅力的ですが、この小さな天文台をいつくしみ、写真集の巻頭に据えたワーナーとスウェイジーの心根に私は打たれます。かのハントに設計を依頼したのも、二人がここをそれだけ大切に思ったからでしょう。立派な中年男性をつかまえて可憐というのも妙ですが、その優しい心根はやっぱり可憐だし、優美だと思います。
(この項おわり)
ワーナー・アンド・スウェイジー、夢の跡(中編) ― 2024年04月17日 07時28分49秒
写真集の中身を見てみます(以下、原著キャプションは青字)。
「米国海軍天文台、ペンシルベニア大学、その他のために製作された天文機器類」。ワーナー社の倉庫ないし展示室に置かれ、納品を待つ製品群です。手前の4台は天体の位置測定用の子午儀・子午環、その奥は一般観測用の望遠鏡。
前回、前々回触れたように、ワーナー社の光学機器はレンズを外注しており、そのオリジナリティは機械的パーツの製作にこそありました。
たとえば、こちらは「米国海軍天文台の26インチ望遠鏡用の運転時計(driving clock)」。天体の日周運動に合わせて鏡筒を動かし、目標天体を自動追尾するための装置です。
あるいは、天体の位置を厳密に読み取る「位置測定用マイクロメーター(position micrometer)」。
あるいは、「自社で製作し使用している40インチ自動目盛刻印装置」。上のマイクロメーターもそうですが、計測機器の「肝」ともいえる目盛盤の目盛りを正確に刻むための装置で、工作機械メーカーの本領は、こんなところに発揮されているのでしょう。
そうした製作加工技術の集大成が、大型望遠鏡であり、それを支える架台であり、全体を覆うドームでした。(「ヤーキス天文台の40インチ望遠鏡、90フィートドームおよび75フィート昇降床」、「ワーナー・アンド・スウェイジー社設計・施工。1897年」。)
上のヤーキスの大望遠鏡は実地使用に先立って、シカゴ万博(1893)にも出展されました。足元には正装をした男女、頭上には巨大な星条旗。天文学では後発だったアメリカがヨーロッパに追いつき、けた外れのスピードで追い越していった時代の変化を如実に物語っています。
(この項、次回完結)




















































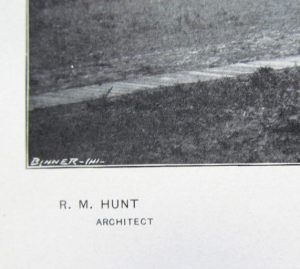

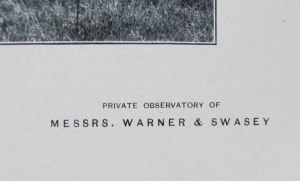








最近のコメント