賢治と鉱物、そして天河石のこと ― 2008年03月20日 19時07分00秒
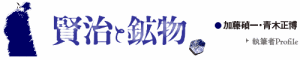
作業はゆっくり、ゆっくり進行中です。
☆ ☆ ☆
さて、ご存知の方も多いでしょうが、現在、工作舎のサイトで加藤碵一・青木正博両氏による 「賢治と鉱物」 の連載が続いています。
(この情報はひと月ほど前に、synaさんに教えていただきました。)
■連載第1回 賢治が愛した青い石
http://www.kousakusha.co.jp/planetalogue/kenji/kenji01.html
連載は鉱物の色ごとに進むらしく、これまでの4回はすべて「青」をテーマにしています。
☆ ☆ ☆
ところで、連載第1回でとり上げているアマゾナイト。
その和名の 「天河石」 がちょっと気になっています。
「天河」 とは天の川のことだそうで、実に美しい名前ですが、ただアマゾンと銀河の結び付きにいくぶん解せないものを感じます。
天の川にちなんで命名するなら 「天河」 よりポピュラーな漢語はいろいろあったはずで(例えば銀漢、天漢、あるいはズバリ銀河など)、わざわざ 「天河」 としたのは一寸苦しい気がします。(字書には 「天河」 も載っていますが、平均的な知識人は上のような語をまず想起したのではないでしょうか。)
で、思ったのは、かつてアマゾンの 「アマ」 と 「天(あま)」 をかけて、アマゾン川を 「天河」 と美称した可能性はないだろうかということです。もちろんこれは訓読みですから、日本限定の異称ということになります。
ただ、そういう実例はまだ見当たらないので、今のところは全くの想像です。明治の初めの文献を見ると、アマゾンはそのままカナ書きしたり、 「亜馬孫」 という不粋な字を当てたりしています。
天河石の名称がいつから使われているかは、寡聞にして知りませんが、国会図書館が所蔵する明治19年の資料(東京教育博物館列品目録)でも、すでに 「Amazon stone 天河石」 となっているので、明治の初期から使われていたのは確実です。あるいは江戸時代には既に使われていたかもしれません。
そもそも、江戸の金石学では外来の鉱物名をどう訳していたんでしょうか?
司馬江漢が描いたアメリカ地図(http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/maps/map021/image/index.html)を見たら、アマゾンは 「アマソ子〔ネ〕ン」 になっていました。そしてもう1つの大河・ラプラタ河が 「銀河」 と書かれているのが非常に気になります。La Plata はスペイン語で 「銀」 の意味ですから、ハリウッドを 「聖林」 というのと同じ表意訳ですね。
で、当時の才人が 「銀河」 と対になるように、アマゾンを 「天河」 と洒落て訳し、そこからさらに 「天河石」 の名も付いたのではあるまいか…そんなことを濁った頭で考えています。
★付記★
出口王仁三郎が大正時代に著した奇書 『霊界物語』 には、「…太古に於けるアマゾン河の名称は天孫河と命ぜられ」 云々という記述があるそうです。これは全く傍証にも何にもなりませんが、「アマゾン」 の音からそういう字を連想した人がいた、ということで挙げておきます。
☆ ☆ ☆
さて、ご存知の方も多いでしょうが、現在、工作舎のサイトで加藤碵一・青木正博両氏による 「賢治と鉱物」 の連載が続いています。
(この情報はひと月ほど前に、synaさんに教えていただきました。)
■連載第1回 賢治が愛した青い石
http://www.kousakusha.co.jp/planetalogue/kenji/kenji01.html
連載は鉱物の色ごとに進むらしく、これまでの4回はすべて「青」をテーマにしています。
☆ ☆ ☆
ところで、連載第1回でとり上げているアマゾナイト。
その和名の 「天河石」 がちょっと気になっています。
「天河」 とは天の川のことだそうで、実に美しい名前ですが、ただアマゾンと銀河の結び付きにいくぶん解せないものを感じます。
天の川にちなんで命名するなら 「天河」 よりポピュラーな漢語はいろいろあったはずで(例えば銀漢、天漢、あるいはズバリ銀河など)、わざわざ 「天河」 としたのは一寸苦しい気がします。(字書には 「天河」 も載っていますが、平均的な知識人は上のような語をまず想起したのではないでしょうか。)
で、思ったのは、かつてアマゾンの 「アマ」 と 「天(あま)」 をかけて、アマゾン川を 「天河」 と美称した可能性はないだろうかということです。もちろんこれは訓読みですから、日本限定の異称ということになります。
ただ、そういう実例はまだ見当たらないので、今のところは全くの想像です。明治の初めの文献を見ると、アマゾンはそのままカナ書きしたり、 「亜馬孫」 という不粋な字を当てたりしています。
天河石の名称がいつから使われているかは、寡聞にして知りませんが、国会図書館が所蔵する明治19年の資料(東京教育博物館列品目録)でも、すでに 「Amazon stone 天河石」 となっているので、明治の初期から使われていたのは確実です。あるいは江戸時代には既に使われていたかもしれません。
そもそも、江戸の金石学では外来の鉱物名をどう訳していたんでしょうか?
司馬江漢が描いたアメリカ地図(http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/maps/map021/image/index.html)を見たら、アマゾンは 「アマソ子〔ネ〕ン」 になっていました。そしてもう1つの大河・ラプラタ河が 「銀河」 と書かれているのが非常に気になります。La Plata はスペイン語で 「銀」 の意味ですから、ハリウッドを 「聖林」 というのと同じ表意訳ですね。
で、当時の才人が 「銀河」 と対になるように、アマゾンを 「天河」 と洒落て訳し、そこからさらに 「天河石」 の名も付いたのではあるまいか…そんなことを濁った頭で考えています。
★付記★
出口王仁三郎が大正時代に著した奇書 『霊界物語』 には、「…太古に於けるアマゾン河の名称は天孫河と命ぜられ」 云々という記述があるそうです。これは全く傍証にも何にもなりませんが、「アマゾン」 の音からそういう字を連想した人がいた、ということで挙げておきます。
コメント
_ S.U ― 2008年03月20日 21時49分15秒
_ ymine ― 2008年03月20日 23時23分01秒
はじめまして。
「天河」の表記は、万葉集中に見られるという記事を見ました(平凡社「世界大百科事典」天の川の項)。
一方、アマゾナイトについては国内に産地があったようなので(http://mineralhunters.hp.infoseek.co.jp/tadati07_8.html)、アマゾンと天河の結びつきはなく、アマゾナイトの名称とは独立に、鉱石の様子から天河石と命名されたという説はいかがでしょう。
「天河」の表記は、万葉集中に見られるという記事を見ました(平凡社「世界大百科事典」天の川の項)。
一方、アマゾナイトについては国内に産地があったようなので(http://mineralhunters.hp.infoseek.co.jp/tadati07_8.html)、アマゾンと天河の結びつきはなく、アマゾナイトの名称とは独立に、鉱石の様子から天河石と命名されたという説はいかがでしょう。
_ mistletoe ― 2008年03月21日 14時50分37秒
こんにちは。
宮沢賢治は好きですが、もう何年も読んでいないので
落ち着いたら色々読み直したいと思っています。
最近、母から『土神と狐』について 宇野亜喜良さんが語られていた事を聞き、 宇野さんの解釈に興味が沸いたので一番初めに読みたいと思っています。
工作舎!!大好きな出版社です。サイト覗いて見ます。
最近は自分の鉱物のコレクションもストップしています・・・色々集めすぎなんですよね・・・
宮沢賢治は好きですが、もう何年も読んでいないので
落ち着いたら色々読み直したいと思っています。
最近、母から『土神と狐』について 宇野亜喜良さんが語られていた事を聞き、 宇野さんの解釈に興味が沸いたので一番初めに読みたいと思っています。
工作舎!!大好きな出版社です。サイト覗いて見ます。
最近は自分の鉱物のコレクションもストップしています・・・色々集めすぎなんですよね・・・
_ 玉青 ― 2008年03月21日 21時32分00秒
語源考証は人を惹き付けるものがありますね!やはり言葉は、人が世界を支配する道具だからでしょうか。
>S.Uさま
何とも興味深い話です。明治の初めにUさんの挙げられた連想ルートで命名し得るほど西洋文明に親炙した人がいたかどうかがポイントでしょうが、しかし自然と虚心に向き合うとき、人の心にはこういう不思議な暗合がまま起こるのも確かだと思います。
死者を乗せて旅する銀河鉄道のアイデアは全く賢治の独創にせよ、彼は同時に銀河を亡魂の通う道と見なした北欧やネイティブ・アメリカンの神話を期せずしてなぞっていたことを想起します。
ほとばしる乳、乳房を切り落とした女傑、青く澄んだ石、インディゴブルーの夏の宵…確かに何かリズムを感じます。
>ymineさま
はじめまして!
「天河石」の名称が、アマゾナイトと独立に古くから使われていたというのは、真剣に検討すべき説だと思います。何かいい文献が見つかると面白いのですが…。
この点について、ふと思いついたことがあるので、明日改めて記事を書こうと思います。
>Mistletoeさま
賢治のことを書いているわりに、私はあんまり賢治を読んでないんですが、「土神と狐」はいい話ですね。
私は賢治を、世間で思う以上に男気のある人だと思っていますが、この作品は「すべての男性の心には土神と狐が棲んでいる」というところが魅力なのではないでしょうか。
>S.Uさま
何とも興味深い話です。明治の初めにUさんの挙げられた連想ルートで命名し得るほど西洋文明に親炙した人がいたかどうかがポイントでしょうが、しかし自然と虚心に向き合うとき、人の心にはこういう不思議な暗合がまま起こるのも確かだと思います。
死者を乗せて旅する銀河鉄道のアイデアは全く賢治の独創にせよ、彼は同時に銀河を亡魂の通う道と見なした北欧やネイティブ・アメリカンの神話を期せずしてなぞっていたことを想起します。
ほとばしる乳、乳房を切り落とした女傑、青く澄んだ石、インディゴブルーの夏の宵…確かに何かリズムを感じます。
>ymineさま
はじめまして!
「天河石」の名称が、アマゾナイトと独立に古くから使われていたというのは、真剣に検討すべき説だと思います。何かいい文献が見つかると面白いのですが…。
この点について、ふと思いついたことがあるので、明日改めて記事を書こうと思います。
>Mistletoeさま
賢治のことを書いているわりに、私はあんまり賢治を読んでないんですが、「土神と狐」はいい話ですね。
私は賢治を、世間で思う以上に男気のある人だと思っていますが、この作品は「すべての男性の心には土神と狐が棲んでいる」というところが魅力なのではないでしょうか。
_ ymine ― 2008年03月21日 23時58分19秒
自説撤回です。(汗)
「天」がつく名前の鉱石が他にもあったように思って調べてみると、
やはり、天青石(Celestite)、天藍石(Lazulite)があります。
なんてひんやりと美しい名前かと思いますが、どちらも青色を含んだ鉱石です。
天河石も青い石のようですので、おそらく、青=「天」という意味づけにアマゾン=「河」を組み合わせて天河石と名づけたのではないでしょうか。
しつこくて済みません。(汗汗)
「天」がつく名前の鉱石が他にもあったように思って調べてみると、
やはり、天青石(Celestite)、天藍石(Lazulite)があります。
なんてひんやりと美しい名前かと思いますが、どちらも青色を含んだ鉱石です。
天河石も青い石のようですので、おそらく、青=「天」という意味づけにアマゾン=「河」を組み合わせて天河石と名づけたのではないでしょうか。
しつこくて済みません。(汗汗)
_ 玉青 ― 2008年03月22日 11時22分41秒
ymineさま、またまたありがとうございます。
>自説撤回です。
いえいえ、天河石という名は、江戸時代にあっても違和感はないので、やはり一度は検討する必要があると思います。
「青い大河の石」。これも美しい豊かなイメージですね。
鉱物の外見的な特徴を示す共通語根は、光・輝・透・斑のように数多いので、「天」=「青」の意ではないかというご指摘も当を得たものと思います。 ただ、「天」についてはこの通則外でしょう。
Celestiteは、直訳すると「天石」となって語調が悪いので、色彩を補って「天青石」としたのでしょう。(透明な青色から Celestite と命名されたので、半ば直訳ともいえますが。)
また、Lazuliteは、「lazul = sky blue」という辞書の記述から考え出したに違いありません。
いずれも「天」の1字で「青」を表しているというよりは、そのあとの「青」や「藍」のニュアンスを形容している字句のように思います。
とはいえ。私は鉱物に関して全く門外漢なので、話半分に聞いてください。(汗)マークが20回ぐらい必要です。。。
>自説撤回です。
いえいえ、天河石という名は、江戸時代にあっても違和感はないので、やはり一度は検討する必要があると思います。
「青い大河の石」。これも美しい豊かなイメージですね。
鉱物の外見的な特徴を示す共通語根は、光・輝・透・斑のように数多いので、「天」=「青」の意ではないかというご指摘も当を得たものと思います。 ただ、「天」についてはこの通則外でしょう。
Celestiteは、直訳すると「天石」となって語調が悪いので、色彩を補って「天青石」としたのでしょう。(透明な青色から Celestite と命名されたので、半ば直訳ともいえますが。)
また、Lazuliteは、「lazul = sky blue」という辞書の記述から考え出したに違いありません。
いずれも「天」の1字で「青」を表しているというよりは、そのあとの「青」や「藍」のニュアンスを形容している字句のように思います。
とはいえ。私は鉱物に関して全く門外漢なので、話半分に聞いてください。(汗)マークが20回ぐらい必要です。。。
_ S.U ― 2008年06月07日 17時55分45秒
玉青様とかすてん様に掛図についてのコメントの議論を戴いたところですが、
ちょっと前の話題にもどらせていただきます。
今日、つくばの産総研の前を通りかかったので、地質標本館の特別展示「青柳鉱物
標本の世界」を見学してきました。
http://www.gsj.jp/Muse/eve_care/2007/aoyagi/aoyagi.html
展示列の劈頭を飾っていたのは、なんと「天河石」でした。けっこう名高い鉱物なのですね。
そのほか、足穂の「水晶物語」に出てくる「草入り水晶」やymine様のご指摘にある「天青石」
(上のwebページで、ポスターのすぐ下にある3つのうちの真ん中のものがそれです)も
「天藍石」もありました。天文古玩の術中にはまったような展示でした。それで、「天青石」
を見た感想ですが、やはりこの学名Celestine/celestiteは、宇宙の青と透明さをイメージ
してつけたもののように思いました。ひょっとすると天動説で天体が張り付いているという
透明な球殻のイメージから来ているのかもしれません。私は、この3つの石に青みがかっ
ていること以外の質的な共通点を感じなかったことから、やはり単純に「天」=「青」という
意味だったのではないかと感じました。(もちろん、ただ感じただけですので、「天」が形容詞
的であるという説や「天ゾン」説を否定するものではありません)
ちょっと前の話題にもどらせていただきます。
今日、つくばの産総研の前を通りかかったので、地質標本館の特別展示「青柳鉱物
標本の世界」を見学してきました。
http://www.gsj.jp/Muse/eve_care/2007/aoyagi/aoyagi.html
展示列の劈頭を飾っていたのは、なんと「天河石」でした。けっこう名高い鉱物なのですね。
そのほか、足穂の「水晶物語」に出てくる「草入り水晶」やymine様のご指摘にある「天青石」
(上のwebページで、ポスターのすぐ下にある3つのうちの真ん中のものがそれです)も
「天藍石」もありました。天文古玩の術中にはまったような展示でした。それで、「天青石」
を見た感想ですが、やはりこの学名Celestine/celestiteは、宇宙の青と透明さをイメージ
してつけたもののように思いました。ひょっとすると天動説で天体が張り付いているという
透明な球殻のイメージから来ているのかもしれません。私は、この3つの石に青みがかっ
ていること以外の質的な共通点を感じなかったことから、やはり単純に「天」=「青」という
意味だったのではないかと感じました。(もちろん、ただ感じただけですので、「天」が形容詞
的であるという説や「天ゾン」説を否定するものではありません)
_ 玉青 ― 2008年06月08日 20時35分49秒
天の石は青く澄んでいる…。とても美しいイメージです。
「名づけ」という行為には、たぶん命名者の思惑以上のものがあり、<ことば>はその言語を共有する人すべてが等しく育んでいくものなのかもしれません。
そうしたイメージから、さらに新しい美しい鉱物名が続々生まれたら素敵ですね!
「名づけ」という行為には、たぶん命名者の思惑以上のものがあり、<ことば>はその言語を共有する人すべてが等しく育んでいくものなのかもしれません。
そうしたイメージから、さらに新しい美しい鉱物名が続々生まれたら素敵ですね!
_ とこ ― 2008年06月08日 23時28分18秒
横レス失礼いたします。
わたしも、本日余力があったら地質標本館にゆこうと思っていたところだったので吃驚しました。頭痛で断念したのですが…これはゆかねば!!
S.Uさま、情報ありがとうございました。
わたしも、本日余力があったら地質標本館にゆこうと思っていたところだったので吃驚しました。頭痛で断念したのですが…これはゆかねば!!
S.Uさま、情報ありがとうございました。
_ S.U ― 2008年06月09日 23時32分51秒
玉青様、そうですね。語源探しは興味が尽きませんが、定着してしまえば、もうすべてが
「みんなのもの」ですね。
とこ様、こんばんは。私は、鉱物の価値はよくわからないのですが、結晶のつぶが
大きくそろっていて良かったように思います。
それから、6月10日(火)~12日(木)は、地質標本館の岩石・鉱物・化石の常設展示室が
閉鎖されるということですので、ご注意下さい。
「みんなのもの」ですね。
とこ様、こんばんは。私は、鉱物の価値はよくわからないのですが、結晶のつぶが
大きくそろっていて良かったように思います。
それから、6月10日(火)~12日(木)は、地質標本館の岩石・鉱物・化石の常設展示室が
閉鎖されるということですので、ご注意下さい。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
おもしろいお話しをありがとうございます。私は、鉱物の知識はさっぱりですが、
やはり「天ゾン」のしゃれだと思います。
ところで、アマゾンの語源を調べてみますと、もちろん、女部族なのですが、Wikipediaでは、
>アマゾンの語源は、弓などの武器を使う時に右の乳房が邪魔となることから切り落としたため、"a"(否定)+"mazos"(乳)=乳無しと呼ばれたことからとされるが、これは近年では民間語源であると考えられおり実際にはすべてのアマゾンが右乳房を切り落としていたわけではない。
アマゾン → 乳を切られる → ヘラの神話 → Milky Way
という連想のパスも考えられるかもしれません。ギリシア神話にはアマゾン族もヘラも
出てくるので、それほど突飛な連想ではないかもしれません。いかがでしょうか。