暦メモ ― 2020年09月06日 20時00分02秒
暦について考える際の参考リンクをメモしておきます。
★
暦の話題は、単なるカレンダーという出版物にとどまらず、もっとはるかに大きな――たぶん私が思っているよりもさらに大きな――話題で、人間と時間をめぐる歴史のすべてにかかわってくるはずです。
日本は暦の後発地域で、大陸や半島から暦学が伝わってから、まだ千数百年といったところですが、それでも暦をめぐる話題は尽きません。そういう大きなテーマを、ナショナル・ギャラリーのレベルでは、どこで取り扱うべきなのか?
もちろん編暦を一手につかさどる国立天文台は、現代の土御門家みたいなものですから、暦学の歴史については詳しいです。
したがって、上のページで明らかなように、暦に焦点を当てた企画展も多いです。たとえば、2016~17年にかけて行われた「二十四節気と暦」をはじめ、「月と暦」、「渋川春海と『天地明察』」(その1、その2、その3)…等々。
さらに、科学史全般を扱う国立科学博物館でも、暦に関する資料をせっせと収集し、展観しています。
上のページは、「理工」分野で「暦」をキーワードに検索した結果一覧です。
今日現在でヒットするのは42件。暦とはダイレクトに関係なさそうな品も表示されていますが、多くは天体観測や、測地・計時に関する品で、暦をめぐる科学の広がりを知ることができます。
★
ところで、今日気が付いたのですが、国立国会図書館もまた非常に充実した、暦に関する特設ページを設けていました。
■日本の暦
ビジュアル的にも凝った、見て楽しい内容で、国会図書館は、書物に関することは何でも扱うとはいえ、暦本という特殊な出版物に、これほど力を入れていたとは意外でした。担当者の熱意に打たれると同時に、大変頼もしい気がしました(最近、文化行政の退潮が著しく、やらなくて済むことはやらないのがデフォルト化していますから)。
★
そんなこんなで、暦については引き続き関心を向けていこうと思います。
コメント
_ S.U ― 2020年09月07日 18時05分30秒
_ 玉青 ― 2020年09月07日 21時37分47秒
これは変化球ですねえ。
S.Uさんは冗談と言われましたが、「暦を支配する最終的な権威は現在どこにあるのか?」というのは、決してゆるがせにできない問題ですから、真顔で考えてみます。
とりあえず江戸時代を基準にすると、当時はもちろん実質的な作業は、すべて幕府の天文方が行っていたんでしょうが、最終的な許認可権は京都(土御門家)にあったわけですよね。仮に京都が首を横に振れば、いかに幕府が怖い顔をしようが、頑として通らない…実際はそんなこともなかったでしょうが、少なくとも理論的にはそういう状態だったと思います。
では、現代ではどうか。現代のもっとも“権威ある”公的な暦は、官報掲載の「暦要項」で、これは国立天文台の暦計算室が作成し、国立天文台の名前で公表されています(特殊法人による公告という扱いです)。すなわち暦の最終的な許認可権は、所管大臣の文部相ではなく、国立天文台長が持っているという制度の建付けです。要するに、現代では国立天文台それ自体が、暦に権威を付与する主体であり、他からの支配を受けないという意味で、やっぱりここが「現代の土御門」のように感じます(そして天文方の役割を果たしているのが、同一組織内の暦計算室です)。
以上は、暦に権威を付与する主体という観点から考えた結果ですが、昔と今のお役所をアナロジカルに眺めたときはどうか?…となると、また違った答もありそうです。大昔の律令官制だと、暦道を司る陰陽寮は中務省所管でしたから、現代でいうと内閣府か総務省あたりで、その点では情報通信研究機構はいい線かもしれませんね。
S.Uさんは冗談と言われましたが、「暦を支配する最終的な権威は現在どこにあるのか?」というのは、決してゆるがせにできない問題ですから、真顔で考えてみます。
とりあえず江戸時代を基準にすると、当時はもちろん実質的な作業は、すべて幕府の天文方が行っていたんでしょうが、最終的な許認可権は京都(土御門家)にあったわけですよね。仮に京都が首を横に振れば、いかに幕府が怖い顔をしようが、頑として通らない…実際はそんなこともなかったでしょうが、少なくとも理論的にはそういう状態だったと思います。
では、現代ではどうか。現代のもっとも“権威ある”公的な暦は、官報掲載の「暦要項」で、これは国立天文台の暦計算室が作成し、国立天文台の名前で公表されています(特殊法人による公告という扱いです)。すなわち暦の最終的な許認可権は、所管大臣の文部相ではなく、国立天文台長が持っているという制度の建付けです。要するに、現代では国立天文台それ自体が、暦に権威を付与する主体であり、他からの支配を受けないという意味で、やっぱりここが「現代の土御門」のように感じます(そして天文方の役割を果たしているのが、同一組織内の暦計算室です)。
以上は、暦に権威を付与する主体という観点から考えた結果ですが、昔と今のお役所をアナロジカルに眺めたときはどうか?…となると、また違った答もありそうです。大昔の律令官制だと、暦道を司る陰陽寮は中務省所管でしたから、現代でいうと内閣府か総務省あたりで、その点では情報通信研究機構はいい線かもしれませんね。
_ S.U ― 2020年09月08日 06時42分53秒
これは、変化球に手を出して下さり、まことにありがとうございます(笑)。
格が今ひとつだなと、公家を見てみますと、土御門家も菅原家も「半家」(堂上家最下位)だそうですから、昔から国家を支える最高の学識といえども、日本の伝統では案外そんなところなのかもしれません。まあ御用学者の格など高くないほうが学識のためにはいいのですが、今日の学術政策と人材育成になんら高邁な理想がなくむしろ等閑視されているのもその流れかと思うと、冗談ではなくなってきました。
いずれにしても、権力や利権が間断なく伝えられるものなら、このような考察も何らかの意味はあるでしょう。暦とは関係ありませんが、弾正忠、左馬助、治部少補、左衛門尉、大炊頭、内匠頭、内蔵助などが、現在のどの役所のどの役職に引き継がれているのか考えるのも暇つぶしになるかと存じます。
格が今ひとつだなと、公家を見てみますと、土御門家も菅原家も「半家」(堂上家最下位)だそうですから、昔から国家を支える最高の学識といえども、日本の伝統では案外そんなところなのかもしれません。まあ御用学者の格など高くないほうが学識のためにはいいのですが、今日の学術政策と人材育成になんら高邁な理想がなくむしろ等閑視されているのもその流れかと思うと、冗談ではなくなってきました。
いずれにしても、権力や利権が間断なく伝えられるものなら、このような考察も何らかの意味はあるでしょう。暦とは関係ありませんが、弾正忠、左馬助、治部少補、左衛門尉、大炊頭、内匠頭、内蔵助などが、現在のどの役所のどの役職に引き継がれているのか考えるのも暇つぶしになるかと存じます。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
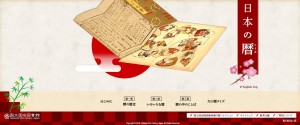
歴史時代に朝廷(天帝)が時を支配した権威、権力を現在の日本の公的研究機関に当てはめたとして、土御門家(公家)に対応するのはどこだと思われますか?
国立天文台は、現在では、大学共同利用機関法人自然科学研究機構の設置する7つの研究機関の1つにすぎません(ずいぶん失礼な言い方ですが、この分析自体が冗談半分ですのでお許しを)。歴史の流れ的には、朝廷系ではなく幕府系でしょうか。
国土地理院は、国土交通省に置かれる特別の機関で、こちらのほうが中央に近いように感じます。気象庁は、国土交通省の外局で、中央からはより遠いのだと思います。今は、天文と気象は別ですよね。海上保安庁水路部も、現在は天文や時に関わる仕事はしていないようです。でも、これらの職員は公務員です。
日本標準時を管理する情報通信研究機構が実質的に「権力が強い」かもしれません。これは非公務員型の国立研究開発法人ですけれども、所管が文科省や経産省や国土交通省ではなく総務相になっているのがミソかもしれません。
半分はどうでもいい冗談ですが、半分は今でも歴史的な思考が残っているのかもと思います。アホな考えでしょうか。