地上の星、天上の星 ― 2024年01月08日 13時22分44秒
先日、年末に注文した品が届きました。今年の初荷です。
それは現代の技術と感覚で作られた、1枚の美しい星図…のはずでした。
でも、輸送用チューブの中から出てきたのはマドンナのセクシーポスターで、「げげ!」と思いました。

このポスターは彼女のアルバム「Bedtime Stories」のリリース(1994)に合わせて作られたものらしく、まあマドンナもスターには違いないでしょうが、私が求めたのは別の星です。
もちろん売り手の方にはすぐ連絡を取りました。
その結果判明したのは、これは売り手ではなく、eBayインターナショナル・サービスセンターのミスだということです。eBayで買い物をされた方はご承知でしょうが、eBayの海外発送はかなり複雑で、途中いくつも業者が介在して荷物の受け渡しを行うのですが、その過程でラベルの貼り間違いが生じた…というのが、今回の出来事の原因でした。聞いてみれば「なるほどそんなこともあるのか…」と思いますが、これまでにない経験だったのでビックリしました。(ただし、その後のeBayの対応は早かったです。クレームを入れると、すぐに返金処理をしてくれました。この点は先日のPayPalと違うところです。)
それにしても、三者間の取り違えでない限り、私の星図はマドンナの到来を待ち望む人の元に届いたはずで、その人もずいぶん驚いたことでしょう。
大事小事、この正月は驚くことが多いです。
遊ぶ子供の声聞けば ― 2023年12月31日 10時23分00秒
いよいよ大晦日。
なんだかんだ言いながら、今年もいろいろなモノを手元に引き寄せて、当人は大いにご満悦です。(ついさっきも、「あ、いいな」と思った古絵葉書をまとめて注文しました。)
まあ、他人から見れば愚かしいことかもしれませんが、家族がちょっと迷惑に感じるぐらいで、世の中に特に害をなすことでもないし、愚は愚でも、わりと質(たち)のいい愚ではないか…と考えます(それこそ愚考かもしれませんが)。
★
昨日、買い物帰りに公園の脇を通ったら、遠目に満開の白い花木が見えました。「おや?冬桜かな?」と近づくと、それは桜でも花でもなく、ナンキンハゼの白い実でした。
ナンキンハゼは、人間を喜ばせようと思ってそうしているわけではないにしろ、樹木の冬の装いとしては至極上々の部で、自然というのは実に美しいものだと思いました。そして木の下で元気に遊ぶ子どもたちを見れば、人間のうちにも確かな美質があると直感できるのです。
★
今年一年「天文古玩」にお付き合いいただき、ありがとうございました。
2024年が、世界と人々にとってどうか良き年となりますように。
星夜独酌 ― 2023年12月28日 16時08分29秒
先月、11月21日の記事の一部を再掲します。
-----------(引用ここから)----------
ワインと12星座で検索したら、こんな記事がありました。
■What’s Your Sign? Matching Wine To Your Zodiac
(あなたの星座は?ご自分の星座にあったワインを)
(あなたの星座は?ご自分の星座にあったワインを)
もちろん真面目に読まれるべき内容でもないですが、ワイン選びに迷っている人には、案外こんなちょっとした耳打ちが有効みたいです。
私は射手座で、もうじき誕生日がくるんですが、「柔軟で、知的で、放浪心のある射手座のあなたには、フランスのカベルネ・フラン種や、イタリアのサンジョヴェーゼ種を使った赤ワインがお勧めだ」みたいなことが書かれていました(意訳)。
ウィキペディアによれば、サンジョヴェーゼの名はラテン語の sangius(血液)と Joves(ジュピター)の合成語で、ぶどう液の鮮やかな濃い赤に由来する由。そして誕生日当日(11月25日)には、木星と月齢12の月が大接近する天体ショーがあるそうなので、これはいよいよトスカーナワインを傾けねばならないことになるやもしれません。(まあ、ジュピターの血色をした赤ワインを傾けるのは、赤いちゃんちゃんこを着せられるよりも、確かにはるかに気が利いているでしょう。)
-----------(引用ここまで)----------
で、私は自分の言葉に励まされて、いそいそとサンジョヴェーゼのワインを買いに行ったものの、せっかくの思い付きも、風邪に阻まれて実行には至りませんでした。まあ、月と木星のドラマは寝床から観察できましたが、酒を口にするような気分と体調ではなかったからです。
(自分で自分の長寿を祝って、亀のラベルのワインを選びました)
そのボトルを、ようやく1か月後のクリスマスに開けることができました。
強靱なユピテルの血潮を口にしたことで、私ももうしばらくはこの世にとどまることができそうです。
★
そして今日は仕事納め。
せっかくだから正月向けのお酒も用意しようと、名古屋の星ヶ丘三越で「星美人」というのを奮発して買ってきました。「蓬莱泉」で有名な関谷酒造が、星ヶ丘店のために特に醸(かも)したものです。
こう書くと、なんだか酒ばかり呷(あお)っているようですが、正直、今年一年はだいぶ疲れがひどく、盃を手にすることが多かったです。
★
中国星座には、酒屋の軒にひるがえる旗に見立てた「酒星(しゅせい)」という洒落た星座があるそうで、李白はそれを踏まえて「天、若し酒を愛さざれば、酒星天に在らず」とうそぶきました。
まこと心を慰めるのには、盃を手に星をふり仰ぐにしくはありません。
疲れる話 ― 2023年12月10日 05時55分36秒
師走ということもあって、なんだかんだ忙しいです。
当分は「月月火水木金金」で、昨日も今日も出勤です。
★
その一方で、ずっと心に刺さっていたトゲが抜けて、ちょっとホッとしました。
それは9月に購入した本をめぐって、売り主であるスウェーデンの古書店主と揉めていた件で、このことは以前もチラッと書いた気がします。
購入したのは戦前の古い地図帳です。
古書店側の記載によれば、その地図帳には50枚の図版が含まれているはずでした。でも、届いた現物には36枚の図版しか含まれておらず、しかも図版が切り取られたとか、そういうわけではなくて、インデックス頁を見ても、最初から36枚の図しか含まれていないのでした。
そのことを先方に連絡した私は、これまでの経験から当然、「それは当方の手違いなので、すぐに返品してください。もちろん返送の送料は当方が負担します」とか、「ただちに返金しますので、お送りした本はそちらで処分をお願いします」とかの返答を期待しました。
でも、先方の回答はこちらの予想の斜め上を行くものでした。
「当方の記述はスウェーデン王立図書館のデータベースを転記したものです。それによれば、その地図帳の当該年の版には50枚の図版を含むものしか存在しません。どうぞご自分でデータベースをチェックしてみてください。残念ながら私にあなたの問題を解決できるとは思えません。」
「え!?」と思いました。スウェーデン王立図書館はたしかに大したものかもしれませんけれど、問題はそんなことではなく、50枚の図版を含むものとして販売された本に、36枚の図版しか含まれていなかったことが問題なのですよ…と、関連ページの写真も添えて、繰り返し説明したのですが、先方は頑として意見を変えず、さらには明らかに無礼な言葉まで投げてきました。これは埒が明かないと、PayPalに苦情を申し立てたのが10月のことです。
その裁定が延びに延びて、結局時間切れで、いったんは泣き寝入りでケース終了になるという嬉しくないオマケまで付いてきました。「そんな馬鹿な」と、再度不服申立をして、ようやくPayPalから返金の連絡があったのが昨日のことです。(時間がかかったのは、返品した本の受取りを先方が拒否し、現物がずっとスウェーデンの郵便局に塩漬けになっていたためです。その後、現物は再度送り返され、今は私の手元にあります。)
★
なんだかこう書いていても疲れます。
冤罪事件やスラップ訴訟に巻き込まれた人は、こんな気分なんでしょうかね。全体として釈然としない感じは残りますが、しかし全ては終わったのです。
重い目で月と木星を見る ― 2023年11月26日 19時38分45秒
風邪でずっと寝込んでいました。
でも月と木星の大接近は、私が風邪を引いたからといって待ってはくれませんから、昨夜は床の中から、この天体ショーを眺めていました。せっかくだから…と、だるい身体を起こして双眼鏡を持ってくると、双眼鏡の視野の中でも両者は仲睦まじく寄り添っていて、実にうるわしい光景です。ここでキャノンご自慢のスタビライザー機能をオンにすると、像はピタリと静止し、針でつついたような木星の月たちも見えてきます。地球の月、木星、そして木星の月たち。それを眺めている自分もまた、地球という惑星に乗って、今も宇宙の中を旅しているんだなあ…と今更ながら実感されました。と同時に、木星の4大衛星と地球の月は似たりよったりの大きさですから、両者を見比べることで、木星までの距離も直感されたのでした。
(いつも手の中で転がしている、木星の表面によく似た瑪瑙)
★
それにしても今回の風邪。金曜日の朝にいきなり39.4度まで熱がガッと上がり、これはてっきり…と思って近医に行ったんですが、インフルもコロナも検査結果は陰性でした。「まあ、ふつうの風邪でしょう」と言われて、薬をもらって帰ってきたものの、ふつうの風邪でこんなふうに突然高熱が出るものなのか?そこがちょっと不審です。
ひょっとして、コロナの後遺症で、免疫系がおかしくなってしまったのか…と、風邪で気弱になっているせいもありますが、そんな想像が頭をよぎり、不安に駆られます。
続・仙境に遊ぶ ― 2023年10月13日 18時32分56秒
海の向こうの本屋と揉めている…と、以前チラッと書きました。
あの件は実はまだ揉めていて、結局、PayPalの買い手保護制度を利用することにしました。ここまで話がこじれることは稀なので、同制度の利用は今回で2度目です。
相手だって、大抵は常識を備えた人間ですから、どんなトラブルでも話し合いが付くのが普通です。でも、今回は先方が謎のロジックを延々と展開するので、それ自体興味深くはありましたが、途中でこれはダメだと匙を投げました。
それにしても交渉事は消耗します。
しかも慣れない英語ですから、翻訳プログラムを援用しても、やっぱり骨が折れます。そんなわけで、記事の間隔が空きましたが、もうあとはPayPal頼みなので、記事の方を続けます。
★
福田美蘭氏の作品に触発されて見つけた私だけの仙境、それがこの1個の石です。
石を飾るときは、木の台座をカスタムメイドするのが通例らしいですが、ここでは浅い青磁の香炉を水盤に見立てて、盆石風に据えてみました。
まあ、伝統的な水石趣味の人に言わせると、これは単なる駄石でしょう。
岩の質が緻密でないし、色つやも冴えないからです。
でもこれを見たとき、かつて見た昇仙峡の景色を思い浮かべ、これこそリアルな岩山だと思いました。モデラーに言わせれば、この冴えない岩肌こそ「ウェザリングが効いている」んじゃないでしょうか。それに山容がいかにも山水画に出てきそうだし、いっそ海中にそびえる霊峰、「蓬莱山」のようだとも思いました。
あの辺りを鶴の群れが飛び、その脇で仙人が碁でも打ってるにちがいない。
あそこには庵があって、戦乱を逃れた隠者が住んでいるんじゃないだろうか。
夕暮れ時には、杣人があの麓の道を越えてゆくのだろう…。
あそこには庵があって、戦乱を逃れた隠者が住んでいるんじゃないだろうか。
夕暮れ時には、杣人があの麓の道を越えてゆくのだろう…。
――これこそ、私にとっての仙境だと思いました。
それにこの石は、どこから見ても、それぞれに山らしい表情をしています。
…とまあ、只同然で手に入れた石をえらく褒めちぎっていますが、こういうのは見る人次第ですから、私自身が仙境と思えば、それはすなわち仙境なのです。
★
「自分だけの世界」ということで、唐突に思い出した作品があります。
三浦哲郎作 「楕円形の故郷」(1972)。
中学卒業とともに青森から上京し、職を転々としている青年が主人公です。
彼は工場勤務のとき、機械で指を切断してしまい、今は荷物運びの助手をしながら、辛うじて生活しているのですが、その彼の唯一の慰めは、同郷の女友達と会って話をすることでした。でも、いつまでも田舎じみた彼を、彼女は疎ましく思い、次第に遠ざけられてしまいます。そんな孤独の中、ひょんなところで出会った以前の同僚から、寄植えの盆栽を見せられて、彼はハッとします。
「それは皿のように平たい楕円形の鉢に、片側を高く、片側を低く、全体として小高い台地のように土を盛りつけ、一面の苔を下草に見せている二十本ほどの寄植で、それが郷里の村にある櫟(くぬぎ)林の、南はずれの様子にそっくりなのだ。彼はそれを一と目見て、ぎくりとして動けなくなった。」
(Pinterestで見かけた寄植。https://www.pinterest.jp/pin/985231160218811/)
その盆栽を気前よく託された主人公は、毎晩それを眺めながら、夢想の世界に入り込むようになります。
「まず、苔の斜面を草地だと思うことにして、そこに寝そべっているちいさな自分を空想する。〔…〕それをじっと見詰めているうちに、ソロの林がだんだん膨れ上ってきて、やがて自分を呑み込んでしまう。林の梢を渡る風の音がきこえてくる。川の瀬の音がきこえてくる。小鳥の声がきこえてくる。遠くから脱穀機の唸りもきこえてくる。寺の鐘も鳴っている…。それから、おもむろに目を開ければ、そこはすでに見上げるような林の中だ。青く晴れ渡った空に、葉を落としたソロの梢が網の目のように交錯している。」
この「楕円形の故郷」という作品を、私は創元の『日本怪奇小説傑作集3』で読みました。これが怪奇小説と呼ばれるわけは、その哀切で奇妙な結末のせいですが、こういう「箱庭幻想」は私の中にも強烈にあって、福田美蘭氏の作品の前で釘付けになったのも、たぶん同じ理由だと思います。
★
無意味な諍いや、血みどろの戦のない世界を、せめて心の中に持ち続けたい…。
たとえ後ろ向きの考えと言われようと、それぐらいの自由は、人間誰しも享受して然るべきだと思います。
寝ぼけ声 ― 2023年08月29日 18時23分35秒
「ひょっとして、あいつは暑さで頓死したな?」と思われたかもしれません。
しかし、こうして無事生きています。生物界には冬眠と対になる「夏眠」というのがありますが、私も酷暑を避けてしばらく夏眠状態にあったわけです。でも、8月も終わりですから、そろそろ夏眠から覚めなくてはなりません。春の啓蟄に対し、秋の啓蟄がもう一つほしいところです。
しかし夏眠から覚めてあたりを見渡すと、世の中どうも芳しくないニュースが多いですね。目覚めの一言も、ちょっと無粋なところから始めます。
★
昔、中学だか高校だかの頃、アイザック・アシモフが「疑似科学」に論駁する本を読んで、おおいに溜飲を下げたことがあります。いわゆる「とんでも学説」を、まさに快刀乱麻を断つように切り捨てていく様は痛快であり、なんだか読んでいる自分まで賢くなったような気がしたものです。実際、アシモフはものすごく頭の切れる人だったのでしょう。
ただ、その中でひとつモヤっとするエピソードがありました。
健康食品に関する文章で、アシモフはヨーグルトが身体にいいという説を一蹴して、「ヨーグルトには牛乳に含まれる以上の栄養素はない!」と切って捨てていました。
それはそれで正しい陳述です。
腸内フローラの研究史は17世紀のレーウェンフックにまで遡るそうですが、その機能に関する研究はだいぶ紆余曲折があって、「ヨーグルトは不老長寿の霊薬」みたいな怪しげな言説も入り混じっていたので、アシモフがそれを疑似科学と切って捨てたのは、理解できなくもないです。ただ、結果的に彼が「食品がもたらすプラスの効果は、すべて栄養素の効果に還元できる」としたのは、あまりにも単純素朴な考えで、そこには大きな見落としがありました。
いかに既存の科学知識で武装しても――その武装がどれほど完璧なものであっても――そこには常に思考の盲点がありうるし、ときにその盲点は、広大な視野の欠落であると後に判明することもあります。アシモフほどの人でも、そこから逃れることはできませんでした。
この一件は私にとって非常に重要な教訓になっていて、今でも折に触れて思い出します。
★
原発「処理水」の海洋放出をめぐって、ネット上で半可通めいた人々が議論しているのを見ると、やっぱり上のことを思い出します。
最初に私の立場をはっきりさせておくと、私は海洋放出に反対です。
海洋中の物質動態は今も不明な点だらけのはずで、環境への影響を考えれば、放出には常に謙抑的であるべきです。それをごく狭い了見にもとづいて、「大丈夫、大丈夫!」と見切り発車するのは、盲者蛇に怖じずというか、蛮勇と呼ぶほかないのではないでしょうか。
★
仮に海洋放出のすべてのプロセスがオープンな状況で進んでも、上の疑念は残ります。ましてや、現在コトを司っているのは民間の一企業(および彼らと多くの利害を共有する関係者)なのです。
そこには巨額の賠償責任を逃れたいという、非常に大きなバイアスが常にかかっている事実を忘れるべきではありません。その意見はたとえ科学的相貌を帯びていても、およそ公平無私なものとは言えないし、そのことをカッコに入れたまま議論するのは相当危なっかしいと思います。
★
以上の文章は詮ずるところ情報量ゼロであり、なにか無責任な発言に聞こえるかもしれませんが、ことの重要性に鑑み、あえて「無知を正しく畏れよ」と私は申し上げたいです。
(記事の方は徐々に平常運転に戻します。)
明けぬ梅雨 ― 2023年07月11日 07時55分06秒
激しい雨によって、九州を中心に甚大な被害が出ました。
梅雨明けが近いと言われながら、「夜明け前がいちばん暗い」の言葉通り、容赦のない雨が続いています。今回被害に遭われた方はもちろん、雨と炎暑に苦しめられている多くの方々にお見舞い申し上げます。
私の方は、ここに来てにわかに本業に追われだしたので、しばらく記事の更新頻度を下げます。
梅雨明けが近いと言われながら、「夜明け前がいちばん暗い」の言葉通り、容赦のない雨が続いています。今回被害に遭われた方はもちろん、雨と炎暑に苦しめられている多くの方々にお見舞い申し上げます。
私の方は、ここに来てにわかに本業に追われだしたので、しばらく記事の更新頻度を下げます。
京都にて ― 2023年06月26日 09時25分05秒
世の中は 三日見ぬ間の 桜かな。
私が一泊二日で京都に行っている間に、ロシアでは大変な花火が上がり、世間は大騒動でした。まこと世界は常に動いていますね。
そんな騒動をよそに、私は足穂イベントの翌日、洛北・圓通寺を訪ねました。ここは江戸時代の初期、後水尾天皇が造営した「幡枝(はたえだ)離宮」の跡をそのまま臨済宗寺院としたもので、美しい庭で知られます。
朝一番に訪問したせいで、他に観光客の姿もなく、比叡全山を借景に取り込んだ雄大な庭を前に、ひとり(と言っても連れ合いが一緒でしたが)、昨夜のことをぼんやり反芻していました。
そして帰り道、ふと見上げた寺の棟飾に三日月を見つけ、何か不思議な暗合めいたものを感じたのです。
★
寺を辞したあとは、山道を抜けて深泥池(みどろがいけ、みぞろがいけ)を見に行きました。ここはジュンサイで有名ですが、市街地にほど近いロケーションでありながら、トンボをはじめとする豊かな生物相で知られる場所です。
(写真を撮り忘れたので、上はウィキペディアからの借用)
ちょうど地元の方たちが、池の清掃を兼ねて生物調査中で、投網を打っては、捕獲した魚類を詳細にカウントし、ブルーギル何尾、カムルチー(雷魚)何尾、ウシガエルのオタマジャクシ何尾…と、記録を取っておられました。それは何となく理科趣味を感じる光景ではありましたが、そんな呑気な感想とは別に、この豊かな池もご多分に漏れず、外来生物の侵入には手を焼いているようで、ここでも世界は常に動いていることを痛感したのでした。
「うーむ…」と思ったこと ― 2023年06月14日 19時06分12秒
話を蒸し返しますが、プラネタリウム100周年を話題にしたとき、改めてプラネタリウム関連の品をいろいろ探していました。そこで見つけたうちのひとつが、「カール・ツァイス創立125周年」を記念して、1971年に当時の東ドイツで発行された切手です。
でも、現物が届いてじーっと見ているうちに、「あれ?」と思いました。
何だかすでに持っているような気がしたからです。
ストックブックを開いたら、たしかに同じものがありました。
すでに持っているのに気づかず、同じものを買ってしまうというのは、日常わりとあることですが、それはたいてい不注意の為せるわざです。
今回、自分が日頃気合を入れている趣味の領域でも、それが生じたということで、「うーむ…」と思いました。モノが増えたということもあるし、自分が衰えたということもあるんですが、いずれにしても、これは自分の所蔵品を自分の脳でうまく管理できなくなっていることの現れで、これはやっぱり「うーむ…」なのです。
切手に罪はなく、52年前の切手は変わらず色鮮やかで、そのことがまた「うーむ…」です。まあ、今後こういうことがだんだん増えていくんでしょうね。



















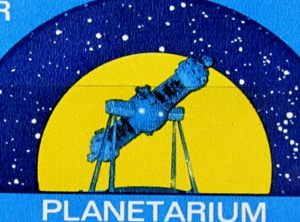
最近のコメント