涼しい星空…カテゴリー縦覧:掛図編 ― 2015年06月01日 20時45分21秒
早くも六月、水無月。
時の流れの速さはもう慣れっこですが、それにしても…と呆れます。
時の流れの速さはもう慣れっこですが、それにしても…と呆れます。
★
さて、今日は来たるべき夏を乗り切るために、涼味満点の星図を載せます。
どうですか、この浅葱色の夜空の風情は。
星図を吊るす棒の長さは125cm。正味のチャート部分だけでも、幅 118cm ありますから、掛図としては大判の部類です。
星図を吊るす棒の長さは125cm。正味のチャート部分だけでも、幅 118cm ありますから、掛図としては大判の部類です。
中央を真一文字に横切る天の赤道をはさんで、南北両天、赤緯にして±60度の範囲の空を描いています。中央をゆるやかに蛇行している曲線は黄道。
古風な星座絵と決別した、そのグラフィカルな星座表現も、またスキッとした涼味を感じさせます(天体は5等星までを表示)。
古風な星座絵と決別した、そのグラフィカルな星座表現も、またスキッとした涼味を感じさせます(天体は5等星までを表示)。
版元はアンティーク星座早見でおなじみの、イギリスのフィリップス社で、1940年のコピーライト表示が見えます。
この星図の見所は、とにもかくにも「涼し気」という点にありますが、掛図として見た場合、ちょっと気になる点があるので、そのことを次回書きます。
(この項つづく)
掛図師のこと ― 2015年06月02日 20時13分32秒
(昨日のつづき)
フィリップス社の掛図で気になるのは、あれは本当に掛図なのか?ということです。いや、もちろん掛図なんですが、当初から掛図として販売されていたのかどうか?
…というのは、あの星図と同じものが、もう1つ手元にあるんですが、見た目がまったく違うんですね。
そちらは、紙表紙を付けた折り図式のものです。
1940年の版権表示も含め、ご覧の通り中身は全く同じ。サイズも同一です。
掛図の方は、星図部分の地色がいくぶん緑がかって見えますが、それは表面にニスが引いてあるせいでしょう。
掛図の方は、星図部分の地色がいくぶん緑がかって見えますが、それは表面にニスが引いてあるせいでしょう。
で、結論から言うと、これは折り図が本来の出版形態で、掛図はそれを購入した人が二次的に加工したものではないか…と推測しています。
(下部をめくり上げたところ)
この掛図は、紙の図をキャンバス地で裏打ちし、木製の軸を打ち付けてあるのですが、イギリス(や他国)には、ちょうど日本の表具師のような、専門の裏打ち職人がいるんじゃないでしょうか。その辺の事情にうといのですが、古い大判の地図にも、布地で裏打ちを施したものが折々あって、あれもそういう職人に個別に頼んだものだと思います。(絵画修復師とか、装幀師とかが、裏打ち商売を兼ねているのかもしれません。)
不埒な天文家とご婦人(後日談)…カテゴリー縦覧:絵葉書編 ― 2015年06月03日 20時41分09秒
今日のカテゴリー縦覧のテーマは「絵葉書」。
絵葉書はこれまでもさんざん載せているので、今さら感がありますけれど、今日はちょっと毛色の変わった話題にします。
絵葉書はこれまでもさんざん載せているので、今さら感がありますけれど、今日はちょっと毛色の変わった話題にします。
★
今から6年前に、こんな絵葉書が登場しました。
天文家をおちょくりの材料にして、そこに艶笑の要素をまぶした、フランス製の古絵葉書で、元記事は以下。
まあ、これは天文家のイマージュとしては最低の部類に属するもので、天文家にとっては不本意でしょうが、見る者を思わずクスリとさせます。
★
で、今日取り上げるのは、この7枚セットの絵葉書を買ってから何年も経った後に、こんな絵葉書を手に入れた…という話題です。
ご覧の通り、これは以前買ったセットには欠けていた「ミッシング・リンク」で、おそらく全体のストーリーの第1枚目を構成するものでしょう。
宛名と通信欄の区画線がない、いわゆるundividedタイプの古い絵葉書。
表面には1905年の年号と、南仏アヴィニョンが差出地であることを示す消印が押されています。その脇のフランス語はよく分かりませんが、どうやら「友よ、早く本復されんことを!」というメッセージのようです。
★
この絵葉書を手に入れたとき、一瞬、「ひょっとして、この8枚は元々同じ持ち主のもので、約百年ぶりに日本で再会を果たしたんじゃないだろうか?」と思いました。
もちろん、そんなはずはなくて、これは単なる偶然のなせるわざでしょう。
事実、これが8枚セットの絵葉書で、後から入手した1枚と、先に買った7枚が対になるものだとしても、そもそも一番「まとも」な絵柄である1枚目は、セットの中で最も使用頻度が高いはずで、となれば、使用済みの1枚目と、1枚目だけが欠けた未使用の7枚セットは、残存の様態として、一番ありふれたものと思えるからです。
★
されど―。
世の中にはこんな話↓もあるので、ひょっとしたら…という思いも捨てきれません。
まあ、真相はすべて歴史の闇の向うです。
世の中にはこんな話↓もあるので、ひょっとしたら…という思いも捨てきれません。
まあ、真相はすべて歴史の闇の向うです。
天文家への警鐘…カテゴリー縦覧:写真・幻燈・スライド編 ― 2015年06月04日 22時42分48秒
昨日の絵葉書は、天文家が天使におちょくられてギャフンとなる…というオチのようでした。天文学がいくらハードサイエンスだ、ビッグサイエンスだと、しかつめらしい顔をして見せても、やはり筒先を空に向けて、星界の消息を覗き見しようとする時点で、なにがしかの怪しさは逃れ難く、異形の者に魅入られたりすることもあるわけです。
(左右の差し渡しは21.5cm、丸窓の径は6cm)
上は19世紀フランスの幻灯種板。
金属ケースの中を、ガラス絵がスライドすることで、絵柄が変るという仕掛けが施されています。
金属ケースの中を、ガラス絵がスライドすることで、絵柄が変るという仕掛けが施されています。
このやっぱりトンガリ帽子の古風な天文家も、最初は熱心に太陽や流れ星を観測していました。そして天界の驚異を目にして、大いに心が満たされていたのです。
しかし、好事魔多し。
彼の視野にはいつか悪魔の跳梁が見えるようになります。
そして、耳には悪魔の囁きが…。
彼の視野にはいつか悪魔の跳梁が見えるようになります。
そして、耳には悪魔の囁きが…。
★
天文家たるもの、第一線の研究者から、ベランダ観望家に至るまで、これは大いに用心せねばなりません。大宇宙は―その恐るべき虚無は―なまなかな気持ちで対峙できるような相手ではありません。
ときには筒先から目を離し、グラスを傾けたり、パイプを握り締めたりする必要があろうというものです。
チョコの星…カテゴリー縦覧:版画・エフェメラ・切手編 ― 2015年06月06日 12時02分40秒
国会の論戦も烈しくなってきました。
国民も大いに注視し、大いに声を上げることが大事かと思います。
国民も大いに注視し、大いに声を上げることが大事かと思います。
とはいえ、天下国家のことと小市民的な喜びは二律背反ではありません。
後者なきところに理想国家なし。
後者なきところに理想国家なし。
…というわけで、大いに小市民的話題に流れますが、今日の主役はエフェメラルなおまけカードです。
星座をモチーフにした12枚セットのカード(サイズは約4cm×5.5cm)。
最近は、細々したカード類は、こういうクリアポケットに整理しているので、ゴチャゴチャ感は減った一方、何となくせせこましい感じがします。いかにも即物的というか、実用的すぎるというか、もう少し風情が欲しいのですが、この辺のバランスはなかなか難しいです。
(薄い紙に印刷されているので、ポケットから出すと、クルッと反り気味になります)
画題は右上から左下にかけて、
○オリオン座と冬の銀河。さらにプロキオンとシリウスの見つけ方
○ちょっと星の結び方が変ですが、さそり座(左) と てんびん座(右)
○はくちょう座(左) と こと座(右)
○ちょっと星の結び方が変ですが、さそり座(左) と てんびん座(右)
○はくちょう座(左) と こと座(右)
カードの裏面。
「世界の驚異 第1集-第10シリーズ『星座』」と、独仏2ヶ国語で表記されています。
「世界の驚異 第1集-第10シリーズ『星座』」と、独仏2ヶ国語で表記されています。
売り手の説明によれば、このカードは、スイスのネスレ社が、チョコバー販促用に、1950年に発行したものだそうです。(ネスレは、1929年にチョコの老舗、ペーター、コーラー、カイエの3社と合併したので、タイトルは4社連名になっています。)
しし座と、その後方に点綴された「かみのけ座」。
このチョコカードは、戦後の1950年発行なのに、依然として古風なクロモ(多色石版)を用いているところが、なかなか奥ゆかしいです。この辺が、実用としてのクロモの最末期ではないでしょうか。
このチョコカードは、戦後の1950年発行なのに、依然として古風なクロモ(多色石版)を用いているところが、なかなか奥ゆかしいです。この辺が、実用としてのクロモの最末期ではないでしょうか。
ふたご座とかに座。
オリオン座拡大。
黒の縁取り、紺碧の空。そこに金の星が光り、銀のラインがスッと星々を結んでいます。色使いがとてもきれいで、星ごころをくすぐります。
黒の縁取り、紺碧の空。そこに金の星が光り、銀のラインがスッと星々を結んでいます。色使いがとてもきれいで、星ごころをくすぐります。
6月はタルホの季節 ― 2015年06月07日 07時31分23秒
さて、2月から続けてきたカテゴリー縦覧も、十分ゴールが見えてきたので、この辺で少し一服します。
★
稲垣足穂の自伝的小説、「弥勒」(初出は1940年)。
明石・神戸で過ごした夢見がちな少年時代を描いた第一部と、後年上京して、物質的窮乏の果てに一種の「宗教的回心」を遂げるまでの心模様を描いた第二部を強引につなげた、なんだか不思議な結構の作品ですが、足穂にとっては、そこに確かな内的必然性があったのでしょう。
その中に、足穂(作中の江美留<エミル>)が6月の情調を感得した、以下のくだりがあります。
〔…〕或る昼休みの教室の黒板に、I は「六月の夜の都会の空」という九字を走り書きして、直ちに消してしまった。「いや何でもありやしない」と彼は甲高い声で江美留に云った。「―でも、ちょっといい感じがしやしないかい?」
なるほど! 六月の夜の都会の空。
この感覚は自分にも確かに在った。夕星を仰いで空中世界を幻視する時、そんな晩方はまた、やがて「六月の夜の都会の空」でなければならない。汗ばんで寝苦しがっているまんまるい地球を抱くようにのしかかっている暗碧の空には、星々がその星座を乱したのであるまいかと疑われるほど狂わしげな位置を採って燦めき、そして時計のセカンドを刻む音と共に地表の傾斜がひどくなって、ついに酸黎のように赤ばんだ月をその一方の地平線におし付けてしまった刻限には、昼間から持ち越しの苦悩に堪えかねた高層建築物たちは、もはや支え切れずに、水晶の群簇(ぐんぞく)のように互いに揺らめきかしいで、放電を取り交わしているのでなければならない。
(稲垣足穂「弥勒」、新潮文庫『一千一秒物語』所収)
なるほど! 六月の夜の都会の空。
この感覚は自分にも確かに在った。夕星を仰いで空中世界を幻視する時、そんな晩方はまた、やがて「六月の夜の都会の空」でなければならない。汗ばんで寝苦しがっているまんまるい地球を抱くようにのしかかっている暗碧の空には、星々がその星座を乱したのであるまいかと疑われるほど狂わしげな位置を採って燦めき、そして時計のセカンドを刻む音と共に地表の傾斜がひどくなって、ついに酸黎のように赤ばんだ月をその一方の地平線におし付けてしまった刻限には、昼間から持ち越しの苦悩に堪えかねた高層建築物たちは、もはや支え切れずに、水晶の群簇(ぐんぞく)のように互いに揺らめきかしいで、放電を取り交わしているのでなければならない。
(稲垣足穂「弥勒」、新潮文庫『一千一秒物語』所収)
「 I 」というのは、足穂と関西学院中学で同窓だった猪原太郎のことで、このエピソードはほぼ事実でしょう。後に足穂が文壇デビューしたのと同じ時期、彼も「猪原一郎」名義で、いくつかの作品を雑誌に発表したそうですが、作家としては大成しませんでした。しかし、その鋭角的な感性は、十代半ばの足穂を存分に刺激し、作家・イナガキタルホの誕生にとって、甚大な影響があったと思います。
(額に関学の三日月マークをつけた、18歳の稲垣足穂(後列中央) 出典:「ユリイカ」2006年9月臨時増刊号)
「弥勒」は、さらに次のような回想に続きます。
Ⅰの云い方を借りれば、その時刻には、どこかの地下室で、競走馬の頭巾のような白覆面の連中がニトログリセリンの桶を前に誓約を立てていることであろうし、またカレー氏の仮装舞踏会から美少年を誘拐した縞の仮面を付けた紳士が、オペラ座前の広場に全速力で自動車を飛ばせていることでもあろう。
江美留自身に依れば、郊外の天文台の円蓋の下に微かな電流の音がして、老天文学者は久し振りで帰ってきた息子を前に、「この瞬間にも多くの世界が滅びまた生れている。わしは、お前のように地球上の人類のことのみを心配しておられぬのじゃ」と云い聞かせていることであろう。いやもっと近代的な大ドームの下で、怪物のようにひっ懸った大望遠鏡を取巻いて、「未来」たちが妖精(エルフ)のように飛び廻っているに相違ない。
― 午後の授業が始まるとすぐに、後ろの席から丸めた紙片が飛んできた。ひろげてみると、「六月の夜の都会の空」と題した詩が書いてあった。遣られた!と江美留は思った。「エーテルは立体的存在の虚空に七色のファンタジーを描き、球と六面体から成立した紳士は、リットルシアターの舞台で直角ダンスを演じて、弁慶縞の観客に泡を吹かせる」というような文句が、そこに連ねられていたからだ。
火竜の乱舞
月が笑う…
生と死のたまゆらに遠い未来を望む飛行者よ
★
江美留自身に依れば、郊外の天文台の円蓋の下に微かな電流の音がして、老天文学者は久し振りで帰ってきた息子を前に、「この瞬間にも多くの世界が滅びまた生れている。わしは、お前のように地球上の人類のことのみを心配しておられぬのじゃ」と云い聞かせていることであろう。いやもっと近代的な大ドームの下で、怪物のようにひっ懸った大望遠鏡を取巻いて、「未来」たちが妖精(エルフ)のように飛び廻っているに相違ない。
― 午後の授業が始まるとすぐに、後ろの席から丸めた紙片が飛んできた。ひろげてみると、「六月の夜の都会の空」と題した詩が書いてあった。遣られた!と江美留は思った。「エーテルは立体的存在の虚空に七色のファンタジーを描き、球と六面体から成立した紳士は、リットルシアターの舞台で直角ダンスを演じて、弁慶縞の観客に泡を吹かせる」というような文句が、そこに連ねられていたからだ。
火竜の乱舞
月が笑う…
生と死のたまゆらに遠い未来を望む飛行者よ
★
当時の足穂は、自らの奔放な思路に、友人の鮮烈なイマジネーションを同化させることで、急速に自らの内に「イナガキタルホ」を胚胎させつつありましたが、その重大な時期に、「六月の夜の都会の空」の一句が、彼に強烈に刷り込まれたことは、その創作活動に絶対的とも言える意味があった…と、根拠は薄弱ですが、何となくそんな気がします。
足穂の後の作品は、すべて「一千一秒物語」の註である…という、足穂自身による有名な言葉がありますが、実は「一千一秒物語」こそ、「六月の夜の都会の空」の謎を追った、足穂の註解ではなかったのか?
★
…というわけで、6月は足穂の季節。
タルホと神戸の話をするには、これ以上ないタイミングです。
ブログの方は、しばらくその話題で続けることにします。
タルホと神戸の話をするには、これ以上ないタイミングです。
ブログの方は、しばらくその話題で続けることにします。
【付記】
神戸には、今もトアロードの西に「ロクガツビル」という不思議な名前の建物があります。そして、神戸のヴンダーショップ、Landschapboek(ランスハップブック)さんは、先日その地階に移転されたばかりで、その不思議なビルの名称の由来を、いつかオーナーの谷さんにうかがえればと思っています。
(そのランスさんも参加されているイベント、「博物蒐集家の応接間」は、明後日までです。)
神戸学序説 ― 2015年06月09日 07時17分17秒
足穂と神戸。
賢治と岩手。
いずれも、その作品世界とホームタウンが不即不離の関係にあった好例です。
足穂にとっての神戸、それは、とびきりハイカラで、エキゾチックで、謎めいて…。
これは彼の脳内で発酵した部分もありますが、現実の神戸もまた、そうした夢を託すのに十分な資質を備えていました。
足穂にとっての神戸、それは、とびきりハイカラで、エキゾチックで、謎めいて…。
これは彼の脳内で発酵した部分もありますが、現実の神戸もまた、そうした夢を託すのに十分な資質を備えていました。
これから私は「星を売る店」(初出1923年)の世界に足を踏み入れようと思うのですが、それに先立って、まず神戸という街の成り立ちに言及しておくことも、タルホ・ワールドの魅力を探る上で、まんざら無駄ではないでしょう。
★
よお、いよいよ神戸行きだってね。
やあ、君か。うん、いよいよ正面からタルホ氏に面会を願おうと思ってね。
そりゃ結構。
でも改めて思うけど、神戸って、よそ者、特に関東の人間には、分かりにくい街だよね。誤解されやすいというか。
別に分かりにくいこともないだろ?人間関係の網の目とか、関西特有の「綾」はあるにしてもさ、要は港町で、ハイカラで…。言ってみりゃ横浜みたいなもんじゃないか。そう割り切って、ずんずん話を進めるさ。
(横浜(左上)と神戸。ウィキメディア・コモンズより)
そこだよ。関東の人はすぐそう言いたがるよね。「神戸って、横浜みたいなもんでしょ」って。異人さんの雰囲気があって、中華街があって、東京と大阪のサイドシティで…。でも、そうじゃない。横浜と神戸じゃずいぶん違う。
へええ。と云うと?
これから話すことは、にわか仕込みの知識だから、そのつもりで聞いてほしい。
よしきた。御説拝聴といこう。
まず神戸と横浜は、幕末に開港し、外国人居留地が設けられたという共通点がある。それが「異人さん」の雰囲気の源流であることは、誰でも知ってるよね。
そりゃ、まあ。
でも、その居留地のあり方が、横浜と神戸じゃずいぶん違ったのさ。横浜は幕府の意向で、外国人をとにかく一定のエリアに押し込んで、日本人と雑居できないような町割りになっていた。言ってみれば、長崎の出島みたいなもんだね。何せ、攘夷騒動で物騒な時代だったし、幕府としても無用な混乱は避けたかったわけさ。
なるほど。
でも神戸は違った。そもそも神戸が開港したのは、攘夷の嵐が過ぎ去った慶応3年(1868)で、旧暦でいうと12月7日。まだ明治改元前だけど、既に「大政奉還」も済み、2日後の12月9日がいわゆる「王政復古の大号令」だから、実質明治といっていい。海沿いの居留地が横浜より狭かった分、外国商人は居留地外に自由に住居を構えることが許されていた。外国人から見れば、よりオープンな雰囲気だったし、日本人から見れば、「異人さん」との距離がぐっと近かったわけさ。
ふーむ。でも明治になれば、横浜だって似たようなものじゃないのかい?
それが違うんだ。神戸の一大特徴はね、これは外国目線の言い方になるけど、横浜よりも、あるいは上海なんかよりも、ずっと「模範的」な居留地だったという点にあるんだ。横浜の都市計画が、幕府や新政府の意向を強く受けたのに対し、神戸はそこに暮らす外国人自身の創意が大きく生かされていた。いわば、街の骨格からして「リトル・ヨーロッパ」だったと云えばいいかな。
へえ、そんなもんかなあ。
街のムードもずいぶん違ってね。横浜では列強各国の意見対立が大きくて、居留地の自治組織が育たなかったのに、神戸では明治32年(1899)に治外法権が撤廃されるまで、各国と日本の代表から成る委員会が結成されて、居留地のことは一貫して合議で決めていた。言ってみれば、ヨーロッパ本国にもないような、理想の国際社会がそこに実現していたんだ。今もトアロードの突き当り、昔トアホテルがあった場所に、デーンと神戸外国倶楽部なんてのがあるけど、あれがその末流に当るのさ。
(明治23年竣工の神戸倶楽部(現・神戸外国倶楽部)。出典同上)
なんでそんな違いが生まれたんだろう?
肝心な点だけど、正直よく分からない。横浜は基本的に輸出港、神戸は輸入港だったという性格の違いが影響したのかもね。当時の横浜からは、金になる生糸や茶がジャンジャン輸出されていたけど、神戸の方はおっとりと「文化を商う」気風があったというかな。
…と、ここまでのところは、足穂が生まれる前の話だけど、足穂が闊歩した頃の神戸というのが、これまた別格でね。
ふむ、大正時代の話だな。
戦争で金儲けなんて、気が進まない話だけど、結果的に第1次大戦で日本はずいぶん潤ったよね。そしてその恩恵は、神戸にいっそう及んだらしいんだ。大正6年(1917)には、貿易額が横浜を超えて、名実ともに日本一の貿易港になったし、そもそもこの時期、神戸が東京、大阪に次いで、日本で3番目に人口の多い都市だったって、君、知ってたかい?
へえ、それは知らなかった。
そして大正12年(1923)の関東大震災。あれで横浜が甚大な被害を受けたことも、神戸にとっては追い風になった。東の方から人や資本が神戸に流入した結果、神戸はますます繁華な地となり、「最強のモダン都市」になったのさ。これこそ、足穂が目にし、肌で感じた神戸なんだよ。
なるほどなあ。
だからね、関東の人に昔の神戸のことを分かってもらおうと思ったら、「横浜と銀座をくっつけて、さらに浅草を寄せたような街」と言って、初めて通じると思うんだ。まあ、地元の人は違うと言うかもしれないけど、今の僕にとって最上の比喩はそんなところさ。
★
…と、脳内の二人は勝手なことを言っていますが、ここに書いたことは、ほぼすべて以下の文献の受け売りです。
■高橋孝次 「旧居留地の文学─「星を売る店」の神戸」
千葉大学人文研究 第38号 pp.55-86.
http://mitizane.ll.chiba-u.jp/meta-bin/mt-pdetail.cgi?cd=00052070
(全文PDFへのリンクが張られていています。)
千葉大学人文研究 第38号 pp.55-86.
http://mitizane.ll.chiba-u.jp/meta-bin/mt-pdetail.cgi?cd=00052070
(全文PDFへのリンクが張られていています。)
高橋氏の上記論文には、「星を売る店」の同時代評も紹介されていて、実に興味深かったです(菊池寛や久米正雄が酷評している一方、芥川龍之介は肯定的に見ていました)。
そして結論部分において、日本文学におけるエキゾチシズムの系譜の中に足穂を定位している箇所が、また大層示唆的でした。私が足穂に惹かれる理由も、それで何となく分かった気がします。つまり、私の中の異土憧憬が足穂のそれと共振すると同時に、私にとっては足穂そのものが、エキゾチックな香りを放つ存在だからでしょう。
★
神戸の歴史を一瞥したところで、さらに「星を売る店の神戸」に踏み込みます。
「星を売る店」の神戸(1) ― 2015年06月10日 19時49分55秒
稲垣足穂の「星を売る店」。
神戸を舞台にした、足穂のいわゆる「神戸もの」の代表作。
主人公である「私」が、神戸の街を徘徊しているうちに、ふと不思議な「星を売る店」を発見する物語。
主人公である「私」が、神戸の街を徘徊しているうちに、ふと不思議な「星を売る店」を発見する物語。
現実が徐々に幻想に置き換わっていく過程が脳髄に心地よく、また星を商う店員に向かって「私」が突如発した、意味ありげな台詞とともに、物語がぶつっと終る切断感も印象的です。そして何よりも「星を売る店」のきらきらした描写―。あれを読んで、実際にあの店を訪問したいと願わない人は、少ないのではありますまいか。
本作は新潮文庫版の『一千一秒物語』にも収録されていて、この本は先月の新潮文庫フェア「ピース又吉がむさぼり読む新潮文庫20冊」というので取り上げられたため、本屋さんの店頭に平積みになっていました。足穂が平積みされている光景にビックリしましたが、ビックリついでに、私もすかさず買いました。
新潮文庫だと20ページちょっとの短編です。
初出は大正12年(1923)の「中央公論」7月号で、その後、大正15年(1926)に金星堂から単行本『星を売る店』として出版されました。
初出は大正12年(1923)の「中央公論」7月号で、その後、大正15年(1926)に金星堂から単行本『星を売る店』として出版されました。
ここで一つ問題となるのは、「星を売る店」は、作者・足穂自身が後に手を加えたため、現行の形態と初出形態がずいぶん異なることです。まあ、足穂は自作に手を入れることを好んだため、大半の作品がそうなのですが、「星を売る店」の場合は、ちょっとやそっとの改変ではなく、初出時は、現在目にする形のほぼ3倍のボリュームがありました。こうなると、ちょっとした中編小説で、それを削りに削ったのが、現行のヴァージョンというわけです。
さらに個人的に問題になるのは、私はその初出形態を見たことがないことです。
断片的情報から判断すると、どうも初出形態の方が、神戸の街の描写も、主人公である「私」の行動も、より具体的かつ詳細であり、神戸の街に沈潜する良き手引きとなってくれそうなのですが、これは将来、金星堂版『星を売る店』の復刻版でも出たときの楽しみにとっておくことにして、ここでは現行形態に基づいて、作品世界に入り込むことにします。
断片的情報から判断すると、どうも初出形態の方が、神戸の街の描写も、主人公である「私」の行動も、より具体的かつ詳細であり、神戸の街に沈潜する良き手引きとなってくれそうなのですが、これは将来、金星堂版『星を売る店』の復刻版でも出たときの楽しみにとっておくことにして、ここでは現行形態に基づいて、作品世界に入り込むことにします。
(この項ゆっくりと続く)
「星を売る店」の神戸(2)…すみれ色のバウ ― 2015年06月11日 20時40分38秒
日が山の端に隠れると、港の街には清らかな夕べがやってきた。私は、ワイシャツを取り替え、先日買ったすみれ色のバウを結んで外へ出た。
これが「星を売る店」の書き出しです。
港町、清らかな夕べ、洗い立てのワイシャツ、そして菫色のボウタイ。
おそらく、こうしたものが足穂にとって神戸を象徴するものであり、この作品の基調音を奏でるものなのでしょう。
港町、清らかな夕べ、洗い立てのワイシャツ、そして菫色のボウタイ。
おそらく、こうしたものが足穂にとって神戸を象徴するものであり、この作品の基調音を奏でるものなのでしょう。
それに何と言っても、すみれ色はタルホ色ですから(彼はいろいろなところで、菫色を持ち上げています)、足穂の神戸を訪ねるには、ぜひ「すみれ色のバウ」をしなければいけません。
ただ、世間に紫色の蝶ネクタイは、いくらも売っていますけれど、本気であの世界に入るには、やはりそれなりの身ごしらえが必要です。
そう思って、ネット上を徘徊した末に見つけたのがこれ。
そう思って、ネット上を徘徊した末に見つけたのがこれ。
戦前、おそらく1930年代のシルクのボウタイ。
古いものなので、ちょっとヨレっとしていますが、これは何とかしようがあるでしょう。
古いものなので、ちょっとヨレっとしていますが、これは何とかしようがあるでしょう。
この「すみれ色」は、赤と青を混ぜて織り出してあります。
原作では「バウを結んで」とあるので、シュルシュルと上手に結び目を作ったのでしょうが、これは最初から結んであるのを、クリップでカラーに留めるだけのタイプ。恥ずかしながら、私はこれまでの人生で蝶ネクタイをしたことは、ただの一度もありませんが、これなら簡単です。
原作では「バウを結んで」とあるので、シュルシュルと上手に結び目を作ったのでしょうが、これは最初から結んであるのを、クリップでカラーに留めるだけのタイプ。恥ずかしながら、私はこれまでの人生で蝶ネクタイをしたことは、ただの一度もありませんが、これなら簡単です。
さて、身ごしらえが出来たところで、涼しい夕風の吹き上げてくる、神戸の山手へ―。
★
…とまあ、こんなふうに瑣末なことにこだわりつつ、星を売る店を目指します。
それにしても、この4月以来の「星店」への傾倒ぶりというか、迷妄ぶりは、我ながら大したものです。
それにしても、この4月以来の「星店」への傾倒ぶりというか、迷妄ぶりは、我ながら大したものです。
このボウタイは、イギリスの人から買いました。
他にも、日本から西回りに、中国、インド、レバノン、エジプト、ブルガリア、ハンガリー、ドイツ、イタリア、フランス、そしてアメリカと、私は電子と情報の流れに乗って、この惑星のあちこちを巡り、「星店」に至る手立てを求め続けました。これほど短期間に、これほど多くの売り手と交渉したのは、かつてないことです。
他にも、日本から西回りに、中国、インド、レバノン、エジプト、ブルガリア、ハンガリー、ドイツ、イタリア、フランス、そしてアメリカと、私は電子と情報の流れに乗って、この惑星のあちこちを巡り、「星店」に至る手立てを求め続けました。これほど短期間に、これほど多くの売り手と交渉したのは、かつてないことです。
益体もない吹聴をして恐縮ですが、「星店」ファンであれば、このつまらぬ自慢にも耳を傾けて下さることでしょう。少なくともそれによって、この夕べの散歩に有ってほしい異国の情調は、十分備わることになったのですから。
(この項つづく)
「星を売る店」の神戸(3) ― 2015年06月13日 10時27分15秒
梅雨の中休み。心の中の景色は爽やかな夕晴れです。
以下、前回の引用箇所に続く文章。
以下、前回の引用箇所に続く文章。
青々と繁ったプラタナスがフィルムの両はしの孔のようにならんでいる山本通りに差しかかると、海の方から、夕凪時にはめずらしく涼しい風が吹き上げてくる。教会の隣りのテニスコートでは、グリーンやピンクの子供らがバネ仕掛の人形のように縄飛びしている。樅の梢ごしに見える蔦をからませたヴェランダからはピアノのワルツが洩れてくる。
みずみずしい神戸の山ノ手の風景です。
(明治前半とおぼしい神戸の幻燈スライド。ガラスの向うに広がる明るい世界)
先日引用させていただいた(http://mononoke.asablo.jp/blog/2015/06/09/)、高橋孝次氏の旧居留地と足穂に関する論文には、「星を売る店」の初出形態が、断片的に引用されていますが、それによると、最初は上の描写に続いて、以下のような文章が続いていたそうです(繰り返し記号を通常の文字に改めて再引用)。
「やはり神戸はいいなあ」と、私は打ち水をした歩道の上を、コツコツ歩きながら、あたりを見まわした。ほんとうに、こんな夕方の一ときをハバナの細巻でもくゆらして、トレアドルソングの口笛でも吹きながら散歩するのは、何とも云へぬ清新な、そしてはいからな気分がするものだ。
やはり神戸はいい、清新な、ハイカラな気分がする…とまで説明的に言ってしまうと、文章の技巧として拙いので、後で削ったのだと思いますが、これが足穂の素直な気持ちなのかもしれません。
★
…と言いつつも、どうでしょう、皆さんはこの書き出し部分を読んで、何か違和感を覚えないでしょうか? 私は上の箇所が、余りにも神戸のスレテオタイプな描写になっているのが気になりました。何だか芝居の書き割りめいた感じがします。
足穂はハイカラ神戸を素朴に讃美すると見せかけて、実は既に読者を術中にはめようとしているのではないか? どうもそんな気がするのです。
主人公の「私」は、この後トアロード沿いに、港の方に坂を下っていきます。
そこにも書き割り臭い「平面描写」が顔を出します。
そこにも書き割り臭い「平面描写」が顔を出します。
坂下には、自動車や電車の横がおや群衆やがごたごたもつれ合って、国々の色彩が交錯した海港のたそがれ模様が織り出されている。その上方、坂の中途から真正面の位置に、倉庫? それとも建築中のビルディングか、何やら長方形と三角形のつみ重なりが見えて、そこへ山の合間から射しているらしい夕陽が桃色に当っている。いずこも青ばんでいる景色の中で、視線正面の一廓だけがキネオラマの舞台のように浮き出し、幾何学的模様に見える形と影の向うに、赤、黄、青の船体とエントツがひっかかっている。
さらに、散歩の途中で出会った友人Nと食事を済ませ、再び一人で夜の街を歩き出した「私」の目には、妙にボンヤリとした光景が映ります。
さらに、散歩の途中で出会った友人Nと食事を済ませ、再び一人で夜の街を歩き出した「私」の目には、妙にボンヤリとした光景が映ります。
行手の遠い辻に現れてすぐどこかへ消えてしまうギラギラ眼玉の自動車や、また前後からゴーッと通りすぎて行く明々したボギー電車の中にも、非常にきれいな夢―何かそんな感じの者が乗っているようだ。二条の軌道のまんなかにつづいた鉄柱の上にある二箇の燈火が、やはり二列の光の点線を空間に引いて、向うの坂の所から鋭角をえがいて下方へ折れまがっている。いつか映画で観た表現派の街を歩いているようだ。
私は、夢だったか、気まぐれな空想であったか、自分がちょうどそんな怪奇映画の都会にはいっていたことをよび起こした。
私は、夢だったか、気まぐれな空想であったか、自分がちょうどそんな怪奇映画の都会にはいっていたことをよび起こした。
「キネオラマの舞台」に続いて、今度は「表現派の街」です。
ここで言う表現派の怪奇映画とは、先ほど共に食事をした友人Nが洩らした「こりゃカリガリ博士の馬車じゃねえか」というセリフから、カリガリ博士の物語だと容易に想像が付きます。夜の街を舞台に、夢と現実が溶け合い、話者の視点が複雑に入り組んだ、この狂気と幻想に彩られた映画(日本公開は大正10年=1921)は、「星を売る店」を理解する上で、重要な鍵だと思います。
さらに言えば、「軌道沿いに燈火が形作る2列の光点」は、冒頭の「プラタナスがフィルムの両はしの孔のようにならんでいる」風景と照応しており、この作品は最初から全てフィルムの中に仕組まれていたんじゃないか…という気がするのです。
そして、フィルムの登場人物めいた「私」は、周囲に漂う「いつにないふしぎさ」、「口では云えぬファンタジー」の霧の向うに、ついに「星を売る店」を見出すわけです。
(大正時代のハイカラ神戸。ブルーインクを使った繊細な石版刷りで、文字通り「いずこも青ばんでいる景色」)
(長くなったので、ここでいったん記事を割ります。)






















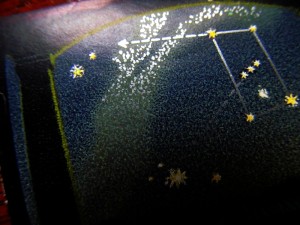









最近のコメント