ガリレオの指 ― 2010年06月18日 19時32分01秒
銀河模型の話が続いていますが、ちょっと話が単調なので、他の話題を割り込ませます。といっても、全く関係がないわけもでもなくて、銀河が星の群れだと発見した人、すなわちガリレオ・ガリレイ(1564-1642)の話題。
★
先日、例によってメーリングリスト経由で、変わった記事を読みました。「ガリレオの指がフィレンツェの博物館に!」というニュースです(原文はこちら)。
検索してみたら、日本でも既に報じられていました。
■ゆかしメディア:「偶然落札したガリレオの指、フィレンツェの博物館で展示」
短信なので全文引用させていただきます。
「17世紀のイタリアの天文学者、ガリレオ・ガリレイの2本の指が、
8日よりフィレンツェのガリレオ博物館で展示されている。
展示されているのは、1642年に77歳で死去したガリレオの右手の
親指と中指。死後約100年後の1737年に行われた埋葬式典で、
フィレンツェのサンタ・クローチェ教会に遺体を移動させた時に、
ガリレオの賛美者たちによって指・歯・脊椎が切り取られていた。
その後、ガリレオの指は何人もの美術コレクターの手にわたる
うちに行方不明に。脊椎は、ガリレオが20年間講師を務めたパドワ
大学で保管されていた。今回展示される親指と中指は、昨年ある
コレクターがオークションで他の美術品と一緒に偶然落札したという。
ガリレオ博物館は、2年間閉鎖されていたフィレンツェの科学歴史
博物館が、8日に名称を変えてリニューアルオープンしたもの。
ガリレオの他の指は以前からこの博物館に常設展示されていた。
指のほかにガリレオの望遠鏡なども展示されている。」
★
日本にも即身仏や仏舎利信仰がありますが、死後100年も経たない、まだ生々しさの感じられる遺体の指をポキンと折って珍蔵するというのは、現代の感覚からすれば、怪奇千万です。人間の肉体までもが、大っぴらにコレクションの対象となったヴンダーカンマー的志向のなせる業なのでしょうか。

(↑ガリレオ博物館のサイトより)
ガラスの球に収められた、ガリレオの右中指。
いくら大偉人のものとはいえ、ふつうに考えればあまり気色のいい品ではありませんが、これこそ400年前に望遠鏡を握りしめ、銀河の正体にわなないた、まさにその指なのです。かつては紛れもなく血が通い、星を指し、ペンを走らせた指!
それを思えば、単に黴くさいばかりの、猟奇的な品とも言えないように思います。
世界のヴンダーショップ(7) ― 2010年05月28日 18時42分06秒

博物学からヴンダー系の話題が続いていますが、今日は「世界のヴンダーショップ」第7弾 (これまでの6店舗については、付記を参照)。
今回はイタリアのトリノにあるお店、「ノーチラス」です。
■Nautilus : Antique Scientific Instruments & Old Oddities
http://www.thenautilus.it/Index_Inglese.html
これまでアメリカ、オーストラリア、フランス、日本と、さまざまなヴンダーショップを見てきましたが、今回はイタリア。もう“イタリア”と聞くだけで、濃艶・華麗・凄惨…そんな文字が脳裏をかすめます。何だか「濃い」感じです。サイトデザインからして、赤と黒を基調としたまがまがしい表情。
メニューから「Shop」に入ると、店内を撮影した画像がずらっとあって、店の雰囲気がよくわかります。まさに店舗の体裁をとったヴンダーカンマーそのもの。予想にたがわず「濃い」です。
メニューの「Catologue」を見ると、その取扱品目の多さにも驚きます。ふつうの理系骨董(アンティーク顕微鏡とか)も置いてありますが、それ以上に医療・解剖系の充実ぶりが素晴らしく、各種の剥製もバンバン扱っています。「Old Oddities」を看板に掲げているだけあって、いわゆる理系骨董の範疇に収まらない珍物(奇怪な人形など)も多いようです。
私はイタリアに行ったことがないので、全てイメージだけで書いていますが、“とば口”のトリノですら、このありさまですから、ヴェネチア、フィレンツェ、ローマと、さらにイタリアの懐深く踏み込んだら、いったいどんな店が待ちかまえているのか…想像するだに恐ろしいことです。
【付記:世界のヴンダーショップ、過去記事一覧】
(1)Evolution(アメリカ) http://mononoke.asablo.jp/blog/2009/03/25/
(2)Wunderkammer(オーストラリア) http://mononoke.asablo.jp/blog/2009/03/27/
(3)Librairie Alain Brieux(フランス) http://mononoke.asablo.jp/blog/2009/07/19/
(4)Claude Nature(フランス) http://mononoke.asablo.jp/blog/2009/08/22/
(5)The Bone Room(アメリカ) http://mononoke.asablo.jp/blog/2009/10/21/
(6)Landschapboek(日本) http://mononoke.asablo.jp/blog/2009/11/15/
今回はイタリアのトリノにあるお店、「ノーチラス」です。
■Nautilus : Antique Scientific Instruments & Old Oddities
http://www.thenautilus.it/Index_Inglese.html
これまでアメリカ、オーストラリア、フランス、日本と、さまざまなヴンダーショップを見てきましたが、今回はイタリア。もう“イタリア”と聞くだけで、濃艶・華麗・凄惨…そんな文字が脳裏をかすめます。何だか「濃い」感じです。サイトデザインからして、赤と黒を基調としたまがまがしい表情。
メニューから「Shop」に入ると、店内を撮影した画像がずらっとあって、店の雰囲気がよくわかります。まさに店舗の体裁をとったヴンダーカンマーそのもの。予想にたがわず「濃い」です。
メニューの「Catologue」を見ると、その取扱品目の多さにも驚きます。ふつうの理系骨董(アンティーク顕微鏡とか)も置いてありますが、それ以上に医療・解剖系の充実ぶりが素晴らしく、各種の剥製もバンバン扱っています。「Old Oddities」を看板に掲げているだけあって、いわゆる理系骨董の範疇に収まらない珍物(奇怪な人形など)も多いようです。
私はイタリアに行ったことがないので、全てイメージだけで書いていますが、“とば口”のトリノですら、このありさまですから、ヴェネチア、フィレンツェ、ローマと、さらにイタリアの懐深く踏み込んだら、いったいどんな店が待ちかまえているのか…想像するだに恐ろしいことです。
【付記:世界のヴンダーショップ、過去記事一覧】
(1)Evolution(アメリカ) http://mononoke.asablo.jp/blog/2009/03/25/
(2)Wunderkammer(オーストラリア) http://mononoke.asablo.jp/blog/2009/03/27/
(3)Librairie Alain Brieux(フランス) http://mononoke.asablo.jp/blog/2009/07/19/
(4)Claude Nature(フランス) http://mononoke.asablo.jp/blog/2009/08/22/
(5)The Bone Room(アメリカ) http://mononoke.asablo.jp/blog/2009/10/21/
(6)Landschapboek(日本) http://mononoke.asablo.jp/blog/2009/11/15/
乙女 vs. 博物学 ― 2010年05月01日 18時44分38秒
ついに5月。ゴールデン・ウィークなれども、世間に迎合することなく、部屋に沈殿。
★
(昨日のつづき)
すっきりとした理科室も良いものです。
なんだか、サイエンスの涼しい風が吹き抜けるようで。
しかし、それだけではちょっと物足りない。
この辺が、理科と並んで―あるいは理科以上に―「理科室」が好きという変則的な嗜好のなせるわざ。
理科室好きとしては、下の写真のような、こってりした味わいも欲しいのです。
★
(昨日のつづき)
すっきりとした理科室も良いものです。
なんだか、サイエンスの涼しい風が吹き抜けるようで。
しかし、それだけではちょっと物足りない。
この辺が、理科と並んで―あるいは理科以上に―「理科室」が好きという変則的な嗜好のなせるわざ。
理科室好きとしては、下の写真のような、こってりした味わいも欲しいのです。
■ソフィ・ジェルマン校 博物学室(パリ、1910年頃)
ソフィ・ジェルマン校は1882年に女子校として創設されました。現在の校名はLycée Sophie Germain。キャプションにある Ecoles primaire supérieure というのは昔の学制による名称で、そのまま訳せば高等小学校ですが、たぶん日本の女学校に相当する教育機関だと思います。
剥製や骨格標本がなかなか充実していますね。右手の骨格標本は、当時のことですから、たぶん本物の人骨でしょう。手前の陳列ケースには、鉱物や化石が並んでいるようです。左手前の筒状のものは、きっとデロール製の博物掛図にちがいありません。いいなあ…
一口に「理科室」といっても、実験室、講義室、標本室…と、いろいろな用途の部屋がありうるので、昨日の絵葉書とは単純に比較できませんが(昨日の学校にも上のような部屋が別にあるのかもしれません)、それにしてもヴンダー濃度が高い。あんまり整理されすぎずに、ゴチャゴチャっとしているのも素敵です。
こんな小部屋がわが家にあったらなあ…と、毎度のことですが、思わずにはいられません。
【付記】
上の絵葉書とは別テイクの写真(撮影時期は異なります)を含む、往時のソフィ・ジェルマン校の様子が同校のサイトに載っています(http://lyc-sophie-germain.scola.ac-paris.fr/Historique/1882.html)。
うーむ、乙女の園ですねえ。日本の女学校文化の源流はこの辺りにあるんでしょうか。でも、女子の中・高等教育に関しては、日本も西洋もあまり時間差がなさそうなので、乙女文化は世界同時多発的に生れたのかもしれません。
江戸のダビンチたち ― 2010年04月20日 21時52分54秒
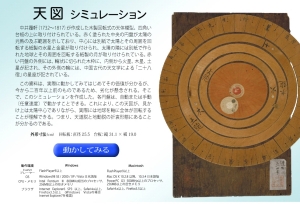
(↑中井履軒が手作りした「天図」、いわば素朴な和製オーラリーです。履軒を顕彰するサイト、“WEB懐徳堂”では、この天図の動きを画面上で見ることができます。以下のリンク先の右側にあるメニューから、「天図シミュレーション」を選択してください。http://kaitokudo.jp/navi/index.html)
★
昨日の記事の最後に挙げたリンク先(http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/1997Archaeology/02/20400.html)には、冒頭、西野嘉章氏(東大総合研究博物館)の文章が掲載されています(「医学解剖と美術教育:「脇分」から「藝用解剖学」へ」)。
その巻末の注釈を見ていて、次の記載が目にとまりました。1771(明和8)年、杉田玄白と前野良沢が女性の腑分けを参観したことに始まる、近代解剖学の歴史を記述した章に付けられた注です。
“[25]儒学者の中井履軒までもが、『解体新書』の刊行
と同じ年、友人の麻田剛立の人体・動物解剖実験の結果
を纏めた『越俎弄筆』を出している。こちらの底本は
パルヘイン著簡易医学書『巴爾靴員解体書』のようである。”
麻田剛立(あさだごうりゅう、1734-1799)は、このブログにも何度か登場しました。出身地・大分では「Goryu」という焼酎まで作られているとか、そんな類の記事でしたが、もちろん彼はお酒に名前を残しているだけの人ではなくて、独力でケプラーの第3法則を(再)発見したともささやかれる、江戸時代の天才天文学者。弟子たちにも俊才・逸材が多く、剛立はいわば1つのスクール(学統)を率いて、日本の天文学・暦学を大いに振興した立役者です。
その名に、ひょんなところで出くわし、オッと思いました。
まあ、剛立は生業が医者なので、解剖を手掛けても特に異とするに足りませんが、それにしても…という感じです。さらにまた、その友人・中井履軒(なかいりけん、1732-1817)という人は、天文学や博物学全般に強い興味を示した異能の儒学者。
剛立といい、履軒といい、「万能人」を輩出する時間と空間が、どうもこの世にはあるような気がします。
中井履軒と『越俎弄筆』のことを検索していたら、下のような大変分かりやすいまとめがありました。
■眠い人の戯れ言垂れ流しブログ: 商いは学問に通ず(by 「眠い人」様)
http://nemuihito.at.webry.info/201003/article_17.html
麻田剛立や中井履軒をはじめ、木村蒹葭堂、服部永錫、山片蟠桃、高橋至時、間重富、橋本宗吉といった、きら星のような人間模様を見るにつけ、18世紀後期の大阪の奥深さ、すごさを感じます。
(そういえば夕べ、橋本府知事がテレビで、恐い顔をして「大阪都構想」を語っていましたが、まあ、そんなに口角泡を飛ばして語らずとも、もっと鷹揚に、大人(たいじん)の風格を示してはどうかと、当時の大阪のことを考えながら思いました。)
★
昨日の記事の最後に挙げたリンク先(http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/1997Archaeology/02/20400.html)には、冒頭、西野嘉章氏(東大総合研究博物館)の文章が掲載されています(「医学解剖と美術教育:「脇分」から「藝用解剖学」へ」)。
その巻末の注釈を見ていて、次の記載が目にとまりました。1771(明和8)年、杉田玄白と前野良沢が女性の腑分けを参観したことに始まる、近代解剖学の歴史を記述した章に付けられた注です。
“[25]儒学者の中井履軒までもが、『解体新書』の刊行
と同じ年、友人の麻田剛立の人体・動物解剖実験の結果
を纏めた『越俎弄筆』を出している。こちらの底本は
パルヘイン著簡易医学書『巴爾靴員解体書』のようである。”
麻田剛立(あさだごうりゅう、1734-1799)は、このブログにも何度か登場しました。出身地・大分では「Goryu」という焼酎まで作られているとか、そんな類の記事でしたが、もちろん彼はお酒に名前を残しているだけの人ではなくて、独力でケプラーの第3法則を(再)発見したともささやかれる、江戸時代の天才天文学者。弟子たちにも俊才・逸材が多く、剛立はいわば1つのスクール(学統)を率いて、日本の天文学・暦学を大いに振興した立役者です。
その名に、ひょんなところで出くわし、オッと思いました。
まあ、剛立は生業が医者なので、解剖を手掛けても特に異とするに足りませんが、それにしても…という感じです。さらにまた、その友人・中井履軒(なかいりけん、1732-1817)という人は、天文学や博物学全般に強い興味を示した異能の儒学者。
剛立といい、履軒といい、「万能人」を輩出する時間と空間が、どうもこの世にはあるような気がします。
中井履軒と『越俎弄筆』のことを検索していたら、下のような大変分かりやすいまとめがありました。
■眠い人の戯れ言垂れ流しブログ: 商いは学問に通ず(by 「眠い人」様)
http://nemuihito.at.webry.info/201003/article_17.html
麻田剛立や中井履軒をはじめ、木村蒹葭堂、服部永錫、山片蟠桃、高橋至時、間重富、橋本宗吉といった、きら星のような人間模様を見るにつけ、18世紀後期の大阪の奥深さ、すごさを感じます。
(そういえば夕べ、橋本府知事がテレビで、恐い顔をして「大阪都構想」を語っていましたが、まあ、そんなに口角泡を飛ばして語らずとも、もっと鷹揚に、大人(たいじん)の風格を示してはどうかと、当時の大阪のことを考えながら思いました。)
本朝人体模型縁起 ― 2010年04月19日 21時56分03秒

エディさんからの連想で、人体模型の話をさらに続けます。
★
人体模型の歴史に依然として関心を抱いているのですが、それを強く刺激される記事を目にしました。例の奇想系ブログ、Curious Expeditions が今度もソースです。
■Curious Expeditions:From the Voyage Vaults, Object No. 28
http://curiousexpeditions.org/?p=861
これぞ、あっと驚く日本式人体模型。
アメリカの国立保健医学博物館(National Museum of Health and Medicine;NMHM)の展示品だそうです。記事中の説明によれば、
◆ ◇
「17世紀から18世紀にかけて、日本古来の医師たち(彼らは当時、
身体の働きをアジアの伝統医学や医術に従い、その外観から
推論しようと試みていた)は、患者に薬の効果を説明するのに、
人形を用いた。
この模型は、様々な器官を正確に表現したものというよりは、一連の
フローチャートを示したものである。ここには「虚」(陽)の器官として、
胆嚢、胃、大腸、小腸、膀胱、そして身体を巡るエネルギーの流れ
を調節する「3重の燃焼・加熱システム」があり、さらに「実」(陰)の
器官として心臓、肺、肝臓、脾臓、腎臓があった。」
◇ ◆
“triple burning or heating system”、「3重の燃焼・加熱システム」とは、漢方で云うところの「三焦」のこと。三焦は、五臓六腑のうちの「腑」の1つで、ウィキペディアにも記述(↓)がありますが、実体のない謎の器官。
■Wikipedia「三焦」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%84%A6
上の説明にもある通り、五臓六腑のうち主要器官である「臓」は<陰>、補助器官である「腑」は<陽>と見るのが、中国古来の考え方だそうです。
★
さて、私は上の説明を読んで、一寸不思議に思いました。
説明文の記述では17~18世紀云々とあるのですが、この2体の人形は、それほど古いものとは到底思えないからです。
下の横たわっている人形は、その面貌や肌の色からして、明らかに幕末~明治期の「生き人形」系の作品でしょう。上のどっかと腰を下ろした人形は、色合いこそ伝統的な白色胡粉仕上げですが、そのぱっちりした目の表現からすると、これまた幕末期をさかのぼるものではないように思います(それ以前の人形の目は、概ね切れ長の「引き目」)。
たしかに古い時代にも、人体模型と呼びうるものはあって、たとえば東大の医学部には、江戸時代初期に遡る紙塑製の「胴人形」と呼ばれる、経絡を表現した人形が保管されており、また胴人形自体はさらに古くからあったとも言われます(※)。
ただ、江戸時代前期に、すでに<解剖型>の人体模型があったのかどうか。あったとすれば、我が国の人体模型史において見逃せない事実ですが、私は未だその作例を知りません。
★
で、私なりにこの2体の人体模型の素性を推測してみます。
まず、下の横たわっている方の模型(生き人形風のもの)。これは、妊産婦を表現していますが、傍らに置かれた内臓(腸など)の表現がリアルなので、これは漢方医系の作品ではなしに、西洋医学系の人体模型を、日本で真似て作ったものだと思います。島津製作所標本部(現・京都科学)などが、明治中期に精巧な解剖模型の製作を始める以前の、きわめて珍しい作例だと言えます。
いっぽう、坐像の方は確かに漢方系の解剖模型ですが、こうした模型表現は実は意外に新しいのではないか…というのが私の想像です。まあ、特に物証はないんですが、デザインや発想が、いかにも西洋の解剖模型と類似しているので。
連想するのは、当時西洋の惑星運行模型(オーラリー)に対抗して、須弥山を中心とした仏教宇宙模型を仏僧がからくり師に命じて作らせたことです。それと同じように、この人体模型も、蘭方(あるいは更に新しい西洋医学)の隆盛に対抗して、幕末の漢方医が人形師に作らせたものではないだろうかと、そんなことを考えました。だとすれば、それはそれでまた興味深い事実です。
日本独自の人体模型の展開―。
興味と謎はなかなか尽きそうにありません。
(※)以下のリンク先をずっと下までスクロールすると、その実物写真が載っています。
東京大学創立百二十周年記念東京大学展
学問の過去・現在・未来 第一部「学問のアルケオロジー」第2章
http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/1997Archaeology/02/20400.html
★
人体模型の歴史に依然として関心を抱いているのですが、それを強く刺激される記事を目にしました。例の奇想系ブログ、Curious Expeditions が今度もソースです。
■Curious Expeditions:From the Voyage Vaults, Object No. 28
http://curiousexpeditions.org/?p=861
これぞ、あっと驚く日本式人体模型。
アメリカの国立保健医学博物館(National Museum of Health and Medicine;NMHM)の展示品だそうです。記事中の説明によれば、
◆ ◇
「17世紀から18世紀にかけて、日本古来の医師たち(彼らは当時、
身体の働きをアジアの伝統医学や医術に従い、その外観から
推論しようと試みていた)は、患者に薬の効果を説明するのに、
人形を用いた。
この模型は、様々な器官を正確に表現したものというよりは、一連の
フローチャートを示したものである。ここには「虚」(陽)の器官として、
胆嚢、胃、大腸、小腸、膀胱、そして身体を巡るエネルギーの流れ
を調節する「3重の燃焼・加熱システム」があり、さらに「実」(陰)の
器官として心臓、肺、肝臓、脾臓、腎臓があった。」
◇ ◆
“triple burning or heating system”、「3重の燃焼・加熱システム」とは、漢方で云うところの「三焦」のこと。三焦は、五臓六腑のうちの「腑」の1つで、ウィキペディアにも記述(↓)がありますが、実体のない謎の器官。
■Wikipedia「三焦」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%84%A6
上の説明にもある通り、五臓六腑のうち主要器官である「臓」は<陰>、補助器官である「腑」は<陽>と見るのが、中国古来の考え方だそうです。
★
さて、私は上の説明を読んで、一寸不思議に思いました。
説明文の記述では17~18世紀云々とあるのですが、この2体の人形は、それほど古いものとは到底思えないからです。
下の横たわっている人形は、その面貌や肌の色からして、明らかに幕末~明治期の「生き人形」系の作品でしょう。上のどっかと腰を下ろした人形は、色合いこそ伝統的な白色胡粉仕上げですが、そのぱっちりした目の表現からすると、これまた幕末期をさかのぼるものではないように思います(それ以前の人形の目は、概ね切れ長の「引き目」)。
たしかに古い時代にも、人体模型と呼びうるものはあって、たとえば東大の医学部には、江戸時代初期に遡る紙塑製の「胴人形」と呼ばれる、経絡を表現した人形が保管されており、また胴人形自体はさらに古くからあったとも言われます(※)。
ただ、江戸時代前期に、すでに<解剖型>の人体模型があったのかどうか。あったとすれば、我が国の人体模型史において見逃せない事実ですが、私は未だその作例を知りません。
★
で、私なりにこの2体の人体模型の素性を推測してみます。
まず、下の横たわっている方の模型(生き人形風のもの)。これは、妊産婦を表現していますが、傍らに置かれた内臓(腸など)の表現がリアルなので、これは漢方医系の作品ではなしに、西洋医学系の人体模型を、日本で真似て作ったものだと思います。島津製作所標本部(現・京都科学)などが、明治中期に精巧な解剖模型の製作を始める以前の、きわめて珍しい作例だと言えます。
いっぽう、坐像の方は確かに漢方系の解剖模型ですが、こうした模型表現は実は意外に新しいのではないか…というのが私の想像です。まあ、特に物証はないんですが、デザインや発想が、いかにも西洋の解剖模型と類似しているので。
連想するのは、当時西洋の惑星運行模型(オーラリー)に対抗して、須弥山を中心とした仏教宇宙模型を仏僧がからくり師に命じて作らせたことです。それと同じように、この人体模型も、蘭方(あるいは更に新しい西洋医学)の隆盛に対抗して、幕末の漢方医が人形師に作らせたものではないだろうかと、そんなことを考えました。だとすれば、それはそれでまた興味深い事実です。
日本独自の人体模型の展開―。
興味と謎はなかなか尽きそうにありません。
(※)以下のリンク先をずっと下までスクロールすると、その実物写真が載っています。
東京大学創立百二十周年記念東京大学展
学問の過去・現在・未来 第一部「学問のアルケオロジー」第2章
http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/1997Archaeology/02/20400.html
秘密の人体模型、あるいは人体模型の秘密 ― 2010年04月17日 19時53分42秒
ゆうべ、かすてんさんが目を留められた“人体ねえさん”(→昨日のコメント参照)。
この1/2スケールの人体模型は、商品名を「エディーJr」といい、わが家ではエディさんと呼んでいます。
この1/2スケールの人体模型は、商品名を「エディーJr」といい、わが家ではエディさんと呼んでいます。
エディさんともずいぶん長い付き合いで、今の奥さんと結婚した年か、その翌年ぐらいに買ったので、奥さんと同じぐらいの古馴染みになるわけです。
ある日、嫉妬に狂った奥さんがエディさんを粉々に打ち砕いて…というような事件が起きていたら夢野久作的で面白いんですが、そんなこともなくこれまで円満にやってきました。
エディさんは、窓際に置かれていた時期が長かったせいで、気付いた時には赤い塗料がすっかり退色して、筋肉が真っ白になっていました。改めてみると不思議な感じです。
人体模型なので、こんな風にパカッと頭部が外れます。

頭部の結合がごく緩いために、地震がくるとすぐに<ひとり唐竹割り状態>となって、見る者を驚かせます。
★
さて、エディさんは、わりと中性的で理知的な顔立ちをしていますが、彼女の最大の秘密は何か?
その答は上の写真に写っています(エディさんの足元)。
なんと、エディさんは生殖器のパーツを付け替えると男性にもなれるのです。たぶん、男性としてディスプレイする際には、胸から腹にかけての「ふた」を外した状態(内臓露出状態)を想定しているのでしょうが、でもそうでない形態も取りうるので、そうなると一寸猟奇的というか、倒錯的な雰囲気が漂います。
要するに、エディさんは「ねえさん」か「にいさん」か曖昧なひとで、男女の境界を軽々と越える、まさに完璧なアンドロギュヌスと呼びうる存在なのです。
★
エディさんは、スペースの都合で現在は物置にしまわれています(今日は撮影のために久しぶりに再会)。改めてこれを聖像として部屋に祀り、その前でヘルメス的な、ネオプラトニズム的な、錬金術的な秘儀をとりおこない、暗黒の知のネットワークに参入し……
今宵の妄想はここまで。
驚異の部屋を持つ ― 2010年03月05日 21時58分54秒
例年のことですが、3月はバタバタする月で、今年もやっぱりバタバタしています。
そんな中で、あえて暇そうなことを書いて、暇な気分を味わおうと思います。
★
驚異の部屋というのは、見て良し、作って良し。
何にせよ、身近にあれば云うことなしです。
そんな今様ヴンダーカンマー作りを志す人は、海外にも少なからずいるようで、そういう人の部屋を拝見すると、そこに嗜好の違いはあれども、なんだかとても親近感を覚えます。
医学・解剖系は、私のちょっと苦手な分野ですが、その手の世界に特化したブログに、Morbid Anatomy(http://morbidanatomy.blogspot.com/)があります。ここは以前Tizitさんに教えていただいたサイトで、前にもちらとご紹介しました。
そのブログ主である、ニューヨークのブルックリン在住のグラフィック・デザイナー、ジョアンナ・エーベンスタインさんのアトリエが、WEB上で紹介されているよ…というのが今日の話題です。
■Morbid Anatomy Library
http://newyork.timeout.com/articles/halloween/79539/morbid-anatomy-library
ヴンダーカンマーというほどの稠密感はなくて、割とあっさりしている印象も受けますが、それでもなかなか安楽そうな雰囲気です。博物系の品はとりあえずそのままとして、ここに並んでいる解剖系の品を天文系のアイテムに置き換えたら、「天文古玩」的には言うことなしですね。
記事を読むと、珍奇コレクション作りを目指す人に向けた、エーベンスタインさんからのアドバイスが載っています(以下、適当訳)。
◆◇◆
1 常に目を皿のようにしてモノを探すこと。「全く何もなさそうな場所
も含めて、とにかくどんな所でもよーく見てみましょう。捨てられている
モノも怖れずに!」
2 「一般人」の意見には決して耳を貸さないこと。「どんなに他人が
気持ち悪いと思おうが、自分の感じ方に素直にふるまいましょう。」
3 自分も死ぬという事実に向き合うこと。「死について思いを巡らす
ことは、良い決断を下す助けになります。私は飛行機に乗るのが怖いん
ですが、これは私の生き方そのものにも影響を与えています。もし死に
ついて考えることいがなければ、私はたぶん下らない仕事にかかりきり
になっているでしょうね。」
4 エーベンスタインさんの力を借りることもお忘れなく。「当ライブ
ラリーの開館時間に是非お出でください。これらの高価な本は全部私が
買ったもので、ここにはよそではちょっと見られないアヤシイ世界があり
ますよ!」
◆◇◆
1番目と2番目の助言は、「驚異の部屋」作りにおいて大切なポイントでしょう。
というよりも、今ふと思ったんですが、3番目の助言も含めて、これは千利休が言いそうなセリフじゃないでしょうか。驚異の部屋の要諦は茶道の極意に通じたり。
そう言えば、東大の「驚異の部屋展」の企画者・西野嘉章氏が、展覧会をお茶会に譬えていたのを思い出しました(http://mononoke.asablo.jp/blog/2008/08/02/3669587)。
価値はモノに備わっているというよりも、人間が積極的に付与するものであること。そして人間の有限性が、その価値を一層豊かならしめていること。それを鋭角的に表現したのが「驚異の部屋」であり、茶の道なのではありますまいか。
そんな中で、あえて暇そうなことを書いて、暇な気分を味わおうと思います。
★
驚異の部屋というのは、見て良し、作って良し。
何にせよ、身近にあれば云うことなしです。
そんな今様ヴンダーカンマー作りを志す人は、海外にも少なからずいるようで、そういう人の部屋を拝見すると、そこに嗜好の違いはあれども、なんだかとても親近感を覚えます。
医学・解剖系は、私のちょっと苦手な分野ですが、その手の世界に特化したブログに、Morbid Anatomy(http://morbidanatomy.blogspot.com/)があります。ここは以前Tizitさんに教えていただいたサイトで、前にもちらとご紹介しました。
そのブログ主である、ニューヨークのブルックリン在住のグラフィック・デザイナー、ジョアンナ・エーベンスタインさんのアトリエが、WEB上で紹介されているよ…というのが今日の話題です。
■Morbid Anatomy Library
http://newyork.timeout.com/articles/halloween/79539/morbid-anatomy-library
ヴンダーカンマーというほどの稠密感はなくて、割とあっさりしている印象も受けますが、それでもなかなか安楽そうな雰囲気です。博物系の品はとりあえずそのままとして、ここに並んでいる解剖系の品を天文系のアイテムに置き換えたら、「天文古玩」的には言うことなしですね。
記事を読むと、珍奇コレクション作りを目指す人に向けた、エーベンスタインさんからのアドバイスが載っています(以下、適当訳)。
◆◇◆
1 常に目を皿のようにしてモノを探すこと。「全く何もなさそうな場所
も含めて、とにかくどんな所でもよーく見てみましょう。捨てられている
モノも怖れずに!」
2 「一般人」の意見には決して耳を貸さないこと。「どんなに他人が
気持ち悪いと思おうが、自分の感じ方に素直にふるまいましょう。」
3 自分も死ぬという事実に向き合うこと。「死について思いを巡らす
ことは、良い決断を下す助けになります。私は飛行機に乗るのが怖いん
ですが、これは私の生き方そのものにも影響を与えています。もし死に
ついて考えることいがなければ、私はたぶん下らない仕事にかかりきり
になっているでしょうね。」
4 エーベンスタインさんの力を借りることもお忘れなく。「当ライブ
ラリーの開館時間に是非お出でください。これらの高価な本は全部私が
買ったもので、ここにはよそではちょっと見られないアヤシイ世界があり
ますよ!」
◆◇◆
1番目と2番目の助言は、「驚異の部屋」作りにおいて大切なポイントでしょう。
というよりも、今ふと思ったんですが、3番目の助言も含めて、これは千利休が言いそうなセリフじゃないでしょうか。驚異の部屋の要諦は茶道の極意に通じたり。
そう言えば、東大の「驚異の部屋展」の企画者・西野嘉章氏が、展覧会をお茶会に譬えていたのを思い出しました(http://mononoke.asablo.jp/blog/2008/08/02/3669587)。
価値はモノに備わっているというよりも、人間が積極的に付与するものであること。そして人間の有限性が、その価値を一層豊かならしめていること。それを鋭角的に表現したのが「驚異の部屋」であり、茶の道なのではありますまいか。
囲繞する何か(17)…闇に立つ人 ― 2010年01月09日 19時45分26秒
囲繞する、何か(13)…混沌たる理科室幻景 ― 2009年11月12日 23時13分52秒
世界のヴンダーショップ(3) ― 2009年07月19日 10時56分24秒

(↑公式サイトより)
昨日の記事が長かったので、ちょっと一息。
★
見つけました、新たなヴンダーショップ。
というか、最近既出のお店です(http://mononoke.asablo.jp/blog/2009/07/03/4411040)。
パリはデロールの近くにある「古書+骨董」の店、Librairie Alain Brieux。
今回、再度載せる理由は、flickrで店内の写真を大量に見て、強い衝撃を受けたためです。
前回、動画を眺めて「店内の雰囲気はよく分かる」と書いたのですが、実際にはあんなものではなくて、想像以上にヴンダーなお店でした。というわけで、ここで改めてヴンダーショップ第3号に登録です。
■flickr:Librairie Alain Brieux
http://www.flickr.com/photos/astropop/sets/72157615898247967/
(右上にslide show ボタンがあります。)
デロールとは別の意味ですごい世界ですね。
天文系ももちろん充実していますが、それ以上に医療・解剖系の濃度が高めなので、苦手な方は用心して見てください。
同店には公式サイトもある由ですが、現在はまだ工事中の模様。
■Librairie Alain Brieux公式サイト
http://www.alainbrieux.com/
パリ訪問の機会があるまでぜひ存続してほしいスポットです。
【長ーい付記】
うつけでした。
さきほど記事をアップしてから気付いたのですが、上の flickr のフォトストリームは、先日コメント欄で Tizit さんに教えていただいた、解剖メインの博物系ブログ Morbid Anatomy (http://morbidanatomy.blogspot.com/)のブログ主、Joanna Ebenstein 氏の手になるものでした。微妙なシンクロニシティの作用ですね。
Ebenstein 氏のフォトコレクションは、まさにその手の驚異に惹かれる人にとっては、「解剖趣味のカリフォルニア」とも呼ぶべき豊饒の地でしょう。
★Morbid Anatomy (on FLICKR)
http://www.flickr.com/photos/astropop/collections/72157601772904023/
その手のものが苦手な方(私もどちらかといえばそうです)にも↓はお勧めです。
★Teylers Museum, Haarlem
http://www.flickr.com/photos/astropop/sets/72157612836663492/
18世紀末に創設された、オランダ最古の博物館、Teylers Museum の館内写真集。
味のあるケースやガラスドームに収められた、古い科学機器、鉱物、化石のたたずまいがとても美しい。
なんだか、人のふんどしを何枚も重ね履きして相撲を取ってしまいましたが、近頃ちょっと驚いたことでした。
昨日の記事が長かったので、ちょっと一息。
★
見つけました、新たなヴンダーショップ。
というか、最近既出のお店です(http://mononoke.asablo.jp/blog/2009/07/03/4411040)。
パリはデロールの近くにある「古書+骨董」の店、Librairie Alain Brieux。
今回、再度載せる理由は、flickrで店内の写真を大量に見て、強い衝撃を受けたためです。
前回、動画を眺めて「店内の雰囲気はよく分かる」と書いたのですが、実際にはあんなものではなくて、想像以上にヴンダーなお店でした。というわけで、ここで改めてヴンダーショップ第3号に登録です。
■flickr:Librairie Alain Brieux
http://www.flickr.com/photos/astropop/sets/72157615898247967/
(右上にslide show ボタンがあります。)
デロールとは別の意味ですごい世界ですね。
天文系ももちろん充実していますが、それ以上に医療・解剖系の濃度が高めなので、苦手な方は用心して見てください。
同店には公式サイトもある由ですが、現在はまだ工事中の模様。
■Librairie Alain Brieux公式サイト
http://www.alainbrieux.com/
パリ訪問の機会があるまでぜひ存続してほしいスポットです。
【長ーい付記】
うつけでした。
さきほど記事をアップしてから気付いたのですが、上の flickr のフォトストリームは、先日コメント欄で Tizit さんに教えていただいた、解剖メインの博物系ブログ Morbid Anatomy (http://morbidanatomy.blogspot.com/)のブログ主、Joanna Ebenstein 氏の手になるものでした。微妙なシンクロニシティの作用ですね。
Ebenstein 氏のフォトコレクションは、まさにその手の驚異に惹かれる人にとっては、「解剖趣味のカリフォルニア」とも呼ぶべき豊饒の地でしょう。
★Morbid Anatomy (on FLICKR)
http://www.flickr.com/photos/astropop/collections/72157601772904023/
その手のものが苦手な方(私もどちらかといえばそうです)にも↓はお勧めです。
★Teylers Museum, Haarlem
http://www.flickr.com/photos/astropop/sets/72157612836663492/
18世紀末に創設された、オランダ最古の博物館、Teylers Museum の館内写真集。
味のあるケースやガラスドームに収められた、古い科学機器、鉱物、化石のたたずまいがとても美しい。
なんだか、人のふんどしを何枚も重ね履きして相撲を取ってしまいましたが、近頃ちょっと驚いたことでした。





最近のコメント